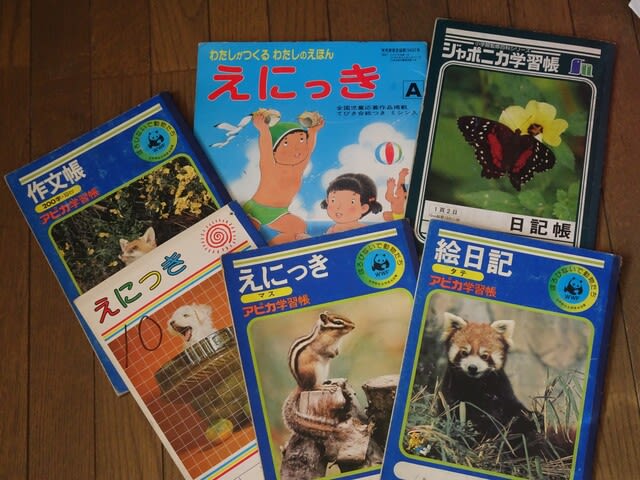毎年「セツブンソウ」を見に行っている木曽まで出かけました。木曽は寒いのでまだ早いかと思ったのですが、友人に会う約束もあって行ったところ、やはり早かったです(2/25) 。 それで、「奈良井宿」の散策をしてみました。奈良井宿の入り口の太鼓橋「木曽の大橋」です。

この下を流れる川は「奈良井川」…中央アルプス北部、楢川地区に源を発し、北へ進んで松本市まで行って梓川に合流、梓川は犀川となり長野市で千曲川に合流、千曲川は信濃川となって日本海に流れ込みます。ちなみに木曽川はこの近くの鳥居峠の向こう側から流れて太平洋に向かっていて、鳥居峠が中央分水嶺となっています。川のつららがみごとでした。

宿場内を歩いてみました。奈良井宿は約1kmもあって規模が大きく、「 奈良井千軒」と呼ばれて多くの旅人で賑わったそうです。(端から端まで往復2㎞!)ちなみにこの場所での歩数、5700歩もありました…ここは「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されています。

古い建物が保存管理され、かつての宿場の面影を今に伝えています。この宿場で特徴的な「出梁造り(だしはりつくり)」がみられます。これは梁が外部まで出て二階部分を支え、街道側に二階がせり出している建築様式です。



ここには6つの水場があって、中山道を行き来する旅人の喉を潤したり、生活用水や防火用水に使ったりしたようです。趣のある水場でした。





この宿場の建物には独特な建築様式があります。それがこの「鎧庇(よろいひさし)」と「猿頭」です。軒庇の板を重ねて並べた様子が鎧のように見えるから「鎧庇」で、庇板を押さえる桟木が猿の頭を並べたように見えるから「猿頭」だそうです。


この宿場には2軒の重要文化財があって、「手塚邸」と「中村邸」です。手塚家は上問屋、中村家は櫛問屋でどちらも天保年間建築の町屋です。


町家の特徴は出梁造りと間口が小さくても奥行きの長い造りです。


宿場内のお蕎麦屋さんに入ってみました。大きな梁が特徴的で注目でした。寒い日でしたので、囲炉裏の端で暖かいお蕎麦をいただきました。


こんな篭もさりげなく置かれていました。

この奈良井宿は今までに何度も来ているのですが、こんなに誰も歩いていない日は初めてでした。いかに観光客が減っていることかと、心配になりました。見かけた七福神…厄払い、招福を願いたいところです。

狸の置物もマスク姿…早くマスクが取れる日が来て、観光客も戻ってくるといいのですが…

最後にここのマンホールの蓋…楢川村(現在は塩尻市)の村の魚「岩魚」と村の木「楢」が描かれています。

ここで山の風景も…まずは木曽へ行くのに通った塩嶺峠からの北アルプスです。


塩尻市桔梗が原付近からの北アルプスです。この付近はブドウの産地です。


目的の一つだった「セツブンソウ」…さすが木曽は寒くて、雪も残る群生地のセツブンソウはまだまだ蕾でした。



帰りにまた立ち寄ってみたら、一つだけ開きそうな花を見つけました。でも咲き始めるのは後一週間くらい先のことかと眺めてきました。


ここでは梅もまだ固い蕾でした。

ここの日当たりのよい土手に咲く「福寿草」…福寿草の方が節分草より咲き初めの時期が早く、ちょうど咲いていました。


落ち葉を突き抜けて、咲いたばかりの福寿草…


春一番のこの明るい黄色の花を見て、寒い木曽にも春の訪れの兆し…と嬉しくなりました。