友人と電話で庭の植物の話をしていると「そうだ、私は今からアロニアを収穫に行かねばならない」と言い出した。さらに話しているとそれほど遠くないところにアロニアを作る農園の話になり行ってみようということになった。何だか天気も上々なので作業場にこもっているのは酷くもったいない気分だったのだ。この天気はどうせ数日しか持たない。。。とつい天気については悲観的になってしまう癖が長年の間についてしまった。天気予報を見ると珍しく4,5日続きで快晴マークが気持ちよく並んでいる。驚きだ。恵みだ。これで作業場にこもっていては残念すぎる。(以上言い訳)


アロニアはビタミン豊富で最近見直されている果実だが、酸味と渋みが強く生食しても美味しくは無いし、種には青酸が含まれるので向かない。(そういいながらも何粒か食べてみた。酸味強くかすかな甘みがあり渋みがが最後に残る)果実汁、ゼリーやリキュールにすることがおおい。危ない成分を含むとはいえ、この果実はビタミンK,Cが豊富で鉄、ヨードなどのミネラルも含有し抗癌作用のある健康食品として最近もてはやされている。ロシアでは高血圧、皮膚病そして神経的病にも良いとされて親しまれているという。


今年は友人の庭のアロニア・メラノカルパも豊作だった。少しだけ貰ってきたのでこれでマルメラーデを作ろう。去年の秋には瀕死だった薔薇アブラハム・ダービーは切り戻して見事に復活し元気の良い新枝を沢山だして素晴らしい香りを放ちながら咲いていた。花に鼻を埋めてしばし恍惚とす。隣のトルコ人の庭には実らない枇杷の木(多分冬が寒いからなのだろう)があってそこから幾枚か葉をいただいてきた。これで又草木染も一寸しておきたい。


アロニアはビタミン豊富で最近見直されている果実だが、酸味と渋みが強く生食しても美味しくは無いし、種には青酸が含まれるので向かない。(そういいながらも何粒か食べてみた。酸味強くかすかな甘みがあり渋みがが最後に残る)果実汁、ゼリーやリキュールにすることがおおい。危ない成分を含むとはいえ、この果実はビタミンK,Cが豊富で鉄、ヨードなどのミネラルも含有し抗癌作用のある健康食品として最近もてはやされている。ロシアでは高血圧、皮膚病そして神経的病にも良いとされて親しまれているという。


今年は友人の庭のアロニア・メラノカルパも豊作だった。少しだけ貰ってきたのでこれでマルメラーデを作ろう。去年の秋には瀕死だった薔薇アブラハム・ダービーは切り戻して見事に復活し元気の良い新枝を沢山だして素晴らしい香りを放ちながら咲いていた。花に鼻を埋めてしばし恍惚とす。隣のトルコ人の庭には実らない枇杷の木(多分冬が寒いからなのだろう)があってそこから幾枚か葉をいただいてきた。これで又草木染も一寸しておきたい。































 城の装甲地下壕
城の装甲地下壕


























 ピンク花のすずらん。。。。初めて見た。
ピンク花のすずらん。。。。初めて見た。

 レベッカ・ホーンの作品。 羽ばたき舞い上がるトランクの内側にはユダヤの星と鳩が記されている。
レベッカ・ホーンの作品。 羽ばたき舞い上がるトランクの内側にはユダヤの星と鳩が記されている。




 近所の公園の栗の木を点検に行った。
近所の公園の栗の木を点検に行った。






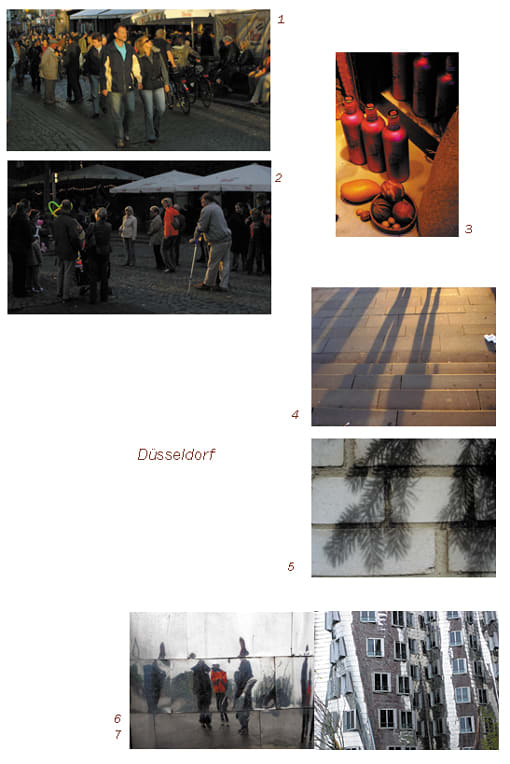
 空には時々ドラマチックな雲が現われる。
空には時々ドラマチックな雲が現われる。 この角度で取られた写真が世の中にうんざりするほどあるはずだ。この角度から撮るまいと思っていながら、つい一枚撮ってしまった。
この角度で取られた写真が世の中にうんざりするほどあるはずだ。この角度から撮るまいと思っていながら、つい一枚撮ってしまった。





