
ブクログより
いやぁ、このシリーズも7作目なんですね。
大阪の呉服屋五鈴屋が、とうとう東京進出を果たしました。
東京と大阪とでは、気質が違うように帯の巻き方、好まれる着物の柄と違うことが多く、戸惑いながらも、女名前を許された7代目店主幸とそれを盛り立てるみんなの奮闘のおかげで、何とか軌道に乗り出します。
他店と違うものをと模索するうち、武士の柄だった小紋を町民にと思い付き、型彫師、型染め師、型紙と皆の奔放のおかげで、ようやっと初の小紋地が仕上がりました。
しかし、問題は、難題は尽きず、今後の五鈴屋の跡目は?
なんと失踪したあの人が生きていた?
などなど、話はまだまだ続いてくれそうです。
もうしばらく楽しめそうです。
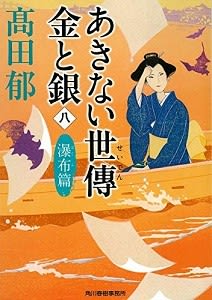
同じく
遠目には無地、近づけば小さな模様が浮かぶ小紋染め、
武士のものとされてきたそんな小紋染めを町人にもと取り組んできた、五鈴屋江戸店の面々。
努力の甲斐あって、それは江戸っ子たちの支持を得て、順調に行くと思いきや、出る杭は打たれるで同業者から、真似をされたり、職人の世話をしろだの、難題が持ち上がりますが、みんなが広めなければ小紋は定着しないと、慌てることなく鷹揚に構える頼もしい7代目幸ですが、来春には女名前を返納して、8代目に譲らなければならない。八代目の人選、妹結の思い等々、幸の気苦労は絶えないものの、
なんとなく明るい兆しが見え始めてきて、シリーズも8作目となり、いよいよこの物語も大詰めという感じがしてきました。
ああそれにしても何という終わり方!!
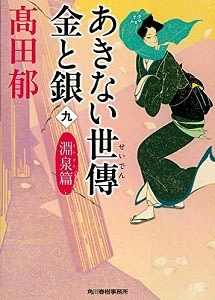
同じく
「人生あざなえる縄のごとし」という言葉があります。
生きているうちは幸運と不運が交互にやってきて、人生を終える時には、その数は同じトントンだった。ということですが、この主人公の人生もまさにこの通り、やっと希望が見えてきたと思ったらどん底に突き落とされ、またそこから這い上がって、の繰り返し。
前作、妹の結ができたばかりの小紋の型紙を持って行方不明になったところで終わりました。
やはり意図あっての出奔で、なんと嫁にと請われていた男のもとへと駆け込んだのでした。
そこで、その型紙をもとに、五鈴屋とそっくりそのままの商いを始めたのです。
え~今までの恩を忘れてなんで其処までせなあかんの?
結いには結のつらい思いがずっとあったんだすて。
そのうえ、よその客を横取りしたとかで、五鈴屋は呉服組合からはじかれてしまいました。
ピンチ!
もう絹物は扱えないんだそうです。
太物といって、木綿地しか扱えない、庶民には良いけれど、お値段が違います。
客層も変わり、だんだんジリ貧になっていきます。
がそれでくじける幸ではないんです。
歌舞伎役者の楽屋で着る木綿地の着物からヒントを得て、これを庶民にも広げられたらとひらめくんですね。お~素晴らしい、こんなところから開発されたんですかね。
皆が打ちひしがれているときに偶然店に現れた学者は、実は幸の故郷の父や兄の知り合い。
その学者が言います。
衰颯的景象 就在盛満中
撥生的機緘 即在零落内
衰える兆しは最も盛んなときに生まれ、新たな盛運の芽生えは何もかも失ったとき、すでにある。
だからこそ君子たるもの、安らかなときには油断せず、一心を堅く守って次にくる災難に備えよ。と菜根譚から来ているこの言葉を送られ、どんなにか心強かったことでしょう。
あぁ、いよいよ終盤が見えてきた気がします。

























