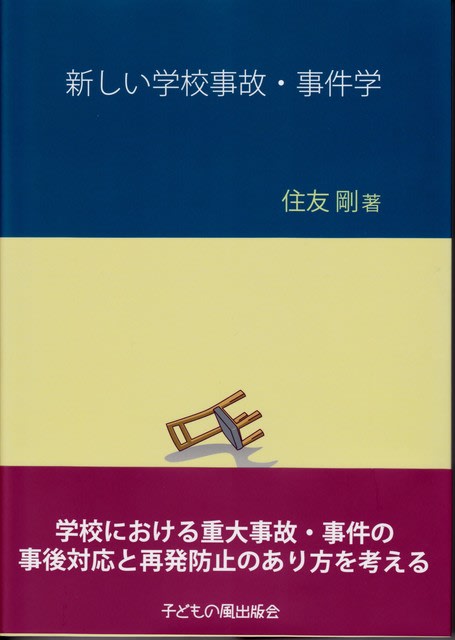今朝の朝日新聞の特集記事に、私のコメントがでています。
有料記事ですが、下記のとおり、このブログでも紹介しておきます。
学校死亡事故、検証報告は1割未満 遺族に募る「なぜ」(朝日新聞デジタル2019年5月5日配信)
さて、今回のこの記事ですが。
「学校事故対応に関する指針」がでてから3年が過ぎて、事故に関する調査・検証作業はどんな現状なのか?
そんな課題意識をもった朝日新聞のある記者さん(+それをサポートする記者さんたち)の、かなり力の入った特集記事です。私も、コメント部分を含めて、いろんなかたちで取材に協力させていただきました。
その上での話なのですが、学校で子どもの死あるいは重度障害が生じるような事故・事件に関して、今、起きている問題は、この記事で示しているとおり、「いじめ」対応も「自殺」防止も、そして事故・事件・災害対応に関することでも、「まったくといっていいほど、同じ」パターンをたどっています。
また、「今、起きている問題」を改善するために国レベルでやっている取り組みや、国レベルでの取り組みをすすめるよう働きかける人々の動き(=そこには遺族や被害者家族サイドからの動きも入っています)についても、「まったくといっていいほど、同じ」パターンをたどっています。
つまり、重大事故・事件の発生を契機にマスコミが動き、政治や行政が国レベルで動いて、一応「法律」なり「指針」なりをつくって、「調査・検証作業をやるべし」という方向にこの数年、動いてきたわけですが…。
「そうやっていくら国レベルで法律や指針を整備したところで、学校現場や地方教育行政はその法律や指針の趣旨どおりには動かない、動けない」ということ。
この課題が、年々、浮上しつつあるということです。
おそらく今後はこの「法律や指針の趣旨どおりには動かない、動けない」背景に何があるのかを解明して、そこから手をつけていく作業をしていく。その作業を最優先的にするべきでしょうね。
また、この作業を最優先的にするためにも、私たち研究者も自分たちの日頃の枠からどんどんはみ出して、どんどん学校現場や地方教育行政のなかに入っていき、教職員や行政職員の頭と体と心がどうなっているのかを掴み取って、彼ら彼女らとともに実務的に課題を解決していく作業をしていかなければいけません。
教職員や行政職員といっしょに痛い目にあいながら、それでもなお調査・検証作業を通じて「これだけは」と思うものをつかみとって、いっしょに再発防止策を実施していく。そういう研究者・専門職のあり方が、今後の重大事故・事件の防止には必要だと思います。
今後は「火の粉をかぶらない」ような安全地帯に自らを置いて、数字と事例で「こうすればいいのに」と論評しているだけでは、もはや、学校事故・事件に関する諸課題の何も変えられない、変わらないと思います。また、あいかわらず、そういう研究者・専門職がマスコミレベルなどでももてはやされ、ネットでも注目されたりしている現状が、本当に情けない限りです。
それと同様に、たとえばマスコミを動かして学校や行政の対応をただ今までと同じように批判して、国レベルでの政治・行政の動きを引き出して満足しているだけなら、従来通りの問題だらけの構造をより強化していくだけで、結局「なにも変わらない」で「イライラだけが募る」ということになってしまうように思います。
やはり、きちんと「実務」を掴まねば…と。あらためて私はそう思っています。他の人はどうだか知りませんが。
そして、「学校事故対応に関する指針」を作った側に居た以上、「実務」を掴んでこの指針を機能させるように動くのが、私の責務だと考えています。だから、私は学校や行政の実務担当者といっしょに、「火の粉」をかぶりながら仕事するしかないな…と思う今日この頃です。
<追記>
久しぶりにですが、併せて自分の本、『新しい学校事故・事件学』(子どもの風出版会、2017年)の宣伝もしておきます。上記のような課題意識を、ちょうど「学校事故対応に関する指針」をつくった直後にまとめて、本にして書いたものなので。朝日新聞の今日の「学校事故」特集の記事とあわせて読んでほしいです。