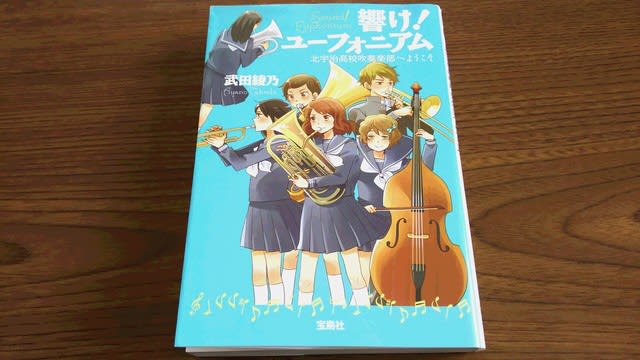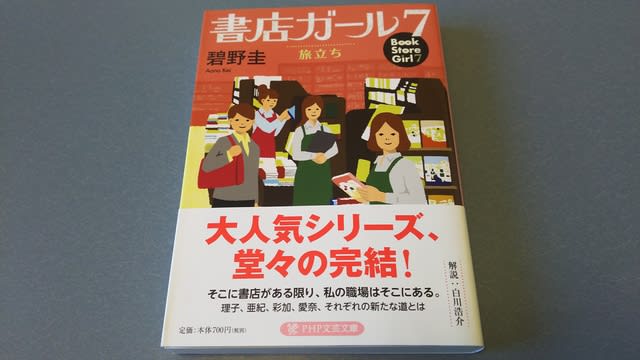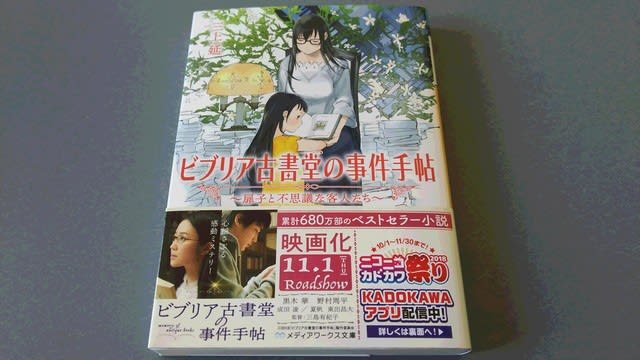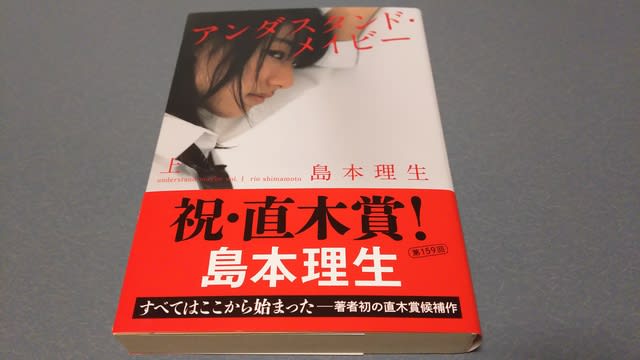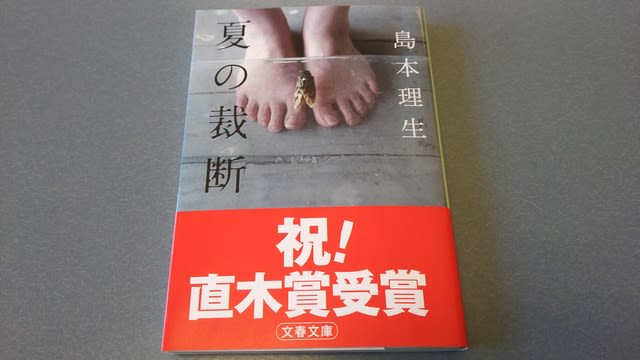今回ご紹介するのは「聖夜」(著:佐藤多佳子)です。
-----内容-----
学校と音楽をモチーフに少年少女の揺れ動く心を瑞々しく描いた School and Music シリーズ第二弾。
物心つく前から教会のオルガンに触れていた18歳の一哉は、幼い自分を捨てた母への思いと父への反発から、屈折した日々を送っていた。
難解なメシアンのオルガン曲と格闘しながら夏が過ぎ、そして聖夜――
-----感想-----
※以前書いた「聖夜」の感想記事をご覧になる方はこちらをどうぞ。
クラシックを中心にコンサートをよく聴くようになった今読むと以前読んだ時とは受ける印象が変わりました。
語り手は高校三年生の鳴海一哉です。
幼稚園、初等部から高等部、さらに大学まである私立のキリスト教系の学校に通っています。
メシアンという現代音楽の作曲家は、音を色として感じるそうだ。なんとなく、ぼんやり、という感覚ではない。音楽を聴きながら、鮮明な色のイメージと変遷が脳内に起こる。
これは音楽をよく聴くようになった今、興味深くて気になりました。
またコンサートでも演奏者がトーク中にオリヴィエ・メシアンの名前を出したことがあり、この作品のことが思い浮かびました。
冒頭、6月のある日一哉は毎日礼拝が行われるJT講堂という場所で二年の天野真弓のオルガン演奏を聴きます。
一哉は天野の弾くオルガンの音に興味を持っていて、二人ともオルガン部に所属していて一哉は部長をしています。
また一哉は一年のうちからどの先輩より弾けたとありかなりの実力者なのが分かりました。
「エリザベト音楽大学同窓会 佐伯区支部 第9回ハートフルコンサート」と「広島女学院 第22回クリスマスチャリティーコンサート」でパイプオルガンの生演奏を聴いた今、オルガンを演奏する場面がとても興味深かったです。
一哉は父が牧師、母が元ピアニストで、記憶のない頃からピアノやオルガンを触っていました。
オルガン部の他に聖書研究会にも入っています。
「俺はキリスト教を信仰していない。それでも、こんな学校にいる以上は宗教のど真ん中にいてやろうと思っている。」とあったのがひねくれた考えをしているなと思いました。
また自身を「揚げ足取りの名人」と表現していてやはりひねくれていると思いました。
ある日聖書研究会の集まりが終わるとオルガン部でも一緒の二年の青木映子が声をかけてきて、オルガン部に音大から先生が教えに来ることになる噂があると言います。
一哉の父が神父を務める教会は世田谷の住宅街にあります。
一哉の母の香住(かすみ)はドイツ人の男と出会い一哉が小学五年の夏に家を出て行きました。
香住が家を出てから半年くらいピアノもオルガンも弾かなくなっていたとありショックの大きさが分かりました。
一哉は父と母への気持ちを次のように語っていました。
母に通じることの全てに背を向けてピアノもオルガンも封印し、父に通じることも拒否して宗教からできるだけ遠ざかるようにすれば、楽なのだろうか。心の平安が得られるのだろうか。
母だけでなく、一哉が何かを話しても神父としての言葉しか言わない父にも嫌な気持ちを抱いていました。
音大のオルガン科の大学院に通う24歳の倉田ゆかりがコーチとしてやって来ます。
一哉は一人の女性を初めて見る時この女は俺を裏切るのかと思うようになったとあり、母が家を出ていったのは一哉の性格に大きな影響を与えていました。
それでも一哉は倉田を「自分より格段に技術のある演奏者」と評していて、認めているのが分かりました。
ただ倉田が自身を先生ではなくコーチと呼んでと言っても一哉だけ頑なに呼びたがらず、やはりひねくれていました。
倉田コーチが9月末の文化祭でコンサートをやろうと言います。
すると部員達が歓声を上げ、やはり音楽をやっている人にとってコンサートを開催できるのは嬉しいのだなと思いました。
コンサートをよく聴いている今読むと嬉しさが胸に迫ります。
一哉はオリヴィエ・メシアンを弾きたいと言い、倉田コーチは「すごいね。それは、すごいチャレンジだわ」と驚きます。
一哉は9歳の時に母が弾く『主の降誕』を聴いてそれがとても印象に残っていました。
倉田コーチが曲を何にするかを聞くと一哉は「『主の降誕』から、『神はわれらのうちに』」と答え、その『神はわれらのうちに』が母の演奏で印象に残った曲でした。
それぞれの部員が弾く曲も決まり、三年で副部長の渡辺がフランクの小品(しょうひん)、青木がメンデルスゾーン、天野がバッハ、一年の北沢が結婚行進曲になり、オルガン未経験の新入部員もごく短い曲を弾きます。
一哉は心の深いところからメシアンの名と曲が浮かび出てきたと胸中で語っていて、嫌な気持ちが胸を浸したともありました。
曲決めの時、倉田コーチが『神はわれらのうちに』を一度弾いてくれました。
メシアンで卒業論文を書いたとありましたが、そんな難しい曲をすぐに弾けるのはそれだけ上手い演奏者だということです。
またコンサートをよく聴くようになって大学の上級生や大学院生がどれくらい上手いかが分かるようになってきて、倉田コーチが上手い演奏を見せている様子が思い浮かびました。
一哉の呼び方が「倉田コーチ」に変わったのも印象的でした。
中学二年の夏前、一哉は父に「神が信じられなくなった」と言います。
一哉は教会の礼拝のオルガン演奏をしていましたが、父は神に捧げる音楽だから信仰がないと届かないので、オルガンはもう弾かなくて良いと言います。
一哉が毎日の日課で祖母にオルガンで弾いてあげている曲にムソルグスキーのピアノ曲『展覧会の絵』が登場しました。
ELPというロックバンドのキーボード奏者キース・エマーソンという人がこの曲を元にロックの曲を作り、一哉はそのロックの曲がかなり印象に残っていました。
7月になり夏休みになります。
自主練で一哉は天野の演奏を見て努力をしても手に入らない天性の才能かも知れないと思います。
そして天野に「生まれながらの演奏者」だと言い、自身の周りでそう思えるのは天野だけだと言います。
一方の天野も一哉の演奏を次のように言います。
「鳴海さんは、ただ、うまいっていうんじゃなくて、ずっとオルガンと暮らしてきたみたいな、すごくオルガンと親しいみたいな、オルガンでなんでもできるみたいな感じがするんです。自由な感じがするんです」
この二人は音楽家の素質のある人同士が引かれ合っているように見えました。
一哉は『神はわれらのうちに』を弾くと思い出したくない記憶が呼び起こされ、「どうも、メシアンのこの曲は危ない」と思っていました。
そして封印していた最悪の記憶を思い出します。
母が父と離婚してオリバー・シュルツというドイツ人と一緒にドイツに行くから一哉も一緒に行こうと言います。
一哉は衝撃を受け「その夜、突然、俺の世界が壊れた。」とあり、さらに次のようにありました。
十歳の俺は、あの夜、「罪」というものを初めて知った。
9月になり一哉は思うように弾けなくて苦しみます。
また「俺は、すべての音が、音符として聞こえる。」とあり絶対音感を持っていることが明らかになります。
そして音楽に関わる時に意外と感情をオープンにしていなかったことに気づき、もっと喜怒哀楽に身を任せても良いのだと思います。
一哉は『神はわれらのうちに』における自身のキーワードを神と母と考え次のように語ります。
信じられない神と、思い出したくない母。負のダブルだ。無理だ。弾けない。やっぱり、この曲は弾けない。
コーチも部員も非常に難しい曲をスムーズに弾けるようになった一哉を褒めてくれていましたが、一哉自身は演奏の出来に納得していませんでした。
文化祭になります。
ELPの『展覧会の絵』がきっかけで話すようになった深井という男子が一緒に文化祭を抜け出さないかと言います。
一哉は14時からオルガン部の発表会がありますが深井と学校を抜け出してしまいます。
深井が「おまえさ、自分で気づいてないみたいだけど、めちゃめちゃ音楽のセンス、あるんじゃないの?」と言っていたのが印象的でした。
深井と『アンバー』という凄く上手いアマチュアバンドのライブに行きます。
ライブ会場は新宿歌舞伎町の裏通りのビルの地下にある飲食店で、『アンバー』が登場するのは22時過ぎ頃です。
一哉は心配しているであろう家族、すっぽかした発表会のことが頭をよぎりますがそのままコンサートを聴きます。
二人はコンサートの後にキーボードの笹本さんと話すことになり、話を聞いて一哉はELPのキース・エマーソンのオルガンにナイフを突き刺すパフォーマンスに昔から抱いていた嫌な気持ちが解消されすっきりします。
次の日の朝、一哉が家に帰ると父と祖母が飛び出してきて二人とも凄く心配していました。
その夜、普段は神父としての言葉しか言わない父と胸を開いて話をします。
一哉は母のことについておよそ父らしくない生身の人間らしい感情を見せてもらって嬉しいと胸中で語っていました。
母の新たな事実も明らかになり、母について初めて希望が持てるものでした。
オルガン部のみんなには顧問の先生、倉田コーチを始めとして全員に一人ずつ謝りに行きます。
天野に謝ると次のように言います。
「いつか……。いつでもいいです。鳴海さんが、納得できるようになった時に、あの曲、聴かせてくださいね。私、本当に聴きたかっ……聴きたい!」
これを聞いた一哉は
聴きたかったと過去を責めるのをやめて、聴きたいと未来の希望を述べた。
と語っていて良い言葉だと思いました。
そして天野にクリスマス・コンサートでは何を弾くのか聞かれ、今度こそ『神はわれらのうちに』を弾くと答えます。
この小説はここからの明るい雰囲気が素晴らしかったです

一哉の言葉もそれまでとは変わって素直になります。
倉田コーチが交渉をしてくれて、学校敷地内にある学校本部の礼拝堂のパイプオルガンで二時間練習できることになり、普段は電子オルガンでの練習なので部員達は喜びます。
パイプオルガンは鍵盤を弾くことによりリコーダーに息を吹き込むように風を送ってパイプを振動させて鳴らす楽器とのことです。

(パイプオルガン。写真は「広島女学院 第22回クリスマスチャリティーコンサート」にて。)
パイプが長いものほど音が低いとあり、これはヴァイオリン属の楽器が大きくなるほど音が低くなるのと同じだと思いました。
パイプオルガンは世界中で一つも同じものはないと言われているというのも興味深かったです。
仕様が同じでも置いてある場所によってまるで響きが違うとありました。
天野のパイプオルガンの演奏を聴いた一哉は「音が生きている!」と感じていて印象的な言葉でした。
そして天野は一哉を探して目が合うと笑顔になり、一哉は「そう、花が咲くように笑う子だ」と表現していてやはり二人は引かれ合っていると思いました。
一哉も『神はわれらのうちに』を弾き、弾き終わると部のみんなが笑顔になってくれたのを見てクリスマス・コンサートはちゃんと弾こうと改めて決意します。
『神はわれらのうちに』には両手鍵盤と足鍵盤が全てリズムが違う場所があるとあり、コンサートで右手と左手で全く違うリズムで弾いているのを見て凄く難しいと思ったのに、さらに足鍵盤のリズムも違ったらとてつもなく難しいと思います。
深井とは「一緒にこれからも何かつながっていたいような気はする。」とあり、友達を作ることに興味のなかった一哉がこう思うのはかなりの変化だと思いました。
クリスマス・コンサートが明日に迫ります。
一哉はパイプオルガンを使ってのリハーサルで天野のことを「オルガンを介して、言葉では表現できないようなつながりが、俺たちには何かあるのだろう。」と胸中で語っていました。
そして一哉も『神はわれらのうちに』を弾きます。
このオルガンが弾けてよかった。
このオルガンを聴けてよかった。
この曲をやってよかった。
思うように弾けなくて苦しんだ末の、万感の思いの言葉がとても印象的でした。
オリヴィエ・メシアンの『神はわれらのうちに』の他にもムソルグスキーの『展覧会の絵』、さらにバッハやメンデルスゾーンなどクラシックの曲がいくつも登場したのが興味深くて聴いてみたくなりました

中でも『神はわれらのうちに』の両手鍵盤と足鍵盤が全てリズムが違う場所はどんな音色なのか興味深かったです。
そして今回この作品を読んで、途中で暗くなったりしながらも終盤になると一気に明るくなってフィナーレに向かうのはまるでクラシックの名曲のようだと思いました。
一度は『神はわれらのうちに』を弾きたくなくなっていた一哉が最後はこの曲をやって良かったと思っていたのが嬉しかったです

※図書レビュー館(レビュー記事の作家ごとの一覧)を見る方はこちらをどうぞ。
※図書ランキングはこちらをどうぞ。