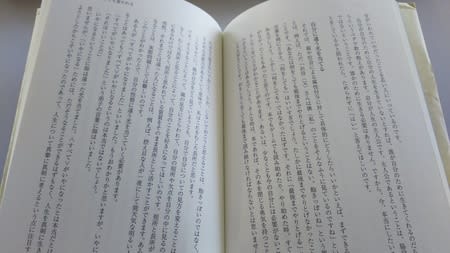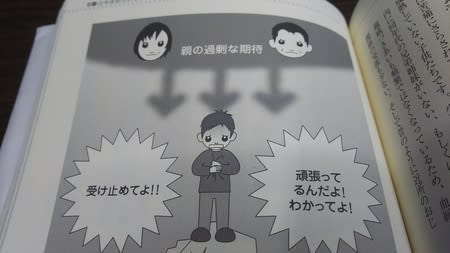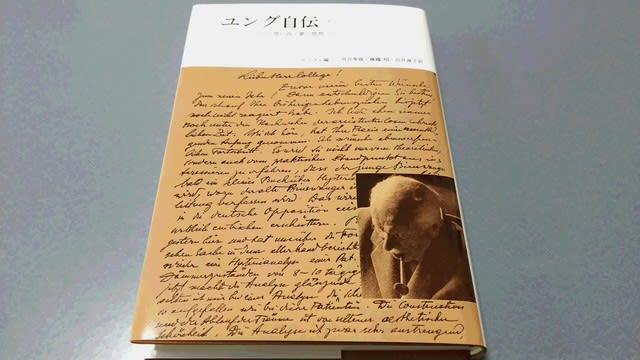
今回ご紹介するのは「ユング自伝 Ⅱ -思い出・夢・思想-」(編:ヤッフェ 訳:河合隼雄、藤縄昭、出井淑子)です。
-----内容&感想-----
※「ユング自伝 Ⅰ -思い出・夢・思想-」の感想記事をご覧になる方はこちらをどうぞ。
この本はジークムント・フロイト、アルフレッド・アドラーと並ぶ心理学三大巨頭の一人、カール・グスタフ・ユングの自伝の完結編です。
内容は一巻の「Ⅵ 無意識との対決」からの続きとなります。
一巻が少年時代から始まったのに対し、二巻はフロイトとの出会いと決別、そして人生の危機を経た後の中年時代から始まります。
「Ⅶ 研究」
「分析心理学について」
「分析心理学は基本的には自然科学である。しかし、それは他のどのような科学よりも、観察者の個人的な先入見に影響される」とありました。
観察者の個人的な先入見に影響されるのを認められるのがユングの良いところだと思います。
私は「私の心理学こそが最も自然科学的であり客観的である」とやけに声高に主張するような人より、「心理学は観察者の個人的な先入見に影響されやすいものだ」ときちんと認めた上で理論を構成する人のほうが信用できる気がします。
「錬金術の研究」
ユングは自身が夢に見たものがきっかけとなり、「錬金術」についての研究をしていくことになります。
これは単に錬金術に興味を持ったからではなく、まだ錬金術に出会う前に見ていた夢の中に、明らかに錬金術のシンボルであるものが登場していたことに気づいたからです。
全く知らないはずの錬金術のシンボルが夢に登場したということで、この体験はユング心理学の重要な考えの一つである「集合的無意識(普遍的無意識)」につながっていると思います。
「集合的無意識(普遍的無意識)」は人類全体が共通で持っている無意識のことで、例えば太陽を見ると神を連想することなどです。
「Ⅷ 塔」
ユングは心理学の学問的研究を続けていくうちに、自身の内奥の想いや得た知識を、「石」に何らかの表現をしなければならないと思うようになります。
そしてスイスのボーリンゲンに「塔」と呼ばれる石造りの家を建てていきます。
ボーリンゲンの塔での生活について、次の文章が印象的でした。
「私は電気を使わず、炉やかまどを自分で燃やし、夕方になると古いランプに灯をともした。水道はなく、私は井戸から水をくみ、薪を割り、食べ物を作った。このような単純な仕事は人間を単純化するものだが、それにしても単純になるということはなんと困難なことであろう。」
この「単純になるということはなんと困難なことであろう」は良い表現だと思いました。
水道も電気もない生活は単純作業を中心にした生活になりますが、その作業をしながらの生活は「単純」ではなくとても大変です。
Ⅶ章やⅧ章は一巻のようなユングの内面についての抽象的な文章は少なくなっていました。
「心について」
ユングは次のように語っていました。
「われわれの心は、身体と同様に、すべてはすでに祖先たちに存在した個別的要素からなり立っている。個人的な心における「新しさ」というのは、太古の構成要素の無限に変化する再構成なのだ。したがって肉体も精神も、すぐれて歴史的性格をもち、新しいもの、つまり今ここに生起するもののなかに、独自といえる個所はない。すなわち、そこでは先祖の要素がただ部分的にあらわれているにすぎないだけである。」
これはとても興味深い考えでした。
現在の私達の心はそれまでの人類の歴史によって形作られているということで、未来の人達の心には、現在の私達の心も歴史の一部となり組み込まれているのだと思います。
「Ⅳ 旅」
ユングは初めて非ヨーロッパの地、北アフリカに来ます。
かねてからアフリカに行ってみたいと思っていた念願が叶いました。
「時計について」
ユングの時計についての考えが興味深かったです。
「時計というものは、疑いもなく、無心な魂を脅かすようにたれこめた暗雲なのである。」
時計を暗雲としているのが印象的で、たしかに時計によって時間が刻まれていくのは漠然とした圧迫感があります。
「ヨーロッパ人について」
ユングはヨーロッパ人について、「ヨーロッパ人は軽薄」「ヨーロッパ人は合理主義傾向が強い」と特徴を語っていました。
自身もスイス人でありヨーロッパ人なのですが、ヨーロッパ人全体を軽薄と見ているのが印象的でした。
元々そう思っていて、北アフリカの人達を見て比較したら一層そう思ったようです。
「アメリカのインディアンについて」
ユングはアメリカにも行って先住民族であるプエブロ=インディアンに会います。
ユングがプエブロ=インディアン達に話を聞くと、彼らは太陽を神として崇め、毎日太陽が天空を横切るのを手伝うことが全世界のためになると本気で信じていました。
これが宗教の凄いところであり、この信仰に対し、「太陽が横切っていくのではなく、地球が自転しているから太陽が横切って行くように見えるのであって…」などと理論をぶつけても役には立たないです。
また、太陽を神と捉えることは「集合的無意識(普遍的無意識)」によって人類全体が神と捉える傾向があり、日本でも「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」という最高位の神様になっています。
「ケニヤとウガンダ」
次はケニヤとウガンダに行きました。
ウガンダでユングに「ここの国は人間のものではなく、神の国なのだ。だから、たとえどのようなことが起こっても、ただじっと坐っていて、心配することはない」と話しかけてきた人がいました。
これは「ウガンダは神によって守られている」と「病気などになっても神が見守っているのだから怖がることはない」の両方の意味かなと思います。
小屋で寝ているところをハイエナに引きずり出されて食べられてしまった老人がいました。
このことについてユングは「アフリカには確かなものは何もない」という言葉を使っていて、重く響きました。
ユングはこの地の黒人について「彼ら黒人たちは、相手となる人の表現とか、身振りとか、歩き方などを驚くほど正確にまねることができて、意図したり目的とするもののすべてを肌に感じてしまうらしい」と言っていました。
感性が凄く優れているようです。
これはユング達ヨーロッパ人に比べて文明が発達していない分その生活は自然とともにあり、それだけ感性が豊かなのだと思います。
この部族では太陽が姿を現す「日の出」を神として崇めていました。
プエブロ=インディアンと同じくここでも太陽に関するものが神となっていて、これらの経験からユングは「集合的無意識(普遍的無意識)」に気づいたようです。
「Ⅹ 幻像(ヴィジョン)」
ユングは1944年に心筋梗塞に続いて足を骨折し、意識不明になり生死の境を彷徨う経験をします。
そして意識不明になっている時、様々な幻像(ヴィジョン)を見ます。
その中でユングは宇宙空間から地球を見ている幻像を見ます。
そうしたら主治医のH博士が地球から宇宙空間にやってきて、ユングがこの世から立ち去ることには異議があると言っていました。
これはたまに聞く話で、生死の境を彷徨って「あちら側」に行きそうになった時、誰かが「まだ死ぬのは早い」と連れ戻しに来ることがあるようです。
ユングの話で興味深かったのはH博士が人間の姿ではなく、黄金の鎖か、あるいは黄金の月桂冠で作られたH博士の似姿という、「原初的な姿」で現れたことです。
ユングは次のように語っていました。
誰でもこういった姿になると、その人の死を意味している。それはその人は既に、『原初的な人たちの仲間』に属しているからだ。
原初的な人たちはこの世には存在しないので、その人たちの仲間に属しているということは、「あちら側」に行きかけているということだと思います。
ユングは意識が戻ってからH博士に死の危機が迫っていることを伝えようとしますが、H博士はまともには聞きませんでした。
そのすぐ後H博士は敗血症で亡くなってしまいます。
こんなことがあるので、生死の境を彷徨った時に見た幻像は重要な場合があるのだと思います。
「ⅩⅠ 死後の生命」
「合理主義と教条主義について」
ユングは次のように語っています。
「合理主義と教条主義は現代の病である。つまり、それらはすべてのことについて答えをもっているかのように見せかける。しかし、多くのことが未だ見出されるだろうに、それを、われわれの現在の限定された見方によって、不可能なこととして除外してしまっているのだ。」
また死後の世界については、「批判的な合理性は、死後の世界についての考えを多くの他の神秘的な考えと共に、除去してしまったようである。」と語っていました。
ユングは死後の世界を「そんなものはない」や「そんなのを考えても無駄」と合理的に片付けることには疑問を持っていたようで、死後の世界について真剣に考えていました。
「無意識」
「無意識(例えば夢)は、いろいろなことをわれわれに伝え、あるいは、比喩的なほのめかしによって、われわれを助けてくれる。」
ユングは無意識からこちらに送られてくるメッセージの力を借りて死後の世界について考えることができるのでは、としていました。
例として、「ある日突然誰かが溺れかけるイメージに襲われ、家に帰ってみたら孫の男の子が船小屋の水に落ちて溺れかける事件が起きていた」とありました。
「突然誰かが溺れかけるイメージ」はユングが頭の中で考えたものではなく、明らかに無意識が訴えてきたものなのですが、ユングはこれを「無意識がその他のこと(例えば死後の世界)についても、私に知らせを与えることが出来ないということがあるだろうか。」と言っていました。
これは興味深い考えで、例えば無意識がある日突然「誰かが溺れかけるイメージ」を訴えてくることがあるなら、同じくある日突然「死後の世界」のイメージを訴えてきても不思議はないと思います。
また「このような問題は、科学的、知的な問題からは、はずさねばならない」とも言っていました。
合理主義だと「科学的、知的でない問題など時間の無駄であり考える必要はない」で終わるのですが、そこをそうはせずに真剣に考えるのがユングの特徴です。
「ⅩⅡ 晩年の思想」
「善と悪」
この章ではユングの「善」と「悪」についての考えが書かれていました。
剥き出しの悪があちこちに台頭した20世紀について、ユングは次のように言っていました。
「悪を善の欠如などという楽観論によって見くびることはできない。悪はひとつの決定的な現実となる。婉曲な言いわけ(悪を善の欠如と言い変えること)によって、この世界から悪をとりさることは、もはや不可能である。われわれは、悪が、この世にとどまり存在しているからには、いかにそれを取り扱うかを学ばねばならない。おそろしい結果を伴わずに、われわれが悪と共にいかに生きてゆけるかは、今のところ、解らない。」
またユングはキリスト教を完全には信じていないので、「キリスト教の世界は今やすでに、悪の原理、むきだしの不正、専制政治、虚言、奴隷制度、良心の圧迫との対決を迫られている」とも言っていました。
調べてみたらキリスト教では悪のことを「善の欠如」としているようです。
ユングは「そんな言い変えによってこの世界から悪を取り去ることはもはや不可能」と言っていて、これはそのとおりだと思います。
そこを「そんなことはない」として信じるのが教徒、信じないのが非教徒なのだと思います。
「意識は二番目」
「意識は系統(人間という種族)発生的にも個体(人間一人ひとり)発生的にも、第二番目のものである。
今日の人間の体がその各所の部分にその進化の結果を示し、その早期の痕跡を各所に今なお示しているように、心についても同様のことが言えるのではないだろうか。
意識はわれわれにとって無意識と思える動物のような状態から進化を始めた。
無意識が一番目にあって、そこから徐々に意識が形作られていったというのがユングの考えで、これも興味深かったです。
たしかに人類になったばかりの頃の人間よりも、現在の人間のほうがだいぶ「意識」は進化しているのではと思います。
「ⅩⅢ 追想」
「人々が私を指して博識と呼び、「賢者」というのを、私は受け容れることができない。一人の人が川の流れから、一すくいの水を得たとして、それが何であろうか。私はその川の流れではない。」とありました。
権威主義的な面のあったフロイトとはだいぶ性格が違うなと思います。
ユングはこのように言っていますが、無意識という広大な川の流れの中からいくつものものをすくい上げ理論として打ち立てたのは凄いことだと思います。
「付録Ⅰ~Ⅴ」
付録Ⅰはフロイトからユングへの手紙、付録Ⅱはアメリカからユングが書いた妻のエンマ・ユングへの手紙、付録Ⅲは北アフリカからエンマ・ユングへの手紙です。
付録Ⅳはリヒアルト・ヴィルヘルムというユングと関わりのあった人物のこと、付録Ⅴは「死者への七つの語らい」というユングが若い頃に自費出版した本についてのことが書かれています。
フロイトの手紙にはユーモアを交えながらもフロイトの特徴である権威主義的な面が現れていました。
ユングの手紙は見た景色や船の上での状況の書き方が凄く表現力豊かでした。
心理学者であり心の研究をしていることのほかに、まだ携帯電話も電子メールもない時代だったのも影響していそうです。
手紙で状況を伝えるしかないため、自然と表現力が豊かなのかも知れないと思いました。
そしてここでも、「現在は便利にはなったが心の豊かさは失われた」の状態になっていると思いました。
一巻、二巻と読んでみて、ユングの物事の捉え方は子供の頃から常人とはだいぶ違っていたことがよく分かりました。
ユングに限らず偉人には少なからずその傾向のある人がいるのだと思います。
私は普段は主に小説の感想記事を書いていて、誰かの自伝の感想記事を書くのは初めてなのですが、初の感想記事が縁のあるユングで良かったと思います。
※図書レビュー館(レビュー記事の作家ごとの一覧)を見る方はこちらをどうぞ。
※図書ランキングはこちらをどうぞ。