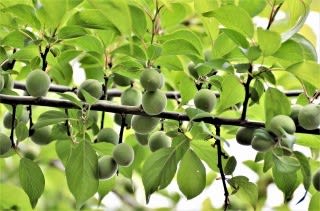あれから1週間過ぎた。報道では21万人が来場したという米軍岩国基地での航空ショー、その様子はアイ・キャンで見た。子どもが小学校低学年のころに1度行ったことがある。そのころは今のように記録に残せる方法は動かない写真が主流のころだったが、8㍉映写機を持っていたので動く映像が残っている。といっても編集後に見ただけでお蔵入りになっている。その時に驚いたのは垂直離着陸戦闘機ハリアーだった。
聞いてはいたが、垂直に着陸そして垂直に離陸、その直後にものすごい勢いで発進し飛行状態に移る、目の前で展開されるショーは、滑走路がなければ飛べない降りれないという飛行機のイメージをぶっ壊した。小学校時代に時始まった朝鮮戦争、B29爆撃機が、重い爆音を地上に注ぎながら朝鮮半島に向かっていたこととの差異に驚いたものだ。
垂直離着陸機など今では多機種あり物珍しさは失い、その性能が使用目的に合わせいかに優れているかをアピールする。垂直離着陸が可能でレーダーに探知されにくいステレス製の最新鋭戦闘機F35Bが米国以外で初めて岩国基地に配備され飛行している。極東の緊迫化に合わせ基地への不安が高まっているものの、万一の場合の市民に対する具体的な安全策は何も示されていない。7月以降には原子力空母艦載機の移駐か決まっており極東最大級の基地となり、さらに不安は増す。
航空ショーはカッコいいかもしれない。しかし、飛行ルート下では1時間に6回、轟音で会話を途絶えさせられた知人もいる。連日こんな轟音を浴びせられる基地周辺住民の苦悩にたいし観覧の人たちは想いをはせてほしい。訓練はショーではないため、飛行域は民家上空も海上も区別なく自由に飛行しているように思う。