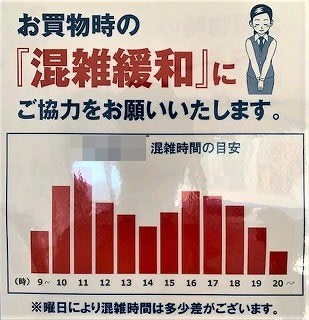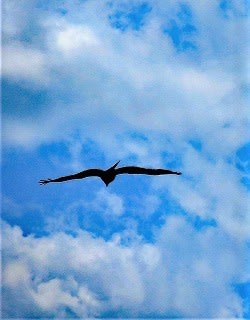新型コロナウイルスの感染防止策の一つとして在宅勤務が推奨された。大都市で50%だが地方ではその半分などと実施状況が報道される。在宅勤務は昔ホワイトカラーと呼んだ層が主で不可能な職種は多岐にわたる。その在宅勤務を阻害する一つに印鑑社会が挙げられた。TVインタビューでも何件か見た。印鑑社会を変える、世論はその流れになりそうだし、マスコミは世論に同調しているようで、印鑑文化の消える運命を感じる。
書類に印鑑がないとその書類は正式な役目を果たさない。特に役所関係に関わるものは厳しい。ある書類を工長調印(丸印)で提出したら不備という、理由は工場印(角印)がないということだった。印鑑がないととにかく仕事が前に進まない。しかし、印鑑制度にはいいとことがある。押印した人は責任を伴うということだ。決裁後に改ざん、さらに隠ぺいなどさせるようでは真摯な官僚とはいえない。
決裁書への押印を受けるためある課長のところへ出向いた。内容は調整すみで異はないが押印しながら「はんこの重さを考えたことがあるか」と聞かれた。私は担当者印なので重さということを考えたことはなかった。「小さな印鑑だが、これを押すことで責任は会社が続く限り背負うことになる。おろそかには押せない」、その課長は役員、そして社長へと昇った。
在職中は社内用として、社員番号と氏名を漢字で刻印した1㌢角で長さ6㌢の印が全員に支給されていた。社章入りのそれは通称「角印」。社内手続きと給与振り込みまでの受領印などすべてが角印で済んだ。電子印鑑や電子決済の時代になりつつある。それこそ判で押した書類になるだろう。ちょっと斜めに、少しかすれて、そんな癖のある押し方に味があった。デジタル決裁では味わえない。