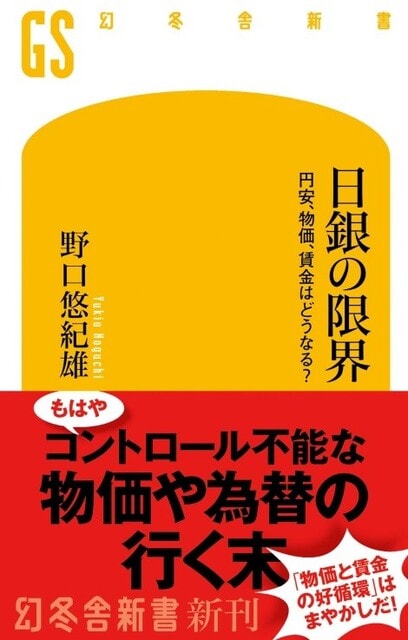
【 2025年2月22日 記 】
たまたま店頭で見かけた本だったが、自分の今の問題意識の沿う内容だったので買って読んでみたら、意外とわかりやすく一気に読んでしまった。
〇 〇 〇
主婦をしていない私にだって、最近のスーパーに並ぶ野菜の値札の金額には驚かされる。果物もおいそれと口にできない。リンゴもみかんも去年の2倍近い値が付いているし、しかも味といったら値段の高騰ぶりに比べたら特別美味しいわけでもない。コメに至っては最悪である。昨年の夏、店頭から米が消えた時の状況を思い出す。小売りの米屋(かつて自分の父親も米穀商を営んでいた)を覗いてみたら、店の奥に30kg入りの紙袋の米が天井近くまで積んであるのに、「あの米は売れない」と言って、カウンターの上に1つだけ置いてある2kg入りの米を指して「もう、これしか残っていない。」という。値段は2か月ほど前、スーパーで買った5Kg入りの物と同じくらいの値段だった。翌日炊く米が無くなっていたので、仕方なくそれを買って家に帰った。
別の米穀店の親父さんは「もうすぐ新米が出回るから、そうしたら前と同じように買えるから心配ない。それまで少し我慢してパンでも食べてりゃいい。」と無責任なことを言っていた。あれから半年、米は出回り始めたけど、値段は以前の水準に戻る気配はない。コメ作り農家が、その分潤っているようにも思えない。誰が儲けているのだろう? 案の定、新聞を見ていたら「商社などが買い占めて投機の対象にしているのではないか?」という報道があった。そして遅きに失した「政府の備蓄米放出」である。
そもそも農家に米を作らせない「減反政策」が間違いなのだが・・・。
〇 〇 〇
本の内容にかかわる本題に入ろう。
今年になって、近所の仲間うちで、【経済学-金融論】の勉強会を始めている。
失われた30年という言葉と同時に、日本の経済停滞がささやかれる中、円安が進み、日銀はようやく、その金融緩和の出口を探るような動きを
見せているように見えるが、何か釈然としない。物価高騰は収まる気配を感じさせないし、賃金はというと、「最近の春闘にない賃金上昇があった」
といわれるが、それを上回る物価上昇に到底追いつくとも思われない。
《ジャパン アズ ナンバー1》も《1億総中流》も《先進国・日本》も遠い昔の出来事のように思える。
「超金融緩和政策で《円安》を誘い、《インフレ率2%を目標にする》ことで経済の円滑化をはかる」という政府と日銀の思惑に、
どこか《まやかし》を感じていた。
このような問題を感じて始めた勉強会であったが、「やっぱりそうだったのか」という一定、確信めいた事が得られた。
本を手に取った一番のきっかけは、本の帯にある【「物価と賃金の好循環」はまやかしだ!】の文言だった。
春闘で賃金上昇が得られるのは良いことだが《それを上回る物価上昇があったら、元も子もない》と。賃金は商品である物価の原価の一部であるから当然のことだ。どうしたら、この《いたちごっこ》を解消できるか?
その答えは、《生産性向上によらない実質賃金の上昇は、持続できない》である。
本書の構成は以下のようになっている。
[はじめに]で
【なぜ異常な円高を止められなかったか?】
【「異常な円高」がもたらした「異常な経済」】
【どこまで円高になるか】
【生産性向上を伴わない「物価と賃金の好循環」はまやかし】
の項目を立て、円安誘導に導いた政府日銀の超金融緩和政策のまやかしを徹底批判し、最近の「物価と賃金の好循環」をもてはやす一部の報道にメスを入れている。
[第1章から第3章]までは
超金融緩和政策によってもたらされた「異常な円安」による弊害と、それがひき起こした「円の海外流失」と「新ニーサ」と「株の上昇」との関連で述べられ、
もはや日本はかつての【一流国の一員ではない】実態が明らかにされている。
[第6章から第8章]では、
【強欲資本主義】が《円安の元》で、如何に自分らの利益を増大させているかが記述されている。
[第9章、第10章]はそれらの克服課題が述べられている。
今より【円高がいいのか、より円安がいいのか】という論議や、【為替レートは《円:ドル》がいくらが適正か】という論議があるが、最終的には【購買力単価】がその基準になるということに納得する。
圧巻は、第6章から第8章である。黒田総裁から現在の植田総裁に代わっても、あれやこれやの理屈を並べて、金融緩和政策を改め、一向に金利を上げなかった背景には、やはり《大企業の意向》と《国債費の負担の増大》があったことが見て取れる。
【より円高が良いか】それとも【より円安がよ良いか】、あるいは【為替レートはどの交換レート】が適正かという問いに対する答えは無いと言えるかもしれない。
どのようなレートを取ってみても、【良い点】と【悪い点】は補間的であって、国全体で見れば帳消しになっている。
例えば、【円安の傾向】は輸出企業にとってみれば相手国の販売価格がより安価になり販売量が増えて利益が増大するし、海外旅行者にとっても日本に来れば、より少ない予算で日本での旅行が楽しめるからインバウンドを迎える観光業では有利である。しかし庶民にとっては食料品をはじめエネルギーなど輸入に依存している分野では《値上がり》が家計を圧迫する。逆の【円高の局面】では、反対の
現象が起こるが、【利を得る集団と損を被る集団が分断されている事】と【大企業・大資本家などが自分らにとっての負の部分】を【他の集団に転化する】ことで、富が偏在して、ますます貧富の差が拡大されていくということである。
具体的に言えば、自動車産業などで輸出が増え、空前の経常利益を出しても、その恩恵を労働者に賃金報酬の増額という形で還元しようとはしないし、逆に原材料や食料の輸入原価が上昇したら、その値上がり分を製品価格に転嫁して、自己の利益はしっかり確保する、というような事が、第6章から第8章にわたって記述されている。
まさに「強欲資本主義」である。
最後の2章は、これらの問題を克服するための問題点や、これからの展望についての章だが、新しい産業技術を切り開いていくことと、やはり教育の重要性が語られるが、それまでの章に比べるとやや迫力に欠けると自分には思える。
それでも、充分に示唆に富んだわかりやすい内容の、タイムリーな本だった。

























