
52系電車は1936年から1937年にかけて、京阪神地区固有の急行電車(急電)に使用することを目的に製造された電車です。基本設計は42系電車に準じますが、車体形状に当時世界的に流行していた流線型を取り入れ、当初は「魚雷型電車」と形容され、後には「流電」の愛称で親しまれました。後に阪和線では特急電車にも使用され、その高速性能を発揮。さらに、後述する高速試験にも使用され、電車による本格的な特急形車両開発の礎となりました。
京阪神緩行線向けに増備が続いていた42系を基本としつつも高速な急電用に特化し、また4両固定編成を組むことを前提に各部の設計が行われています。汎用性を重視する傾向が強かった戦前の鉄道省制式電車としては極めて異例のコンセプトに基づく車両です。
車体については全溶接構造となり、加えて側窓上下の補強用帯(シル・ヘッダー)を外板裏側に隠したノーシル・ノーヘッダー方式と、雨樋を屋根上部に移設した、張り上げ屋根方式を採用したこともあって、非常に平滑な、すっきりとした外観となりました。また、連結面は完全な切妻とされ、編成としての美観を考慮したデザインとなっています。

「流電」の象徴ともいうべき流線型の前頭部は、4組の板ガラス窓を円周上に配置したもので、裾部が丸め込まれた床下のスカートとともに、1933年8月より運行を開始したドイツ帝国鉄道(DRG)の「フリーゲンダー・ハンブルガー(Fliegender Hamburger)」用SVT877形(後のDB VT04形)電気式ディーゼル気動車の影響を強く受けた造形である。本家よりも明朗かつ流麗にまとめられており、その登場は他の幾つかの流線形車両とともに、日本の社会に流線形ブームを引き起こすほどのインパクトを与えています。
もっとも、本系列の動力性能(最高速度95km/h)では、流線形採用による空力的なメリットは十分得られず、機器の保守についてサイドスカートの着脱を必要としたことから保守陣から嫌われ、また乗務員扉を省略したことから客扱い上、様々な不便が生じたため、2回に分けて3編成12両が流線形仕様で製造されたにとどまり、急電運用に必要であった残り2編成8両については、52系と在来の42系を折衷した通常仕様で製造されることとなった。










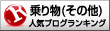



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます