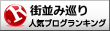堺市の元市議会議員、加藤均氏(85)が海上自衛隊第1術科学校に寄贈したサイパンで発見された旧海軍の艦載砲、日露戦争(明治37年2月8日~明治38年9月5日)に於いて、英国アームストロング社製「QF 6 inch /40 naval gun(40口径6インチ速射砲)」180門が輸入され戦艦・巡洋艦の副砲として使用された。これを準国産化した火砲が「安式四十口径六吋速射砲(アームストロング式40口径6イ . . . 本文を読む
「古鷹山」【標高394m】は、江田島市のシンボル的山であり、兵学校の背後に屏風絵のように聳えている秀峰です。名前の由来は、その昔一葉の小舟が荒れ狂う暴風雨のため難破寸前にせまった時、どこからか一羽の大鷹が現れ、波静かな入り江 (江田島湾)に導いて、小舟を助けた後、この山中に姿を消したことから、いつの頃から「古鷹山」と呼ばれるようになりました。明治21年の旧海軍兵学校江田島開校以後は、心身鍛錬のため . . . 本文を読む
91式徹甲彈と称し戰艦大和、武蔵の主砲用として使用されていたものです。当時は世界にその比を見ない最大のものであり 恐らく将来もこのような大きな彈丸は見ることが出来ないと思われます。この大きな彈丸を発射し得る砲で遠距離に飛ばす火薬、これを命中せしめる指揮装置、この彈丸自体に装甲板を貫く形状と材質があるわけでこの一発の彈丸に旧海軍が到達した用兵技術の極地が示されていると言ってもよいと思います。
大戰終 . . . 本文を読む
「にっこ」さんのブログで紹介のあった、教育参考館です。1936年(昭和11年)竣工。 鉄筋コンクリート造。 自己修養と学術研鑽の資とするため、兵学校卒業生の積立金及び一般企業等の寄付をもって建築された参考館です。見学時は脱帽、内部の撮影は禁止となっています。館の周辺には以前のブログで紹介させてもらった、特殊潜行艇をはじめ、貴重な展示物があります。日本人なら一度は訪れるべき所だと思います。
. . . 本文を読む
ここには、かつて初期の貸与護衛艦や「ちくご」型に装備された40mm連装機銃があったのですが今は跡しかありませんでした。どこかに移設したのでしょうか?
2ポンド砲 Mk IIは、旧日本海軍でも「毘式四○粍機銃」として艦載用に用いられているのですが、トラブルが多発し撤去され、フランスのオチキス(ホッチキス)系である十三粍機銃や二十五粍機銃に置き換えられたとのこと。
現物はなかったのですが…。
ス . . . 本文を読む
初期の貸与護衛艦や「いかづち」などに装備されたもの。第二次大戦中に米海軍が護送駆逐艦やフリゲート艦などに搭載した単装砲で、元をたどれば20世紀初頭に開発されたMk10単装砲に行き着く古い設計の砲です。バリエーションとして潜水艦搭載型なども存在するとのこと。 完全な人力操作の旧式砲であるが戦後は照準用レーダーが搭載されるようになっている。海上自衛隊でも米国からの貸与艦や初期の護衛艦(DEやPF)など . . . 本文を読む
戦艦「長門」40センチ主砲弾です。長門は太平洋戦争には日本海軍の旗艦として、ミッドウェー海戦、トラック島、マリアナ沖海戦、そして世界最大の海戦といわれるレイテ沖海戦に参戦し、その後、横須賀で終戦を迎えています。帝国海軍の軍艦は米軍に殆ど撃沈され、長門は横須賀に係留されたまま爆撃に曝される事になりますが、終戦の間際まで浮かんでいられた唯一の日本の主力戦艦となりました。
終戦で米軍に接収された「長 . . . 本文を読む
護衛艦「あやなみ」型2番艦の「いそかぜ」は、対潜任務に主眼を置いた対潜型護衛艦として建造された艦でした。同程度の艦では日本軍艦史上初めて長船首楼型を採用(これまでの日本軍艦では短船首楼型(艦橋直後で一段甲板が下がる)が主だった)しており、艦内スペースが拡大され、耐波性や復元性も向上している。後部マストの後ろで甲板が下がった部分は傾斜路となっており、この部分はオランダ坂とあだ名でした。
「はるかぜ . . . 本文を読む
駆逐艦「雪風」の錨です。雪風は、陽炎型の8番艦です。太平洋戦争を戦い、当時の艦隊型新鋭駆逐艦であった、朝潮型駆逐艦、陽炎型駆逐艦及びその改良型夕雲型駆逐艦、そして「島風」の計50隻の中で唯一終戦まで生き残った艦です。日本海軍の駆逐艦は、激戦区に投入され非常に損耗率が高かったが、本艦は16回以上の主要な作戦に参加し、戦果を上げつつほとんど無傷で終戦を迎え「奇跡の駆逐艦」と呼ばれました。敗戦後は武装を . . . 本文を読む
戦艦「金剛」「榛名」がヘンダーソン基地艦砲射撃(ヘンダーソンきちかんぽうしゃげき)に利用された砲弾です。1942年10月13日から14日、ガダルカナル島のアメリカ軍飛行場・ヘンダーソン基地への艦砲射撃をがおこなわれました。0時56分の「撃ち方・止め」までに、戦艦「金剛」は三式弾104発、徹甲弾(一式弾)331発、副砲27発の計462発。 戦艦「榛名」は零式弾189発、徹甲弾294発、副砲21発の . . . 本文を読む
日本三景である陸奥松島、安芸厳島(宮島)、丹後天橋立からそれぞれ松島(まつしま)、厳島(いつくしま)、橋立(はしだて)と命名された名を取ったことが三景艦(松島型防護巡洋艦)と呼ばれた所以です。
大国清国との衝突が避けられない時期、清国北洋艦隊の主力である砲塔装甲艦「鎮遠(ちんえん)」、「定遠(ていえん)」の2隻は、東洋最大級の主砲である30.5cm砲を4門も備え、対して24cm砲4門でしかない . . . 本文を読む
海軍中佐浅野卯一郎の発案による「海龍(海竜)」は、大日本帝国海軍の特殊潜航艇の一種で、敵艦に対して魚雷若しくは艦首の炸薬体当りにより攻撃を行う有翼特殊潜航艇・水中特攻兵器です。SS金物とも呼ばれました。
本土決戦用の特攻兵器として官民建造所で開発製造され、飛行機の部品などを使って横須賀の海軍工廠などでも、1945年(昭和20年)に全部で200隻が建造された。通常の潜水艦と異なり、翼を有し、飛行機 . . . 本文を読む
兵学校の艇は、伊号「第16号」「第18号」「第20号」「第22号」「第24号」潜水艦に搭載され、真珠湾攻撃作戦に参加した、5隻の中の1隻、実物である。この艇は作戦従事中に敵艦に発見、撃沈され、後に米軍に引き上げられた。そして終戦後、日本に持ち帰られ、頭部は新たに新造され復元展示されています。
特殊潜航艇は非常に小型の潜水艦の艇首に2発の魚雷を装填しているため、魚雷発射後に艇首が浮き上がって敵に . . . 本文を読む
昭和20年3月建造のT型駆逐艦「梨」に搭載されていたもので、九三式魚雷の発射管。 「梨」は昭和20年7月、米空母機の攻撃をうけて山口県沖で沈没した。
戦時急造型の小型駆逐艦で、松型といわれる。同型艦は約5ヶ月で建造されたが、かなりの被害を受けても沈没したものは少なかったという。「梨」は沈没したが戦後護衛艦「わかば」として再度海上自衛隊で活躍した。この発射管から発射される93式魚雷は世界に卓絶したも . . . 本文を読む