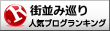河瀬駅は彦根市南西部の集落に位置する滋賀県彦根市南川瀬町、西日本旅客鉄道(JR西日本)東海道本線の駅です。
「琵琶湖線」の愛称区間に含まれています。日中時間帯は1時間あたり2本が停車いたします。駅周辺には上場企業・中小企業の工場・事業所が西口・東口に多く点在しています。
また滋賀県立河瀬中学校・高等学校、滋賀県立彦根工業高等学校の最寄り駅です。
単式ホーム1面1線と島式ホーム1面 . . . 本文を読む
83式地雷敷設装置は、陸上自衛隊の施設科に配備されている対戦車地雷敷設装置である。装甲車やトラックに牽引され、広範囲にわたり迅速に地雷原を構築できる。
対人地雷は国際条約で禁止され、自衛隊は保有していないので、対戦車地雷を敷設する。
時間あたり300個以上の地雷を敷設可能だが、自走能力は無いため73式装甲車や73式大型トラックなどで牽引して使用される。
全長:3900mm(走行状 . . . 本文を読む
昭和21年開業の宝珠山駅(ほうしゅやまえき)は、福岡県朝倉郡東峰村大字福井にある、九州旅客鉄道(JR九州)日田彦山線の駅です。
九州で唯一、プラットホームが県境をまたいでいる駅であり、ホームの3分の1が大分県、残りが福岡県にある。
大分県と福岡県の境界線には東峰村の特産である小石原焼の陶板が埋め込まれている。
東峰村の南端部に立地しており、村の中心地や村役場へは隣の大行司駅のほう . . . 本文を読む
南彦根駅は、国鉄末期(昭和56年6月)に開業した新しい駅です。滋賀県彦根市小泉町にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)東海道本線の駅です。「琵琶湖線」の愛称区間に含まれています。日中時間帯は1時間あたり2本が停車いたし、乗降客数は市内で彦根に次ぐ2番目となっています。駅の東南約1キロ程度の位置に近江鉄道の分岐駅高宮駅があります。
相対式ホーム2面2線を有する地上駅になっており、橋上駅舎です . . . 本文を読む
彦根駅は、滋賀県彦根市古沢町にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)・近江鉄道の駅です。県東部の主要都市、城下町彦根の代表駅で、駅前もそれなりに賑やかな市街地が広がっています。JR西日本の東海道本線と、近江鉄道の本線が乗り入れています。JR西日本の駅はアーバンネットワークエリアに属し、東海道本線は「琵琶湖線」の路線愛称設定区間に含まれています。またIC乗車カード「ICOCA」の利用エリアに含まれて . . . 本文を読む
南風(なんぷう)は、四国旅客鉄道(JR四国)、土佐くろしお鉄道および西日本旅客鉄道(JR西日本)が岡山駅 - 高知駅・中村駅・宿毛駅間を、宇野線・本四備讃線(瀬戸大橋線)・予讃線・土讃線・土佐くろしお鉄道中村線・宿毛線経由で運行している特別急行列車です。
岡山駅で山陽新幹線と接続し、本州と高知県を結ぶ列車です。特急「南風」は、1972年3月15日に山陽新幹線岡山開業にともなって行われたダイヤ . . . 本文を読む
阿波赤石駅(あわあかいしえき)は、徳島県小松島市赤石町にある四国旅客鉄道(JR四国)牟岐線の駅です。
駅番号はM07。駅周辺は住宅が多く、線内では利用客の多い。日本製紙小松島工場が近い。
単式ホーム1面1線を有する地上駅。以前は相対式2面2線であった。狭い場所にあるため、木造駅舎の側面(妻面)に入り口があります。
1972年(昭和47年)頃無人化された簡易委託駅です。
乗車券は . . . 本文を読む
壬生川駅(にゅうがわえき)は、愛媛県西条市三津屋にある四国旅客鉄道(JR四国)予讃線の駅。特急を含む全列車が停車する主要駅の一つです。駅名標のコメントは喜左衛門狸伝説の駅。特急停車駅を含め原則的に全列車が停車します。東予港(オレンジフェリー)へは車で10分。夜行便発着に合わせて無料連絡バスがある。
難読駅名だが、付近に川が多いことから「入川」と呼ばれていたことに由来する。(古代、付近で水 . . . 本文を読む
120mm迫撃砲 RT(フランス語: Mortier 120mm Rayé Tracté Modèle F1, MO-120-RT-61)は、フランス・トムソン-ブラーント社が開発した迫撃砲。口径120mmで、従来の軽榴弾砲に匹敵する射程を備えることで知られている。射程約10数Km。
開発は、トムソン-ブラーント社によって行なわれた。なお同社はタレス・グ . . . 本文を読む
立田駅(たてだえき)は、高知県南国市立田にある、土佐くろしお鉄道阿佐線(ごめん・なはり線)の駅である。駅番号はGN38。仮称は土佐電気鉄道安芸線に設けられていた駅名と同じ「日章駅」でした。
高知龍馬空港と距離的に最も近い駅である。開業前には分岐して空港に向かう路線も検討されたが採算が合わないとして断念された。宅地化が進行中。
片面1面1線のホームを持つ駅員無配置の高架駅である。ホームは . . . 本文を読む
豊後森駅(ぶんごもりえき)は、大分県玖珠郡玖珠町大字帆足にある、九州旅客鉄道(JR九州)久大本線の駅。玖珠町の中心駅で、久大本線の重要な拠点駅としての機能を持っている。
かつては恵良駅からの宮原線列車も発着していたが現在は廃線となっている。豊後森駅の近くに旧豊後森機関区の扇形機関庫である豊後森機関庫が残っている。車窓からは恵良方面進行方向右側に見える。
豊後森駅周辺は玖珠町の中心部にあ . . . 本文を読む
後免町駅(ごめんまちえき)は、高知県南国市大甲にある、土佐電気鉄道後免線の電停、ならびに土佐くろしお鉄道阿佐線(ごめん・なはり線)の駅です。
「ごめん」に対して「ありがとう駅」という愛称が付いています。
安芸方面に向かって右側に1面1線のホームを持つ駅員無配置の高架駅。
ホームは線路から見て南側にあります。
駅舎は設置されていないが、地上とホームはエレベーターで往復可 . . . 本文を読む
大正14年開業の後免駅(ごめんえき)は、高知県南国市駅前町二丁目にあります。
四国旅客鉄道(JR四国)、土佐くろしお鉄道の駅。南国市の代表駅です。JRの管轄駅(JR・土佐くろしお鉄道の共同使用駅)です。
全特急列車が停車します。駅番号はJR四国がD40、土佐くろしお鉄道がGN40である。JR後免駅の1日平均の乗車人員は1,844人(2006年度)。
これは高知県内の駅では高知駅に . . . 本文を読む
保線とは、鉄道や軌道の線路の保守を行うことをいう。鉄道(軌道も含む)の線路は、重量のある列車が走行するうちに寸法の狂い、磨耗が生じる。これを放置しておくと乗り心地や走行安定が悪くなり、酷くなると脱線の原因になるため、定期的に保守を行い、規定の状態を維持することで安全性を保つ。この一連の流れを保線という。なお、保線作業に用いる資材や車両を留置させておく基地を「保線基地」「保守基地」「基地線」など . . . 本文を読む
グレーダは、陸上自衛隊の施設科の装備。ブレード、スカリファイヤを利用した土木作業や除雪用のアタッチメントを取り付けて、交通作業、除雪作業などに使用される器材です。モーターグレーダー。
グレーダは民生品の流用であり市販品との性能的な相違はないが、陸上自衛隊のグレーダには全車に2個の黄色の回転灯が装備され、車体の塗装がオリーブドラブ色になっています。施設科の重機は様々な企業の製品が採用されて . . . 本文を読む