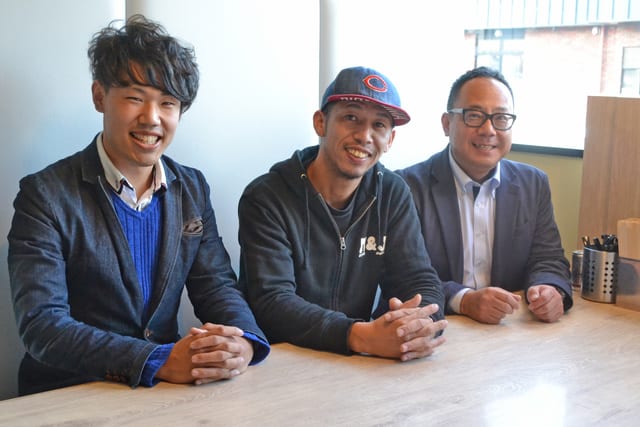週刊奈良日日新聞は、惜しまれながら平成31年4月26日(金)付を最後に休刊となった。私の連載「奈良ものろーぐ」も、この日が最終回(第37回)となった。最終回の見出しは「『古寺巡礼』百周年記念/『奈良百寺巡礼』を発刊」。本書は現在、啓林堂書店全店で新書部門ベストセラー1位、総合2位である(総合1位は『おしりたんてい』!)。本書の出版を記念して、同店では5月4日~6日まで、出版記念イベントが行われた。
本書は奈良県内および京都府南部のお寺(廃寺を含む)115ヵ寺を、すべて見開き2ページで紹介している。基本的には奈良検定テキストに掲載された寺院としたが、執筆者(全42人)が独自に取材した「かくれ寺」的な寺院もある。そのため本書は、今まであまり活字にならなかった小さなお寺に歓迎されている。中身もお寺に見てもらっているので、間違いはない。今回の本欄では、そのようなあまり知られていないお寺を10ヵ寺選んで紹介させていただいた。では全文を紹介する
 。
。
これら2枚の写真は啓林堂書店奈良店で撮影(5/4)、石田一雄さんと山﨑愛子さん
今年は和辻哲郎の名著『古寺巡礼』が発刊されて百周年の年だ。これを記念して奈良まほろばソムリエの会は、42人の書き手による『お寺参りが楽しくなる 奈良百寺巡礼』(本体980円+税)を京阪奈情報教育出版から発刊した(京阪奈新書)。今月18日には県庁で記者発表も行った。
お寺は基本的には『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』(山と渓谷社刊)に掲載の寺院としたが、掲載されていない寺もある。その中から10ヵ寺を選び、以下に紹介する。

表紙イラストは、童話作家・画家のなかじまゆたかさんに描き下ろしていただいた
▽璉珹寺(れんじょうじ 奈良市西紀寺町)
7世紀後半、飛鳥に創建され、その後平城京に移転した紀寺(きでら)の後身とも。ご本尊は光明皇后がモデルともいわれる木造阿弥陀如来立像(県指定文化財)。白く美しい裸形像で、50年に一度、袴(はかま)が取り替えられる。
▽不空院(ふくういん奈良市高畑町)
新薬師寺の東にあり鑑真和上は一時ここに住んでいた。空海も滞在し、興福寺南円堂のもとになる八角円堂を建てたとも。寺の鎮守だった宇賀弁財天女(室町時代の秘仏)が福をもたらすことから「福院」とも呼ばれた。近年「かなで奉納」「地蔵盆夏祭り」などで親しまれる。
▽極楽寺(安堵町東安堵)
納骨堂の木造阿弥陀如来坐像は、もとは原爆ドーム横のお寺に安置されていたもの。それが巡り巡ってこの寺に安置された。毎年8月6日の原爆の日には、ここでも法要が営まれ、犠牲者を追悼し平和を願う。
▽補巌寺(ふがんじ 田原本町味間)
室町時代に能楽を大成した世阿弥が禅を学んだ。門前に「世阿弥参学之地」の碑が立つ。
▽平等寺(桜井市三輪) 大神神社の神宮寺として栄えたが明治初年の廃仏毀釈で廃寺に。昭和52年、住職の托鉢行脚(たくはつあんぎゃ)により再興。関ヶ原の戦いに敗れた島津軍の14人を70日間かくまったことから、今も島津家との縁が続く。
▽音羽山観音寺(桜井市南音羽)
NHK「やまと尼寺 精進日記」に登場。約1kmの参道は、ある崇敬者が父親の満願成就に感謝し、平成3年から20年以上かけて木の根や岩を取り除いて道幅を広げ、石垣を築いて整備。
▽威徳院(明日香村尾曽[おおそ])
本尊の秘仏・毘沙門天像は毎年4月の第2日曜日に開帳。境内の高台には、四国をかたどった「四国八十八ヶ所霊場お砂ふみ道場」がある。
▽阿日寺(香芝市良福寺)
恵心僧都源信の誕生寺とされ「ぽっくり往生の寺」として知られる。源信は15歳のとき宮中で経典の講義をし、いただいた褒美を母親に送る。しかし母からは「仏法を自分の世渡りの道具としてはいけない」と戒められ、のち源信は念仏三昧の道を選んだ。
▽転法輪寺(御所市高天)
金剛山山頂付近に建つ。明治初年の神仏分離令・修験道廃止令で廃れるが昭和25年の役行者一千二百五十年遠忌を機に再興。
▽生蓮寺(しょうれんじ 五條市二見)
平安初期、嵯峨天皇の皇后が安産祈願のため地蔵菩薩を安置したことに始まるという。空海が高野山開創のとき立ち寄り小地蔵を刻み本尊胎内に安置したとも。境内では約120種類の蓮が育つ。
皆さん、これまで本欄37回(3年と1ヵ月)のご愛読、ありがとうございました!

本書は奈良県内および京都府南部のお寺(廃寺を含む)115ヵ寺を、すべて見開き2ページで紹介している。基本的には奈良検定テキストに掲載された寺院としたが、執筆者(全42人)が独自に取材した「かくれ寺」的な寺院もある。そのため本書は、今まであまり活字にならなかった小さなお寺に歓迎されている。中身もお寺に見てもらっているので、間違いはない。今回の本欄では、そのようなあまり知られていないお寺を10ヵ寺選んで紹介させていただいた。では全文を紹介する
 。
。これら2枚の写真は啓林堂書店奈良店で撮影(5/4)、石田一雄さんと山﨑愛子さん
今年は和辻哲郎の名著『古寺巡礼』が発刊されて百周年の年だ。これを記念して奈良まほろばソムリエの会は、42人の書き手による『お寺参りが楽しくなる 奈良百寺巡礼』(本体980円+税)を京阪奈情報教育出版から発刊した(京阪奈新書)。今月18日には県庁で記者発表も行った。
お寺は基本的には『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』(山と渓谷社刊)に掲載の寺院としたが、掲載されていない寺もある。その中から10ヵ寺を選び、以下に紹介する。

表紙イラストは、童話作家・画家のなかじまゆたかさんに描き下ろしていただいた
▽璉珹寺(れんじょうじ 奈良市西紀寺町)
7世紀後半、飛鳥に創建され、その後平城京に移転した紀寺(きでら)の後身とも。ご本尊は光明皇后がモデルともいわれる木造阿弥陀如来立像(県指定文化財)。白く美しい裸形像で、50年に一度、袴(はかま)が取り替えられる。
▽不空院(ふくういん奈良市高畑町)
新薬師寺の東にあり鑑真和上は一時ここに住んでいた。空海も滞在し、興福寺南円堂のもとになる八角円堂を建てたとも。寺の鎮守だった宇賀弁財天女(室町時代の秘仏)が福をもたらすことから「福院」とも呼ばれた。近年「かなで奉納」「地蔵盆夏祭り」などで親しまれる。
▽極楽寺(安堵町東安堵)
納骨堂の木造阿弥陀如来坐像は、もとは原爆ドーム横のお寺に安置されていたもの。それが巡り巡ってこの寺に安置された。毎年8月6日の原爆の日には、ここでも法要が営まれ、犠牲者を追悼し平和を願う。
▽補巌寺(ふがんじ 田原本町味間)
室町時代に能楽を大成した世阿弥が禅を学んだ。門前に「世阿弥参学之地」の碑が立つ。
▽平等寺(桜井市三輪) 大神神社の神宮寺として栄えたが明治初年の廃仏毀釈で廃寺に。昭和52年、住職の托鉢行脚(たくはつあんぎゃ)により再興。関ヶ原の戦いに敗れた島津軍の14人を70日間かくまったことから、今も島津家との縁が続く。
▽音羽山観音寺(桜井市南音羽)
NHK「やまと尼寺 精進日記」に登場。約1kmの参道は、ある崇敬者が父親の満願成就に感謝し、平成3年から20年以上かけて木の根や岩を取り除いて道幅を広げ、石垣を築いて整備。
▽威徳院(明日香村尾曽[おおそ])
本尊の秘仏・毘沙門天像は毎年4月の第2日曜日に開帳。境内の高台には、四国をかたどった「四国八十八ヶ所霊場お砂ふみ道場」がある。
▽阿日寺(香芝市良福寺)
恵心僧都源信の誕生寺とされ「ぽっくり往生の寺」として知られる。源信は15歳のとき宮中で経典の講義をし、いただいた褒美を母親に送る。しかし母からは「仏法を自分の世渡りの道具としてはいけない」と戒められ、のち源信は念仏三昧の道を選んだ。
▽転法輪寺(御所市高天)
金剛山山頂付近に建つ。明治初年の神仏分離令・修験道廃止令で廃れるが昭和25年の役行者一千二百五十年遠忌を機に再興。
▽生蓮寺(しょうれんじ 五條市二見)
平安初期、嵯峨天皇の皇后が安産祈願のため地蔵菩薩を安置したことに始まるという。空海が高野山開創のとき立ち寄り小地蔵を刻み本尊胎内に安置したとも。境内では約120種類の蓮が育つ。
皆さん、これまで本欄37回(3年と1ヵ月)のご愛読、ありがとうございました!