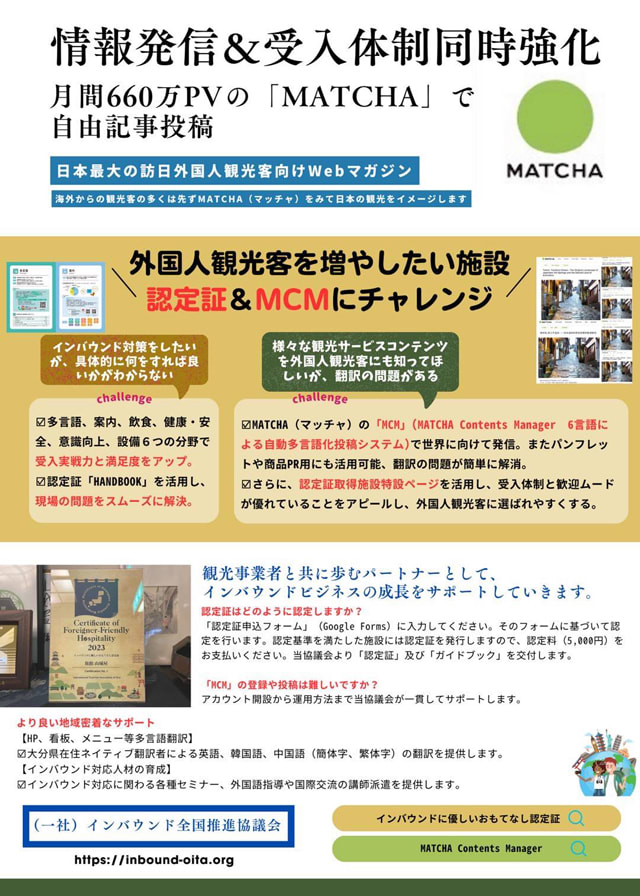奈良の観光について、〈「安い・浅い・狭い」脱却を 県観光戦略会議 初会合〉(毎日新聞奈良版 2024.5.16 付)という記事が各紙に出ていた。「安、近、短」は聞いたことがあるが、46年も奈良県に住んでいて、「安い、浅い、狭い」と聞いたのは初めてだ。
※トップ写真は、興福寺境内の桜(2024.3.31 撮影)
「どうもしっくり来ないな」と思っていると、「TBS NEWS DIG」というサイトに、〈『奈良の観光は、安い・浅い・狭い』マイナス面を三拍子で…こんな結論は誰が作った?奈良県観光戦略本部に聞くと〉という記事が出ていた(5/18付)。全文を引用すると、
以前から、“宿泊客が少ない”などの課題が挙げられている奈良県は、観光戦略本部を立ち上げて、15日に初会合を行った。そこで委員らに示された資料には、奈良観光のマイナス面をはっきり示す衝撃的なキーワードが並んでいる。結論『現在の奈良の観光は 安い 浅い 狭い』これはどういうことで、誰が作成したのか。資料を読みとき、県の担当者に話を聞いた。
◆安い=観光消費額が少ない
奈良県を訪れる観光客は、一定数いる。コロナ前の2019年は全国19位(4500万人)、インバウンド客に至っては2位大阪、4位京都に続く全国トップクラスの5位(350万人)。それにもかかわらず、1人あたりの観光消費額5308円は、全国平均の9931円に大きな開きがある。
日帰り客の消費額、6年間平均を見ると、飲食費は1344円。土産代は1156円。入場料は369円。飲食費はランチ代+飲み物程度か。こうしたデータから圧倒的に「奈良観光は安い」ことがわかる。入場料の平均369円といったところから、県は体験やアクティビティなどの消費額はほとんどない、と分析している。
◆浅い=滞在時間が短い
奈良県で宿泊する客は非常に少ない、これは昔から課題に挙げられている。過去9年はほぼ46位、最高は44位で、最低は47位だ。外国人訪問者数が全国5位に達した2019年も、外国人宿泊者となると全国24位に沈んでいる。奈良を訪れた観光客の94%は日帰りを選ぶ。宿泊者の割合は6%、これは和歌山県の半分の値だという。
◆狭い=奈良公園周辺ばかり
人流は、年間通じて奈良公園エリアに集中。桜シーズンの吉野には人流のピークがあるものの、飛鳥、橿原、平城宮跡などほかの地域にピークはほぼない。
インバウンド客に限ると、なんと85%が奈良公園周辺だ。県は誘客イベントをするにしても、奈良公園周辺以外には、飲食店や宿泊先の受け皿環境がないとした。また、観光客が来訪するのを待つ「大仏商法」の側面が否定できないとした。
◆結論を三拍子にしたのは奈良県自身だった
こうしたデータを基に、「現在の奈良の観光は 安い 浅い 狭い」の三拍子で結論づけられた。これを作ったのは、奈良県自身だった。県の担当者によると、原案は観光戦略課が作成し、その後上司に上がるなど、県として資料をまとめ上げていく中で、結論部分は『端的にまとまった、わかりやすい言葉が必要』という意見が出たという。
その結果、奈良県自らが『安い、浅い、狭い』の三拍子を打ちだした。『浅い』は『滞在時間が短く、深い魅力を知ってもらえていない』の意。ある意味自虐的にも聞こえるが、その心は、課題を明らかにしてテコ入れし、変えていこうとする姿勢のあらわれだという。
山下真知事「素材は良い、ポテンシャルはある」
初会合を終えた山下真知事は、奈良県について「素材は良い、ポテンシャルはある」と話した。観光戦略本部は、2030年度の数値目標を、宿泊者数500万人(273万人)、一人当たり観光消費額は6000円(4569円)などと定めて、これまでのように県全体を対象にしたプランニングではなく、各地の状況にあわせて、小さいところからはじめるという。
奈良の観光は「高い、深い、広い」に変わることはできるだろうか。戦略本部は、各地で観光地としての「磨き上げ」などが必要だとしている。
なーんだ。観光消費額が少ない、滞在時間が短い、奈良公園周辺に集中、ということなら「少額、短時間、集中」とすれば良かったのではないか。もっと短くするなら「少、短、狭」か。これは要するに、以前から言われている1つの事象(観光客が奈良公園周辺に集中する)を3つにバラして言っているだけなのだ。
「大仏商法」を悪口のように使っているのも、気になる。これはもともと「東大寺の大仏という優れたコンテンツを持つ奈良には、自然と多くの参拝客・観光客が集まる」という羨望の言葉だった。
それが次第に「大仏があることにあぐらをかいて、観光振興の努力を怠った」という悪い意味に使われるようになった。そもそも他府県民は「大仏商法」という言葉をよく知らないから、この悪い意味での「大仏商法」は、県民の自虐の言葉だろう。
「少額、短時間、集中」なら、ずいぶん以前から続いてきた現象である。これにどのようなメスが入るのか、県観光戦略会議の今後の動向に、大いに期待している。
※トップ写真は、興福寺境内の桜(2024.3.31 撮影)
「どうもしっくり来ないな」と思っていると、「TBS NEWS DIG」というサイトに、〈『奈良の観光は、安い・浅い・狭い』マイナス面を三拍子で…こんな結論は誰が作った?奈良県観光戦略本部に聞くと〉という記事が出ていた(5/18付)。全文を引用すると、
以前から、“宿泊客が少ない”などの課題が挙げられている奈良県は、観光戦略本部を立ち上げて、15日に初会合を行った。そこで委員らに示された資料には、奈良観光のマイナス面をはっきり示す衝撃的なキーワードが並んでいる。結論『現在の奈良の観光は 安い 浅い 狭い』これはどういうことで、誰が作成したのか。資料を読みとき、県の担当者に話を聞いた。
◆安い=観光消費額が少ない
奈良県を訪れる観光客は、一定数いる。コロナ前の2019年は全国19位(4500万人)、インバウンド客に至っては2位大阪、4位京都に続く全国トップクラスの5位(350万人)。それにもかかわらず、1人あたりの観光消費額5308円は、全国平均の9931円に大きな開きがある。
日帰り客の消費額、6年間平均を見ると、飲食費は1344円。土産代は1156円。入場料は369円。飲食費はランチ代+飲み物程度か。こうしたデータから圧倒的に「奈良観光は安い」ことがわかる。入場料の平均369円といったところから、県は体験やアクティビティなどの消費額はほとんどない、と分析している。
◆浅い=滞在時間が短い
奈良県で宿泊する客は非常に少ない、これは昔から課題に挙げられている。過去9年はほぼ46位、最高は44位で、最低は47位だ。外国人訪問者数が全国5位に達した2019年も、外国人宿泊者となると全国24位に沈んでいる。奈良を訪れた観光客の94%は日帰りを選ぶ。宿泊者の割合は6%、これは和歌山県の半分の値だという。
◆狭い=奈良公園周辺ばかり
人流は、年間通じて奈良公園エリアに集中。桜シーズンの吉野には人流のピークがあるものの、飛鳥、橿原、平城宮跡などほかの地域にピークはほぼない。
インバウンド客に限ると、なんと85%が奈良公園周辺だ。県は誘客イベントをするにしても、奈良公園周辺以外には、飲食店や宿泊先の受け皿環境がないとした。また、観光客が来訪するのを待つ「大仏商法」の側面が否定できないとした。
◆結論を三拍子にしたのは奈良県自身だった
こうしたデータを基に、「現在の奈良の観光は 安い 浅い 狭い」の三拍子で結論づけられた。これを作ったのは、奈良県自身だった。県の担当者によると、原案は観光戦略課が作成し、その後上司に上がるなど、県として資料をまとめ上げていく中で、結論部分は『端的にまとまった、わかりやすい言葉が必要』という意見が出たという。
その結果、奈良県自らが『安い、浅い、狭い』の三拍子を打ちだした。『浅い』は『滞在時間が短く、深い魅力を知ってもらえていない』の意。ある意味自虐的にも聞こえるが、その心は、課題を明らかにしてテコ入れし、変えていこうとする姿勢のあらわれだという。
山下真知事「素材は良い、ポテンシャルはある」
初会合を終えた山下真知事は、奈良県について「素材は良い、ポテンシャルはある」と話した。観光戦略本部は、2030年度の数値目標を、宿泊者数500万人(273万人)、一人当たり観光消費額は6000円(4569円)などと定めて、これまでのように県全体を対象にしたプランニングではなく、各地の状況にあわせて、小さいところからはじめるという。
奈良の観光は「高い、深い、広い」に変わることはできるだろうか。戦略本部は、各地で観光地としての「磨き上げ」などが必要だとしている。
なーんだ。観光消費額が少ない、滞在時間が短い、奈良公園周辺に集中、ということなら「少額、短時間、集中」とすれば良かったのではないか。もっと短くするなら「少、短、狭」か。これは要するに、以前から言われている1つの事象(観光客が奈良公園周辺に集中する)を3つにバラして言っているだけなのだ。
「大仏商法」を悪口のように使っているのも、気になる。これはもともと「東大寺の大仏という優れたコンテンツを持つ奈良には、自然と多くの参拝客・観光客が集まる」という羨望の言葉だった。
それが次第に「大仏があることにあぐらをかいて、観光振興の努力を怠った」という悪い意味に使われるようになった。そもそも他府県民は「大仏商法」という言葉をよく知らないから、この悪い意味での「大仏商法」は、県民の自虐の言葉だろう。
「少額、短時間、集中」なら、ずいぶん以前から続いてきた現象である。これにどのようなメスが入るのか、県観光戦略会議の今後の動向に、大いに期待している。