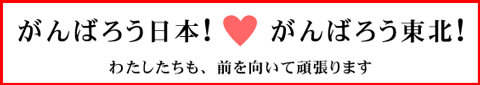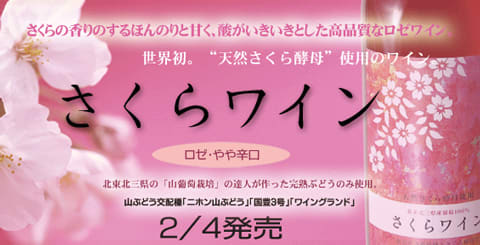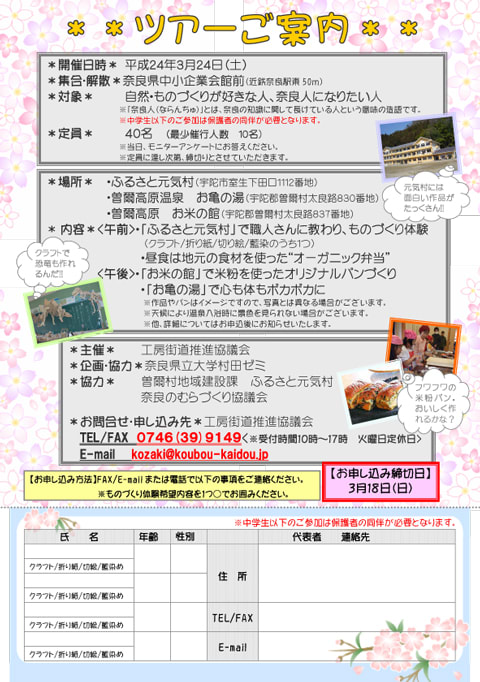2/28(火)奈良市観光戦略課が、「一目惚れ」する素晴らしい企画を発表した。多賀城市(宮城県)の「ひとめぼれ」を使った「多賀城市復興支援酒」が発売されるのである。お酒の名前は“みちのく多賀城「遠の朝廷(とおのみかど)」大和のかほり”。陸奥の国の多賀城政庁(律令時代の国府・鎮守府)は、かつて「遠の朝廷」と呼ばれたことにちなむ。なお多賀城市は奈良市の姉妹都市である。今朝(2/29)の産経新聞奈良版には「復興支援酒が完成 宮城産米使用 奈良の醸造元など協力」、奈良新聞には「多賀城市復興を支援 売上げの10%寄付」と出ている。
報道資料によると《奈良市と東大寺が「日本清酒発祥の地・奈良」で多賀城市の今年収穫した米(ひとめぼれ)を使い、奈良市の醸造元で復興支援の新酒を造る提案をし、多賀城市の協力も得て、前向きに検討を重ねてまいりました。このたび、奈良市の醸造元3社が協力してくださり、新酒が出来上がりましたので、3月1日より発売を開始します。新酒の名称は、友好都市を結んでいる多賀城市と奈良市の歴史を反映して、みちのく多賀城「遠の朝廷(みかど)」大和のかほりで決定させていただきました。ネーミングは東大寺別当(北河原公敬師)の書にてラベルとし、その売上金の一部を義援金として、多賀城市に送ります》。
醸造元は、
○(株)今西清兵衛商店 (奈良市福智院町24-1)
○奈良豊澤酒造(株) (奈良市今市町405)
○八木酒造(株) (奈良市高畑町915)
の3社である。販売開始は3月1日から(奈良豊澤酒造のみ3月5日から)。
販売店は、各醸造元のほか
○東大寺ミュージアムショップ(東大寺ミュージアム内)
○近鉄百貨店の9店舗(阿倍野店・上本町店・奈良店・橿原店・生駒店・桃山店・和歌山店・四日市店・草津店)
など。精米歩合70%の純米酒で、価格は1,575円(720ml)である。
産経新聞には《復興支援酒は東大寺境内で披露され、奈良市の仲川げん市長は「一人でも多くの人がこの酒を通じ、復興支援の輪に加わってもらいたい」、北河原別当は「多くの人に酒を買っていただき、支援につなげることができれば。今後も被災地のために努力していきたい」と話した。多賀城市の菊地健次郎市長は「(取り組みを)継続することができれば、さらに友好が深まる」と期待を込めた》というコメントが紹介されていた。
以前、当ブログに「Buy 東北!」という記事を書いたことがある。東北の物産を買って支援しようという「応援買い」のことであるが、今回の企画は、原料米を東北から仕入れ、それを奈良で醸造し東北のブランドを付して販売する、という凝った仕組みで、いわば「地産他消」、米どころと酒どころのコラボレーション企画なのである。
奈良が清酒発祥の地であることは、驚くほど知られていない。今回の「遠の朝廷」の登場で、それが広く知られることになれば、これも有り難いことである。皆さん、「遠の朝廷」を飲んで、多賀城市を支援しましょう!
報道資料によると《奈良市と東大寺が「日本清酒発祥の地・奈良」で多賀城市の今年収穫した米(ひとめぼれ)を使い、奈良市の醸造元で復興支援の新酒を造る提案をし、多賀城市の協力も得て、前向きに検討を重ねてまいりました。このたび、奈良市の醸造元3社が協力してくださり、新酒が出来上がりましたので、3月1日より発売を開始します。新酒の名称は、友好都市を結んでいる多賀城市と奈良市の歴史を反映して、みちのく多賀城「遠の朝廷(みかど)」大和のかほりで決定させていただきました。ネーミングは東大寺別当(北河原公敬師)の書にてラベルとし、その売上金の一部を義援金として、多賀城市に送ります》。
醸造元は、
○(株)今西清兵衛商店 (奈良市福智院町24-1)
○奈良豊澤酒造(株) (奈良市今市町405)
○八木酒造(株) (奈良市高畑町915)
の3社である。販売開始は3月1日から(奈良豊澤酒造のみ3月5日から)。
販売店は、各醸造元のほか
○東大寺ミュージアムショップ(東大寺ミュージアム内)
○近鉄百貨店の9店舗(阿倍野店・上本町店・奈良店・橿原店・生駒店・桃山店・和歌山店・四日市店・草津店)
など。精米歩合70%の純米酒で、価格は1,575円(720ml)である。
産経新聞には《復興支援酒は東大寺境内で披露され、奈良市の仲川げん市長は「一人でも多くの人がこの酒を通じ、復興支援の輪に加わってもらいたい」、北河原別当は「多くの人に酒を買っていただき、支援につなげることができれば。今後も被災地のために努力していきたい」と話した。多賀城市の菊地健次郎市長は「(取り組みを)継続することができれば、さらに友好が深まる」と期待を込めた》というコメントが紹介されていた。
以前、当ブログに「Buy 東北!」という記事を書いたことがある。東北の物産を買って支援しようという「応援買い」のことであるが、今回の企画は、原料米を東北から仕入れ、それを奈良で醸造し東北のブランドを付して販売する、という凝った仕組みで、いわば「地産他消」、米どころと酒どころのコラボレーション企画なのである。
奈良が清酒発祥の地であることは、驚くほど知られていない。今回の「遠の朝廷」の登場で、それが広く知られることになれば、これも有り難いことである。皆さん、「遠の朝廷」を飲んで、多賀城市を支援しましょう!