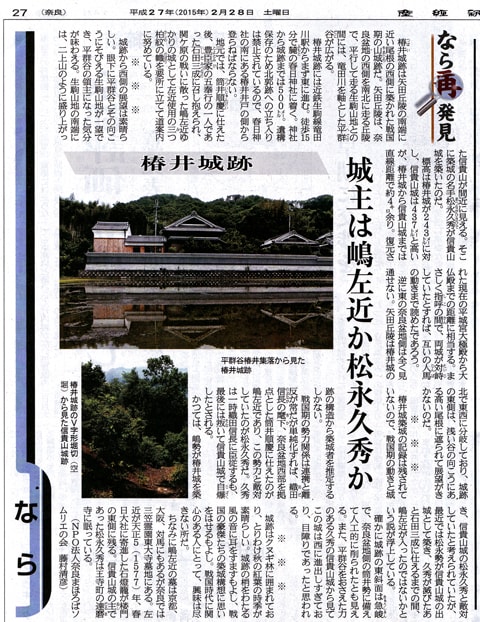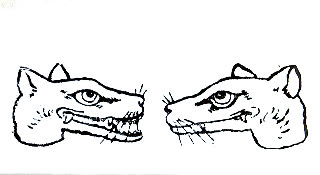産経新聞奈良版・三重版ほかに好評連載され、本年3月末で連載終了となった「なら再発見」、当ブログで未紹介だったものを順次紹介している。今回(3/7に掲載)紹介するのは「桂昌院 奈良の文化財修復に尽力」、執筆されたのはNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」で広報グループに所属する辰馬真知子さんだ、辰馬さんは初回から連載終了まで、一貫して記事のチェック役をご担当いただいた。
※トップ写真は春日大社の桂昌殿(桂昌院が寄進した)。この写真は春日大社のHPから拝借。他の2点は記事から拝借した
桂昌院の通称は「お玉の方」で、それが「玉の輿」の語源だとする説がある。彼女については毀誉褒貶が激しい。桂昌院がいなければ5代将軍綱吉は生まれず、「生類憐みの令」という最悪の法令が発せられることもなかった。隆光僧正(奈良市出身)を寵愛したため、奈良や京都の寺社の建立や修繕などで、幕府財政は悪化した。しかし数々のおかげで多くの社寺が救われた。桂昌院に(女性として最高位の)従一位を与えるため、宮中からの使者を招くこともなかったので、松の廊下での刃傷沙汰も起こらなかった。つまり「忠臣蔵」は生まれなかった 等々。前置きはこれくらいにして、記事全文を紹介する。

奈良の古寺をめぐっていると、必ず耳にする女性の名前がある。桂昌院(けいしょういん)(1627~1705年)だ。徳川幕府第5代将軍綱吉(つなよし)の生母で、お玉の方と呼ばれ、綱吉が将軍職に就くや大奥で権勢をふるった。
元禄時代を描いた小説や時代劇では好ましからざる人物として描かれることが多い。だが奈良、ひいては日本の文化財にとっては大恩人なのだ。
※ ※ ※
奈良に来た観光客がまず訪れるのが東大寺。大仏様のいらっしゃる大仏殿は、奈良時代の創建のものから数えて3代目にあたる。16世紀半ばの戦乱の時代に内乱によって焼失したあと、100年あまりも再建されず、公慶(こうけい)上人が費用の調達に苦心しながら完成させた。この資金調達に貢献したのが桂昌院だ。
春日大社には寄進された建物、桂昌殿が残る。春日の神に宝物を奉納し、本社中門近くには徳川家の「葵紋」と彼女の実家である本庄(ほんじょう)家の「九目結(ここのつめゆい)紋」をつけた燈籠がある。
世界最古の木造建築と仏像群が私達を古の時代へと誘う法隆寺。元禄時代の大修理は、桂昌院の支援のもと行われた。境内では綱吉の武運長久を願って奉納された燈籠や、軒丸瓦に徳川家と本庄家の家紋がある。
唐招提寺で僧に受戒をする戒壇(かいだん)堂の再建やその堂宇の修繕にも、多額の寄進をした。戒壇堂は焼失し、今では石壇が残るのみとなっているが、その門と鬼瓦にある両家の家紋が歴史を物語る。

春日大社に桂昌院が奉納した燈籠
長谷寺・室生寺への深い帰依(きえ)、信貴山朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)・新薬師寺・東明寺(とうみょうじ)(大和郡山市矢田)の整備―など、桂昌院が奈良に残した足跡は枚挙にいとまがない。
※ ※ ※
桂昌院の生まれは京都。将軍側室の侍女として江戸城に入り、自らも3代将軍家光の側室となって綱吉を産んだ。信仰心が篤く、祈祷(きとう)を行う護持僧(ごじそう)として仕えていた隆光(りゅうこう)に深く帰依し、綱吉に世継ぎとなる男子を授かるために仏教の功徳を積もうとした。すべての生き物の殺生を禁じた『生類憐(しょうるいあわれ)みの令』は、彼女が綱吉に勧めたといわれる。

徳川家と本城家の家紋が彫られた唐招提寺戒壇南門の彫刻
そして、日本各地の神社仏閣の復興に力を尽くすようになった。特に、隆光が奈良の出身だった縁で、多くの奈良の寺社の整備を金銭面で支えた。しかし、その額は国家予算の3分の1にも上ると推算されるほどで、『生類憐みの令』で社会を混乱させたこととともに、「幕府の財政をも傾けた悪女」とみなされることが多い。
すべてがわが子綱吉の世の泰平を願ってのことであったが、結果的には貴重な文化財を現在にまで伝えることに貢献することとなった。桂昌院の援助がなければ、今私たちが目にし、鑑賞することができる多くの文化財は違った形、もしくは伝承だけが残されていたかもしれない。
江戸の人々が感じ、作り上げた桂昌院像、それはひとつの事実であろう。しかし奈良の古社寺を逍遥(しょうよう)し、私たちの眼前にある建物、仏像に彼女の祈りを見るとき、また別の桂昌院像が浮かび上がる。
そして、古代より時代ごとに修復を繰り返し、かけがえのない文化財を現代に伝えるバトンを渡し続けてくれた先人たちに、心から感謝の意を表したい。(NPO法人奈良まほろばソムリエの会 辰馬真知子)
さすがに辰馬さんは女性らしく、すっきりとまとめられている。桂昌院は幕府財政を傾けたとはいえ、貴重な文化財を残してくれたことは間違いない。県下の社寺をお参りするときは、桂昌院の功績にも目を向けよう。辰馬さん、有難うございました。そしてこれまで115回もの原稿チェックに、厚く御礼申し上げます!

※トップ写真は春日大社の桂昌殿(桂昌院が寄進した)。この写真は春日大社のHPから拝借。他の2点は記事から拝借した
桂昌院の通称は「お玉の方」で、それが「玉の輿」の語源だとする説がある。彼女については毀誉褒貶が激しい。桂昌院がいなければ5代将軍綱吉は生まれず、「生類憐みの令」という最悪の法令が発せられることもなかった。隆光僧正(奈良市出身)を寵愛したため、奈良や京都の寺社の建立や修繕などで、幕府財政は悪化した。しかし数々のおかげで多くの社寺が救われた。桂昌院に(女性として最高位の)従一位を与えるため、宮中からの使者を招くこともなかったので、松の廊下での刃傷沙汰も起こらなかった。つまり「忠臣蔵」は生まれなかった 等々。前置きはこれくらいにして、記事全文を紹介する。

奈良の古寺をめぐっていると、必ず耳にする女性の名前がある。桂昌院(けいしょういん)(1627~1705年)だ。徳川幕府第5代将軍綱吉(つなよし)の生母で、お玉の方と呼ばれ、綱吉が将軍職に就くや大奥で権勢をふるった。
元禄時代を描いた小説や時代劇では好ましからざる人物として描かれることが多い。だが奈良、ひいては日本の文化財にとっては大恩人なのだ。
※ ※ ※
奈良に来た観光客がまず訪れるのが東大寺。大仏様のいらっしゃる大仏殿は、奈良時代の創建のものから数えて3代目にあたる。16世紀半ばの戦乱の時代に内乱によって焼失したあと、100年あまりも再建されず、公慶(こうけい)上人が費用の調達に苦心しながら完成させた。この資金調達に貢献したのが桂昌院だ。
春日大社には寄進された建物、桂昌殿が残る。春日の神に宝物を奉納し、本社中門近くには徳川家の「葵紋」と彼女の実家である本庄(ほんじょう)家の「九目結(ここのつめゆい)紋」をつけた燈籠がある。
世界最古の木造建築と仏像群が私達を古の時代へと誘う法隆寺。元禄時代の大修理は、桂昌院の支援のもと行われた。境内では綱吉の武運長久を願って奉納された燈籠や、軒丸瓦に徳川家と本庄家の家紋がある。
唐招提寺で僧に受戒をする戒壇(かいだん)堂の再建やその堂宇の修繕にも、多額の寄進をした。戒壇堂は焼失し、今では石壇が残るのみとなっているが、その門と鬼瓦にある両家の家紋が歴史を物語る。

春日大社に桂昌院が奉納した燈籠
長谷寺・室生寺への深い帰依(きえ)、信貴山朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)・新薬師寺・東明寺(とうみょうじ)(大和郡山市矢田)の整備―など、桂昌院が奈良に残した足跡は枚挙にいとまがない。
※ ※ ※
桂昌院の生まれは京都。将軍側室の侍女として江戸城に入り、自らも3代将軍家光の側室となって綱吉を産んだ。信仰心が篤く、祈祷(きとう)を行う護持僧(ごじそう)として仕えていた隆光(りゅうこう)に深く帰依し、綱吉に世継ぎとなる男子を授かるために仏教の功徳を積もうとした。すべての生き物の殺生を禁じた『生類憐(しょうるいあわれ)みの令』は、彼女が綱吉に勧めたといわれる。

徳川家と本城家の家紋が彫られた唐招提寺戒壇南門の彫刻
そして、日本各地の神社仏閣の復興に力を尽くすようになった。特に、隆光が奈良の出身だった縁で、多くの奈良の寺社の整備を金銭面で支えた。しかし、その額は国家予算の3分の1にも上ると推算されるほどで、『生類憐みの令』で社会を混乱させたこととともに、「幕府の財政をも傾けた悪女」とみなされることが多い。
すべてがわが子綱吉の世の泰平を願ってのことであったが、結果的には貴重な文化財を現在にまで伝えることに貢献することとなった。桂昌院の援助がなければ、今私たちが目にし、鑑賞することができる多くの文化財は違った形、もしくは伝承だけが残されていたかもしれない。
江戸の人々が感じ、作り上げた桂昌院像、それはひとつの事実であろう。しかし奈良の古社寺を逍遥(しょうよう)し、私たちの眼前にある建物、仏像に彼女の祈りを見るとき、また別の桂昌院像が浮かび上がる。
そして、古代より時代ごとに修復を繰り返し、かけがえのない文化財を現代に伝えるバトンを渡し続けてくれた先人たちに、心から感謝の意を表したい。(NPO法人奈良まほろばソムリエの会 辰馬真知子)
さすがに辰馬さんは女性らしく、すっきりとまとめられている。桂昌院は幕府財政を傾けたとはいえ、貴重な文化財を残してくれたことは間違いない。県下の社寺をお参りするときは、桂昌院の功績にも目を向けよう。辰馬さん、有難うございました。そしてこれまで115回もの原稿チェックに、厚く御礼申し上げます!