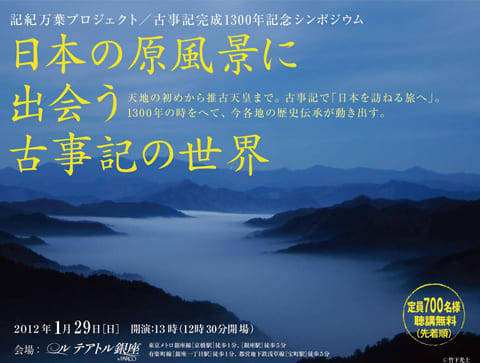朝日新聞奈良版の人気コーナー「人生あおによし」に、1/29(日)から、「清澄の里 粟」の三浦雅之さんが登場している。全27回の連載である。雅之さんはFacebookに「拙い文章で恐縮ですが、こうして半生記をまとめる機会も多くはないと思いますので、素直な内容を心掛けて締め切りと格闘していきたいと思ってます」とコメントされていた。
連載の1回目に、三浦雅之さんのプロフィールが出ている。《みうら・まさゆき 1970年、京都府舞鶴市生まれ。福祉関係の研究職を経て三重・奈良県境の「赤目自然農塾」で学び、98年、妻の陽子さんと奈良市高樋町に移住。県内の伝統野菜の調査研究や栽培保存に取り組んできた。2002年にオープンした農家レストラン「清澄の里 粟」は昨年、世界的なグルメ本「ミシュランガイド」で一つ星を獲得した》。

初回のイントロは、17年前の話である。《人生の転機は17年前。新婚旅行先のアメリカで、見聞を広めようと訪ねた、あるネーティブアメリカンの村で目にした光景だった。村の知恵袋として尊敬を集め、生涯現役で働くお年寄り。笑顔で遊び回る子どもたち。村人の生き生きとした暮らしは、協働で耕した畑の収穫物を食し、種を採り、また育てる繰り返しがつくり出す食文化の伝承で成り立っていた。彼らの伝統作物であるトウモロコシの色鮮やかな種と伝統文化を中心に、各世代が結びつき、人々は幸せそうに生きていた》。ネーティブアメリカンとは、アメリカ先住民(インディアン)のことである。
《それは当時、総合病院で看護師をしていた妻の陽子と福祉関係の研究機関で働いていた私にとって、目からうろこが落ちるような光景だった。日本では、「要介護者」となった高齢者の生きがいの喪失や学校でのいじめが、当たり前のようになっていた。豊かになった日本が知らず知らずのうちに置き忘れた大切なもの。制度、テクノロジー、施設と同じぐらい、いやそれよりも大切なことがあるのではないか―。そんなことを考えながら、日本に戻った》。

これが三浦さんご夫妻の原点なのである。13年前、清澄の里(きよすみのさと 奈良市高樋町)の荒地を開墾し、伝統野菜の種を蒔いた。3年後(今から10年前)には立派な畑に生まれ変わり、そこに農家レストラン「清澄の里 粟」を開店。3年前には姉妹店「粟 ならまち店」もオープンされた。当ブログご愛読者のazukiさんは、「清澄の里 粟」をきれいなお写真入りでレポートされている。
初回のしめくくりに三浦さんは書いている。《日本人として生まれ、奈良にご縁をいただいたことを幸せに感じる。日本の農村文化を体現してこられた方々に教わった大切なこと。大和の伝統野菜を受け継いでこられた先人から受け取った物語。大和の伝統野菜の小さな種は古の大和を、日本の文化を訪ねる入口となる。その種火を、しっかりと守り育てていきたいと思っている》。
第2回(1/30付)では、「あたたかい故郷の記憶」として、故郷・舞鶴市(京都府)での幼少時代の思い出話を紹介されていた。思うに、雅之さんのご成功の陰には、奥さんの絶大なご尽力があったようだが、それは今まであまりメディアでは紹介されていない。今回の連載では、その辺りを詳しく知ることができるだろうと期待している。雅之さん、これからの展開を大いに注目していますよ!
連載の1回目に、三浦雅之さんのプロフィールが出ている。《みうら・まさゆき 1970年、京都府舞鶴市生まれ。福祉関係の研究職を経て三重・奈良県境の「赤目自然農塾」で学び、98年、妻の陽子さんと奈良市高樋町に移住。県内の伝統野菜の調査研究や栽培保存に取り組んできた。2002年にオープンした農家レストラン「清澄の里 粟」は昨年、世界的なグルメ本「ミシュランガイド」で一つ星を獲得した》。

写真は田の神さま。「清澄の里 粟」で06.6.11に撮影(下の写真も)
初回のイントロは、17年前の話である。《人生の転機は17年前。新婚旅行先のアメリカで、見聞を広めようと訪ねた、あるネーティブアメリカンの村で目にした光景だった。村の知恵袋として尊敬を集め、生涯現役で働くお年寄り。笑顔で遊び回る子どもたち。村人の生き生きとした暮らしは、協働で耕した畑の収穫物を食し、種を採り、また育てる繰り返しがつくり出す食文化の伝承で成り立っていた。彼らの伝統作物であるトウモロコシの色鮮やかな種と伝統文化を中心に、各世代が結びつき、人々は幸せそうに生きていた》。ネーティブアメリカンとは、アメリカ先住民(インディアン)のことである。
《それは当時、総合病院で看護師をしていた妻の陽子と福祉関係の研究機関で働いていた私にとって、目からうろこが落ちるような光景だった。日本では、「要介護者」となった高齢者の生きがいの喪失や学校でのいじめが、当たり前のようになっていた。豊かになった日本が知らず知らずのうちに置き忘れた大切なもの。制度、テクノロジー、施設と同じぐらい、いやそれよりも大切なことがあるのではないか―。そんなことを考えながら、日本に戻った》。

これが三浦さんご夫妻の原点なのである。13年前、清澄の里(きよすみのさと 奈良市高樋町)の荒地を開墾し、伝統野菜の種を蒔いた。3年後(今から10年前)には立派な畑に生まれ変わり、そこに農家レストラン「清澄の里 粟」を開店。3年前には姉妹店「粟 ならまち店」もオープンされた。当ブログご愛読者のazukiさんは、「清澄の里 粟」をきれいなお写真入りでレポートされている。
初回のしめくくりに三浦さんは書いている。《日本人として生まれ、奈良にご縁をいただいたことを幸せに感じる。日本の農村文化を体現してこられた方々に教わった大切なこと。大和の伝統野菜を受け継いでこられた先人から受け取った物語。大和の伝統野菜の小さな種は古の大和を、日本の文化を訪ねる入口となる。その種火を、しっかりと守り育てていきたいと思っている》。
第2回(1/30付)では、「あたたかい故郷の記憶」として、故郷・舞鶴市(京都府)での幼少時代の思い出話を紹介されていた。思うに、雅之さんのご成功の陰には、奥さんの絶大なご尽力があったようだが、それは今まであまりメディアでは紹介されていない。今回の連載では、その辺りを詳しく知ることができるだろうと期待している。雅之さん、これからの展開を大いに注目していますよ!