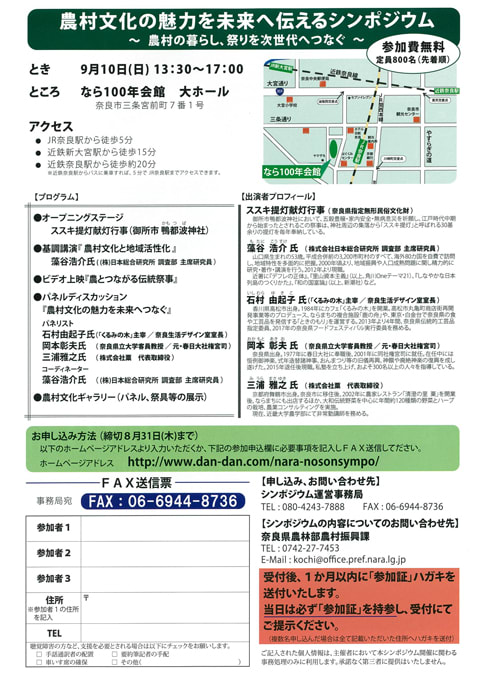毎月第3日曜日、60分で楽しく奈良を学ぶセミナー「奈良の歩き方講座」、9月17日(日)の演題は「奈良市の地名!知ったかぶり」、講師はNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」が誇る「ちょいワルおやじ」吉川和美さん。開催場所は奈良市観光センター(三条通とやすらぎの道の交差点角)「NARANICLE」1階の体験学習室。受講料は500円で、申し込みが必要だ。定員は20名なので、ぜひお早めにお申し込みを!吉川さんのFacebookには、
9月度の「奈良の歩き方講座」は、私が担当としてお話しさせて頂きます。題して[奈良市の地名!知ったかぶり]。拙い話ですが、奈良歩きに興味のあるみなさん、ご参加いただければ大変ありがたいです。
とずいぶん控えめに紹介されている。同講座のチラシには、

吉川和美さん。2016.9.11 クラブツーリズム奈良旅行センターで撮影
【 開催日時 】 9月17日(日)14:00 ~ 15:00
【 講 師 】 NPO法人 奈良まほろばソムリエの会 吉川和美 先生
【 演 題 】 「奈良市の地名!知ったかぶり」
【 料 金 】 おひとり様 500円(受講料+資料代として)
奈良の歴史通が集まるNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」会員の皆さんによるセミナーです。奈良市内の観光地を中心に、地名の由来・伝説を紹介していただきます。皆さんも「知ったかぶりの奈良通」になって、ぶらりと深い奈良歩きをしましょう!
ご予約は、メールまたはファックスで公益社団法人奈良市観光協会まで
E-mail :order@narashikanko.or.jp
FAX : 0742-22-5200 (℡ 0742-22-3900)
※当日 、会場受付も可能です。駐車場がございませんので、会場へは公共交通機関でお越しください。
★次回(10月)のご案内
【開催日時】10月15日(日)14:00~15:00
【講 師】NPO法人奈良まほろばソムリエの会 山本順三先生
【演 題】「世界遺産・春日大社の楽しみ方」
日本有数の燈籠を持ち、世界遺産「興福寺」「春日山原始林」とも関わり、数多い神事・行事があり、趣旨・観点によって様々に楽しめるのが春日大社です。そんな春日大社の魅力を、楽しく分かりやすくお話しします!
わずかワンコイン・500円で楽しく奈良が学べる講座である。館内のレストランでは、ランチも楽しめる。近鉄奈良駅から徒歩5分、JR奈良駅から徒歩10分。皆さん、ぜひ足をお運びください!

9月度の「奈良の歩き方講座」は、私が担当としてお話しさせて頂きます。題して[奈良市の地名!知ったかぶり]。拙い話ですが、奈良歩きに興味のあるみなさん、ご参加いただければ大変ありがたいです。
とずいぶん控えめに紹介されている。同講座のチラシには、

吉川和美さん。2016.9.11 クラブツーリズム奈良旅行センターで撮影
【 開催日時 】 9月17日(日)14:00 ~ 15:00
【 講 師 】 NPO法人 奈良まほろばソムリエの会 吉川和美 先生
【 演 題 】 「奈良市の地名!知ったかぶり」
【 料 金 】 おひとり様 500円(受講料+資料代として)
奈良の歴史通が集まるNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」会員の皆さんによるセミナーです。奈良市内の観光地を中心に、地名の由来・伝説を紹介していただきます。皆さんも「知ったかぶりの奈良通」になって、ぶらりと深い奈良歩きをしましょう!
ご予約は、メールまたはファックスで公益社団法人奈良市観光協会まで
E-mail :order@narashikanko.or.jp
FAX : 0742-22-5200 (℡ 0742-22-3900)
※当日 、会場受付も可能です。駐車場がございませんので、会場へは公共交通機関でお越しください。
★次回(10月)のご案内
【開催日時】10月15日(日)14:00~15:00
【講 師】NPO法人奈良まほろばソムリエの会 山本順三先生
【演 題】「世界遺産・春日大社の楽しみ方」
日本有数の燈籠を持ち、世界遺産「興福寺」「春日山原始林」とも関わり、数多い神事・行事があり、趣旨・観点によって様々に楽しめるのが春日大社です。そんな春日大社の魅力を、楽しく分かりやすくお話しします!
わずかワンコイン・500円で楽しく奈良が学べる講座である。館内のレストランでは、ランチも楽しめる。近鉄奈良駅から徒歩5分、JR奈良駅から徒歩10分。皆さん、ぜひ足をお運びください!