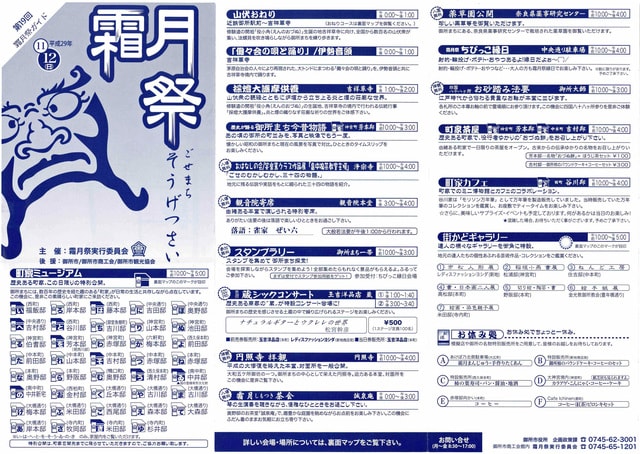NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」が毎週木曜日、毎日新聞奈良版に連載している「ディスカバー!奈良」、先週(10/26)掲載されたのは「大和武士(やまとさむらい)の十市(とおいちorとおち)氏 橿原市の十市城跡」、執筆されたのは広陵町出身・在住で、同会理事の大山恵功(よしのり)さんだ。
※トップ写真は「十市城之跡」石碑(橿原市十市町)
十市遠忠(とおただ)を代表格とする十市氏は、橿原市十市町(奈良県運転免許センターの北東側)に十市城を築き、その勢力を誇っていた。十市氏は、南北朝時代に興福寺大乗院方の国民(いわゆる大和武士)として歴史に登場する。山と渓谷社刊『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』によると、
南北朝の合体が実現すると、興福寺の一国支配が再現したが、動乱期以降在地の有力武士たちの領主化が進み、彼らは興福寺領を含む寺社領を侵食するとともに、党を形成し「私合戦」をくり返すようになった。北大和では筒井・古市・箸尾氏ら、中南和では越智(おち)・十市・楢原氏ら、宇陀では「宇陀三将」と呼ばれた秋山・沢・芳野(ほうの)氏が、それぞれ勢力を伸ばすようになった…。

十市御県坐神社(橿原市十市町)にある「十市遠忠歌碑」
大和武士の名残は、今も「春日若宮おん祭」でうかがい知ることができる。では、記事全文を引用する。
大和武士の十市氏 橿原市の十市城跡
戦国時代、十市(とおいち)城(橿原市)を居城として活躍した十市氏をご存じですか。奈良市周辺の古市氏、大和郡山市周辺の筒井氏、広陵町周辺の箸尾(はしお)氏、高取町周辺の越智(おち)氏と並ぶ大和武士の五強の一つと言われた武士集団です。
十市城は東西約550㍍、南北約430㍍の平城で、ポルトガル人宣教師フロイス(1532~97)の書いた歴史書『日本史』にも登場し、発掘調査では中国製の白磁碗、青磁碗などが出土しています。
十市遠忠(とおただ)(1497~1545)の時代に最盛期を迎え、壮大な山城龍王山(りゅうおうざん)城(天理市)を整備し、現在の橿原市や田原本町、天理市、桜井市の一部地域まで支配したとされています。
また、文武両道に優れ、和歌にも精通し、十市御県坐(とおいちのみあがたにいます)神社に彼の歌碑が建てられています。十市城跡を訪れ、十市氏が活躍していた時代に思いをはせるのはいかがですか。
メモ 十市城跡へは近鉄大和八木駅北口よりバス(耳成循環)で大門橋下車、北西へ徒歩約10分、または近鉄新ノ口駅から北東へ徒歩約20分。バスの本数が少ないのでご注意下さい(奈良まほろばソムリエの会理事 大山恵功)。
「御県坐(みあがたにいます)神社」とは、朝廷に献上するための野菜などを栽培する「神聖な菜園の霊」を神として祀る神社のことで、以前、県下の御県坐神社のすべてを巡拝するバスツアーを実施したこともある。そのとき十市御県坐神社も訪ねたが、「十市遠忠歌碑」には気がつかなかったので、もういちどお参りしたいと思う。
大山さん、貴重な情報をありがとうございました!
※トップ写真は「十市城之跡」石碑(橿原市十市町)
十市遠忠(とおただ)を代表格とする十市氏は、橿原市十市町(奈良県運転免許センターの北東側)に十市城を築き、その勢力を誇っていた。十市氏は、南北朝時代に興福寺大乗院方の国民(いわゆる大和武士)として歴史に登場する。山と渓谷社刊『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』によると、
南北朝の合体が実現すると、興福寺の一国支配が再現したが、動乱期以降在地の有力武士たちの領主化が進み、彼らは興福寺領を含む寺社領を侵食するとともに、党を形成し「私合戦」をくり返すようになった。北大和では筒井・古市・箸尾氏ら、中南和では越智(おち)・十市・楢原氏ら、宇陀では「宇陀三将」と呼ばれた秋山・沢・芳野(ほうの)氏が、それぞれ勢力を伸ばすようになった…。

十市御県坐神社(橿原市十市町)にある「十市遠忠歌碑」
大和武士の名残は、今も「春日若宮おん祭」でうかがい知ることができる。では、記事全文を引用する。
大和武士の十市氏 橿原市の十市城跡
戦国時代、十市(とおいち)城(橿原市)を居城として活躍した十市氏をご存じですか。奈良市周辺の古市氏、大和郡山市周辺の筒井氏、広陵町周辺の箸尾(はしお)氏、高取町周辺の越智(おち)氏と並ぶ大和武士の五強の一つと言われた武士集団です。
十市城は東西約550㍍、南北約430㍍の平城で、ポルトガル人宣教師フロイス(1532~97)の書いた歴史書『日本史』にも登場し、発掘調査では中国製の白磁碗、青磁碗などが出土しています。
十市遠忠(とおただ)(1497~1545)の時代に最盛期を迎え、壮大な山城龍王山(りゅうおうざん)城(天理市)を整備し、現在の橿原市や田原本町、天理市、桜井市の一部地域まで支配したとされています。
また、文武両道に優れ、和歌にも精通し、十市御県坐(とおいちのみあがたにいます)神社に彼の歌碑が建てられています。十市城跡を訪れ、十市氏が活躍していた時代に思いをはせるのはいかがですか。
メモ 十市城跡へは近鉄大和八木駅北口よりバス(耳成循環)で大門橋下車、北西へ徒歩約10分、または近鉄新ノ口駅から北東へ徒歩約20分。バスの本数が少ないのでご注意下さい(奈良まほろばソムリエの会理事 大山恵功)。
「御県坐(みあがたにいます)神社」とは、朝廷に献上するための野菜などを栽培する「神聖な菜園の霊」を神として祀る神社のことで、以前、県下の御県坐神社のすべてを巡拝するバスツアーを実施したこともある。そのとき十市御県坐神社も訪ねたが、「十市遠忠歌碑」には気がつかなかったので、もういちどお参りしたいと思う。
大山さん、貴重な情報をありがとうございました!