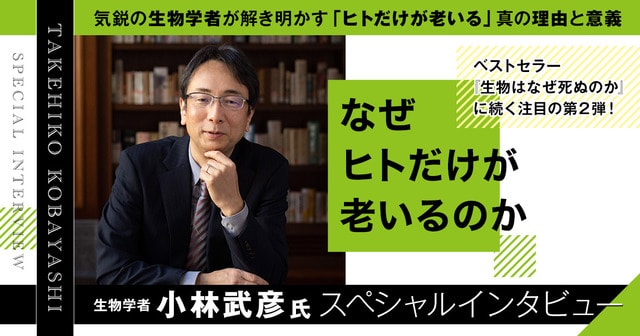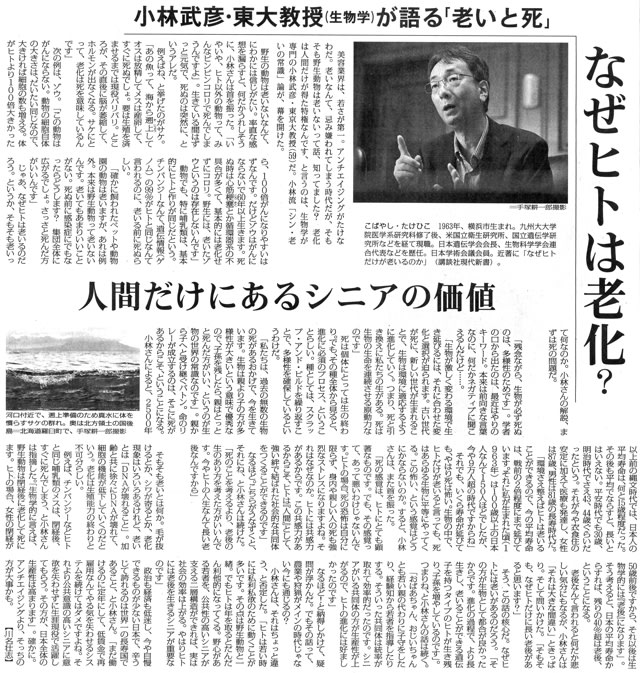今回の「田中利典師曰く」は、「今日は西行忌」(師のブログ 2013.3.27付)である。西行忌(旧暦2月16日)に際して、吉野山の桜を愛した西行法師を偲んで書かれた文章で、これまでにも何度かリメイクされている。師はその原文を、この日のブログに紹介された。では全文を以下に抜粋する。
※写真は、吉野山の桜(3/31撮影)。これはシロヤマザクラではなく、ソメイヨシノのようだ
今日は西行忌
今日は旧暦の2月16日西行忌である。例年より時期の遅い西行忌で、しかも春が早い。桜の開花も例年よりずいぶんと早い。そして今日は満月でもある。
「願わくば花の下にて春死なむ その如月(きさらぎ)の望月のころ」と西行が辞世の歌を詠んだのは有名な話だが、花と満月と西行忌が、今年は重なり合っている。その話は先日、「やまとびと」に書いた。ブログやFBでも紹介した。実は正直にいうと、あの原稿は今から25年前に書いたエッセイのリメイク版である。で、25年前の原文を紹介する。
*******************
「花」は神仏への供養を表す。あるいは、下界の浄土そのものを象徴する、という。今年も春が訪れ、吉野のお山にも花の開花が告げられた。いつもながらの観光客で山はにぎわうことだろう。
吉野の花は山桜である。そして山桜はご本尊金剛蔵王権現様のご神木である。春が来て、全山が桜色に染まる風景に接するたびに、ご本尊への供養の心を新たにさせていただいている。この桜花は、金峯山浄土そのものを荘厳しているにちがいない。吉野の里人ならずとも、この有り難さはわかることであろう。
「願わくば花の下にて春死なむ その如月の望月のころ」と詠んだのは西行法師であった。吉野の桜を愛し、吉野に住した西行は、釈尊入滅の2月15日、満月の頃に、桜の花の咲く下に生涯を終えたいと念願して、この歌を詠んだという。そして西行はその願いどおり、2月16日に死をむかえたのであった。今から800年ほどの昔のことである。
今の吉野山では、西行のいう如月望月に花が咲くことは極めて希(まれ)である。が、その希なことが今年になって起きた。今年は春分の日の翌日に当たったが、この日、吉野山には満開を迎えた桜花が何本かあったのである。本当にいつにない早い春の訪れである。
「このままでは会式に花がないかもしれん…」「あんまり早よ咲くと、人出が減るのではないか…」などと、吉野の町ではあまりに早い春の訪れに、皮算用をして、心配顔である。花見客を目当てにして、商売をしている町人にとっては、当たり前の心配であろう。それはそれで人の営みというものであろうと、ご本尊もこそばゆい心地で微笑んでおられるにちがいない。
いずれにしても、桜で以て、今年もまた、金峯山浄土の荘厳が行われるのである。何度も言うが、本当に有り難いことである。この有り難さ、花を前に多くの人々と分かち合いたい気持ちで一杯である。
*************
「花」と題した小文は平成元年4月に書いた。私の処女作『吉野薫風抄』(白馬社刊)にも載せている。「花と蔵王権現」と題名を変えて書きなおしたのだが、リメイクしたとき、西行忌と満月と花の希なことは削除して書き直した。今年の西行忌が3月下旬の満月とはしらなかったのだ。
ところが、「こんなん書いたよ~」って、映画監督の河瀨直美さんにメールしたら、「今年の旧暦2月16日は新暦の3月27日で、満月だよ~」って教えてもらって、驚いたのだった。25年前と同じような符合の暦。で、また「やまとびと」のリメイク原稿にも、西行忌と満月と花を入れて、書いたのだった。今宵はそんな西行忌である。夜、晴れるといいねえ。
※写真は、吉野山の桜(3/31撮影)。これはシロヤマザクラではなく、ソメイヨシノのようだ
今日は西行忌
今日は旧暦の2月16日西行忌である。例年より時期の遅い西行忌で、しかも春が早い。桜の開花も例年よりずいぶんと早い。そして今日は満月でもある。
「願わくば花の下にて春死なむ その如月(きさらぎ)の望月のころ」と西行が辞世の歌を詠んだのは有名な話だが、花と満月と西行忌が、今年は重なり合っている。その話は先日、「やまとびと」に書いた。ブログやFBでも紹介した。実は正直にいうと、あの原稿は今から25年前に書いたエッセイのリメイク版である。で、25年前の原文を紹介する。
*******************
「花」は神仏への供養を表す。あるいは、下界の浄土そのものを象徴する、という。今年も春が訪れ、吉野のお山にも花の開花が告げられた。いつもながらの観光客で山はにぎわうことだろう。
吉野の花は山桜である。そして山桜はご本尊金剛蔵王権現様のご神木である。春が来て、全山が桜色に染まる風景に接するたびに、ご本尊への供養の心を新たにさせていただいている。この桜花は、金峯山浄土そのものを荘厳しているにちがいない。吉野の里人ならずとも、この有り難さはわかることであろう。
「願わくば花の下にて春死なむ その如月の望月のころ」と詠んだのは西行法師であった。吉野の桜を愛し、吉野に住した西行は、釈尊入滅の2月15日、満月の頃に、桜の花の咲く下に生涯を終えたいと念願して、この歌を詠んだという。そして西行はその願いどおり、2月16日に死をむかえたのであった。今から800年ほどの昔のことである。
今の吉野山では、西行のいう如月望月に花が咲くことは極めて希(まれ)である。が、その希なことが今年になって起きた。今年は春分の日の翌日に当たったが、この日、吉野山には満開を迎えた桜花が何本かあったのである。本当にいつにない早い春の訪れである。
「このままでは会式に花がないかもしれん…」「あんまり早よ咲くと、人出が減るのではないか…」などと、吉野の町ではあまりに早い春の訪れに、皮算用をして、心配顔である。花見客を目当てにして、商売をしている町人にとっては、当たり前の心配であろう。それはそれで人の営みというものであろうと、ご本尊もこそばゆい心地で微笑んでおられるにちがいない。
いずれにしても、桜で以て、今年もまた、金峯山浄土の荘厳が行われるのである。何度も言うが、本当に有り難いことである。この有り難さ、花を前に多くの人々と分かち合いたい気持ちで一杯である。
*************
「花」と題した小文は平成元年4月に書いた。私の処女作『吉野薫風抄』(白馬社刊)にも載せている。「花と蔵王権現」と題名を変えて書きなおしたのだが、リメイクしたとき、西行忌と満月と花の希なことは削除して書き直した。今年の西行忌が3月下旬の満月とはしらなかったのだ。
ところが、「こんなん書いたよ~」って、映画監督の河瀨直美さんにメールしたら、「今年の旧暦2月16日は新暦の3月27日で、満月だよ~」って教えてもらって、驚いたのだった。25年前と同じような符合の暦。で、また「やまとびと」のリメイク原稿にも、西行忌と満月と花を入れて、書いたのだった。今宵はそんな西行忌である。夜、晴れるといいねえ。