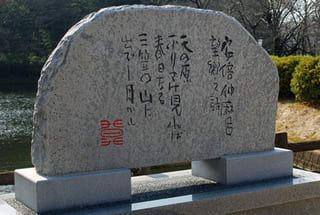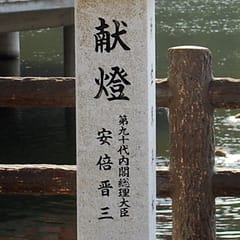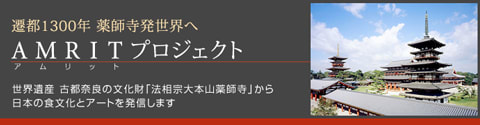お店の近くに住む会社のOBから、「蕎麦処 はやし」(奈良市南袋町1番地)という美味しいおそば屋さんがあると、以前から聞かされていた。老舗料理旅館「古都の宿むさし野」の女将さんのブログ(女将の独り言)にも、《旅館の朝の仕事が終わると、ほとんどお昼に近い時間です。それでお昼によく行くお蕎麦屋さんを、ご紹介しましょう》として、このお店が紹介されている。
※ランチタイム(女将の独り言)
http://www.nara-musashino.com/cgi-bin/info/info.cgi?num_begin=55&mode=&session=

《奈良には、沢山のお蕎麦屋さんがありますが、ここのいいのは、おうどんもあって、専務君のお腹にも十分応えてくれます。ここのご主人は、大阪の道頓堀の今井で、修行なされた方で出汁が美味しく、また1品もなかなかのものです。私はおうどん派なのですが、ここのおうどんは御蕎麦のおまけではなく、しっかりと腰のあるい美味しいおうどんです。いつも鴨なんばうどんを頼んで、出汁が見えなくなるまで山椒を振っていただきます》。
※古都の宿むさし野(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/4943b6a8848db69d1fa48b77bb080b64

鴨のない時期は、天ぷらうどんだそうだ。《天麩羅とおうどんが、別々に出てくるんです。ですから、天麩羅がシュンとしないでいただけます。美味しいお出汁は、いつも全部飲んでしまいます。宜しければ1度、是非お出かけ下さい》と、写真入りで紹介されている。

私の勤務先では、毎年仕事納めの12/30、有志数名を募ってそばを食べに行くことにしている。一昨年は「かえる庵」(奈良市下三条町)、昨年は「季のせ」(奈良市東寺林町)と、市内のそば名店を順ぐりに訪ねている。さて今年は、となったときに思いだしたのが「蕎麦処 はやし」である。著名な料理旅館の女将が太鼓判を押すくらいだから、美味しいに違いない。
※かえる庵で年越しそば(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/1524880393baf8e8ce45c3b17c498eb8
※季のせの辛味大根そば(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/f1212b7eeb18ac83f406797c0d53592e
とにかくいちど味見をしておこうと、お昼(12/27)にお邪魔した。いただいたのは店先の黒板にあった、昼のおすすめ「蕎麦セット」1,250円である。ざるorかけ、かき揚げ(ホタテ入り)、ちりめんご飯、一品、漬け物、そばもち(限定10名)とある。そばは十割。これは豪華だ。それが次の写真である。

むさし野の女将が書いているとおり、天ぷらは揚げたて、あつあつである。麺のゆであがりとピッタリ合わせて、天ぷらが揚がるのである。「当店の蕎麦は、すべて手打ちで湯がきたてでございますので、なるべく早くお召し上がり下さいませ」とあったので、まずは石臼挽きの十割そばを。安曇野産のそばは、細めだがコシがある。ほんのりとした甘みが感じられ、のど越しも抜群だ。
やや甘めのツユが、そばの味を引き立てる。そば湯はあっさりとしてとろみがある。そば粉をとかして作られたものなのだろう。お浸しにも漬け物にも手を抜いていない。締めのそば餅は、名古屋のういろうのような食感で、抹茶の味が引き立っている。これは良い店を発見した。ここに皆をつれて来よう!



で、本番の12/30(木)、同じ職場の8人でお店を訪ねた。豊祝の熱燗2合900円(1合は500円)をちびちびやりながら、蕎麦味噌300円、タコのやわらか煮600円、帆立の天ぷら、牡蠣の天ぷら、タコの天ぷらなどを突つく。人数が多いので、たくさんの一品ものを少しずつ食べられるのが有り難い。ネーミングの通りタコはとても柔らかいし、帆立も牡蠣も大ぶりで新鮮、とても美味しい。


さて、いよいよ真打ち登場である。おそばは「限定10名様」という「割子蕎麦」1,200円を8人全員が注文(=トップ写真)。これは圧巻だ。生卵、山かけ、辛味大根の入ったそばが3皿出てくる。まずは生卵の皿にツユを注ぎ、卵をからめてそばをいただく。次に、皿に残ったツユを山かけそばに注ぎ、これとからめていただく(適宜、新しいツユを足す)。最後に、残ったツユを辛味大根そばにかけていただく…。うーん、これは美味しいおそばの美味しい食べ方だった。みんな大満腹、大満足だ!

締めに蕎麦餅をいただいた
読売奈良ライフの『奈良 麺通88選』1,050円には《主人の林宏典さんは会社員を辞めた後、大阪の老舗で修業を積んだ本格派》。そばは《ほのかに香るそばの風味とつるつるしたのど越しが同時に楽しめる熟練の逸品だ。ダシは利益度外視で上質の鰹、さば、うるめ節と羅臼昆布を用いて丁寧に旨味をとる》。

《「お客様には健康的でいいものを食べてほしい」という思いから、有機野菜や雑穀米も積極的に取り入れる。そばはもちろん一品料理にまで、こだわり抜く同店だが「気負わず、日常的に食べに来てほしい」と林さんは語る。その言葉に従って、気軽に通いたくなる店だ》。
奈良には美味しいおそば屋さんが多い。この店は、その筆頭格の1つである。奈良で味わえる安曇野の十割蕎麦、皆さんぜひお訪ねいただきたい。
※奈良市南袋町1番地(近鉄奈良駅から、やすらぎの道をひたすら南下。徒歩10分ほど)
℡0742-23-5589 Pあり
11:30~14:30 17:30~20:00 水曜定休・火曜の夜も休
※食べログ
http://r.tabelog.com/nara/A2901/A290101/29002012/dtlrvwlst/1556859/
※ランチタイム(女将の独り言)
http://www.nara-musashino.com/cgi-bin/info/info.cgi?num_begin=55&mode=&session=

《奈良には、沢山のお蕎麦屋さんがありますが、ここのいいのは、おうどんもあって、専務君のお腹にも十分応えてくれます。ここのご主人は、大阪の道頓堀の今井で、修行なされた方で出汁が美味しく、また1品もなかなかのものです。私はおうどん派なのですが、ここのおうどんは御蕎麦のおまけではなく、しっかりと腰のあるい美味しいおうどんです。いつも鴨なんばうどんを頼んで、出汁が見えなくなるまで山椒を振っていただきます》。
※古都の宿むさし野(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/4943b6a8848db69d1fa48b77bb080b64

鴨のない時期は、天ぷらうどんだそうだ。《天麩羅とおうどんが、別々に出てくるんです。ですから、天麩羅がシュンとしないでいただけます。美味しいお出汁は、いつも全部飲んでしまいます。宜しければ1度、是非お出かけ下さい》と、写真入りで紹介されている。

私の勤務先では、毎年仕事納めの12/30、有志数名を募ってそばを食べに行くことにしている。一昨年は「かえる庵」(奈良市下三条町)、昨年は「季のせ」(奈良市東寺林町)と、市内のそば名店を順ぐりに訪ねている。さて今年は、となったときに思いだしたのが「蕎麦処 はやし」である。著名な料理旅館の女将が太鼓判を押すくらいだから、美味しいに違いない。
※かえる庵で年越しそば(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/1524880393baf8e8ce45c3b17c498eb8
※季のせの辛味大根そば(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/f1212b7eeb18ac83f406797c0d53592e
とにかくいちど味見をしておこうと、お昼(12/27)にお邪魔した。いただいたのは店先の黒板にあった、昼のおすすめ「蕎麦セット」1,250円である。ざるorかけ、かき揚げ(ホタテ入り)、ちりめんご飯、一品、漬け物、そばもち(限定10名)とある。そばは十割。これは豪華だ。それが次の写真である。

むさし野の女将が書いているとおり、天ぷらは揚げたて、あつあつである。麺のゆであがりとピッタリ合わせて、天ぷらが揚がるのである。「当店の蕎麦は、すべて手打ちで湯がきたてでございますので、なるべく早くお召し上がり下さいませ」とあったので、まずは石臼挽きの十割そばを。安曇野産のそばは、細めだがコシがある。ほんのりとした甘みが感じられ、のど越しも抜群だ。
やや甘めのツユが、そばの味を引き立てる。そば湯はあっさりとしてとろみがある。そば粉をとかして作られたものなのだろう。お浸しにも漬け物にも手を抜いていない。締めのそば餅は、名古屋のういろうのような食感で、抹茶の味が引き立っている。これは良い店を発見した。ここに皆をつれて来よう!



で、本番の12/30(木)、同じ職場の8人でお店を訪ねた。豊祝の熱燗2合900円(1合は500円)をちびちびやりながら、蕎麦味噌300円、タコのやわらか煮600円、帆立の天ぷら、牡蠣の天ぷら、タコの天ぷらなどを突つく。人数が多いので、たくさんの一品ものを少しずつ食べられるのが有り難い。ネーミングの通りタコはとても柔らかいし、帆立も牡蠣も大ぶりで新鮮、とても美味しい。


さて、いよいよ真打ち登場である。おそばは「限定10名様」という「割子蕎麦」1,200円を8人全員が注文(=トップ写真)。これは圧巻だ。生卵、山かけ、辛味大根の入ったそばが3皿出てくる。まずは生卵の皿にツユを注ぎ、卵をからめてそばをいただく。次に、皿に残ったツユを山かけそばに注ぎ、これとからめていただく(適宜、新しいツユを足す)。最後に、残ったツユを辛味大根そばにかけていただく…。うーん、これは美味しいおそばの美味しい食べ方だった。みんな大満腹、大満足だ!

締めに蕎麦餅をいただいた
読売奈良ライフの『奈良 麺通88選』1,050円には《主人の林宏典さんは会社員を辞めた後、大阪の老舗で修業を積んだ本格派》。そばは《ほのかに香るそばの風味とつるつるしたのど越しが同時に楽しめる熟練の逸品だ。ダシは利益度外視で上質の鰹、さば、うるめ節と羅臼昆布を用いて丁寧に旨味をとる》。

《「お客様には健康的でいいものを食べてほしい」という思いから、有機野菜や雑穀米も積極的に取り入れる。そばはもちろん一品料理にまで、こだわり抜く同店だが「気負わず、日常的に食べに来てほしい」と林さんは語る。その言葉に従って、気軽に通いたくなる店だ》。
奈良には美味しいおそば屋さんが多い。この店は、その筆頭格の1つである。奈良で味わえる安曇野の十割蕎麦、皆さんぜひお訪ねいただきたい。
※奈良市南袋町1番地(近鉄奈良駅から、やすらぎの道をひたすら南下。徒歩10分ほど)
℡0742-23-5589 Pあり
11:30~14:30 17:30~20:00 水曜定休・火曜の夜も休
※食べログ
http://r.tabelog.com/nara/A2901/A290101/29002012/dtlrvwlst/1556859/