高崎線は行き帰りとも電車のくるタイミングが絶妙だったのに、京浜東北線と武蔵野線は接続が悪く、大宮と南浦和で待つことそれぞれ十分ずつ。新松戸の二つ手前・三郷駅に着いたのは午後三時近い時間でした。
馬橋・萬満寺の仁王尊股くぐりは午後四時までです。
あと一時間では観音寺と赤城神社の二か所を巡る時間はありません。一つだけに絞っても間に合わないかもしれない。
といいながら、春秋の例祭と正月と、年に三回しかない股くぐりと、来週でも再来週でも見に行ける二本目のムクロジ(無患子)と、どっちを優先するかといえば、むろん無患子(ムクロジ)のほうです。

三郷駅で降りて江戸川を渡ります。堤には一面の菜の花。ツクシ(土筆)も見つけました。
歩行者と自転車専用の橋のたもとに立つと、江戸川の彼方、左前方にこんもりと樹の繁った小山が見えました。ムクロジがあるという赤城神社です。
伝承では、この小山はかつて洪水が起きたとき、群馬県の赤城山の山体の一部が流れてきてここに流れ着いたものだと伝えられています。流山という地名も、そのことに由来するといわれ、付近の地名も流山市流山。
あるいは、その大洪水のときに、上州赤城神社のお札がこの小山に流れ着き、お祀りしたので赤城神社とした、という説もあります。
赤城神社のある赤城山のカルデラ湖・大沼から流れ出る沼尾川は利根川の支流です。江戸川はかつての利根川ですから、こちらのほうがリアリティがあります。
観音寺は橋を渡ったあと、赤城神社方向とは逆に、道を右に折れなければなりません。右へ行くか左へ行くか。寒風に吹かれて川を渡りながら、観音寺訪問は次の機会、と決めました。
時間的に際どい、といいながら、お寺があれば寄らないわけにはいきません。ことにこの流山寺は我が曹洞宗のお寺ですから、なおさらです。
本堂前には流山七福神のうち、大黒天が祀られていました。
三郷駅から徒歩二十分で到着。赤城神社の大注連縄(しめなわ)です。
長さ10メートル、太さ1・5メートル、重量700キロ。毎年十月初めに氏子たち総出でつくられるのだそうです。
参道途中にあったムクロジの樹。
向こう側に隠れている説明板がなければ、これがムクロジだとは気づかず、通り過ぎてしまうところでした。
こちらは先に見てきた北上尾・龍山院のムクロジです。樹齢が格段に違うようだとはいえ、まるで似て非なるもののように見えます。
木肌は同じはずですが、私には違うように感じられます。まあ、人間でも二十歳の肌と六十歳の肌は同じように見えて、じつは違うので、素人の私には違って見えるのかもしれません。
しかし、樹齢によって木肌が違って見えるというのでは、観音寺に行ったときに、説明板でもなければ見つけられる自信はありません。
赤城神社の説明板には、ムクロジの実を見つけたら持ち帰ってください、とありました。そんなことが書かれているので、みんなに拾われてしまうのか、ここでは収穫ゼロ。
この熊笹は上州赤城山の熊笹と同じ種類なのだそうです。
イネ科の植物ですから、洪水とともに種が流されてきたのか、あるいは本当に山の一部が流されてきたのか。
赤城神社。
赤城神社の麓にある真言宗光明院。
本堂は改修工事中で、がらんどうでした。
光明院境内にある秋元双樹夫妻の墓。
秋元双樹、本名は三左衛門(1757年-1812年)。流山の醸造家の五代目で、家業のかたわら俳句をたしなみ、小林一茶のパトロンでもありました。
一茶と双樹の交友関係が深かったことを記念して建てられた一茶双樹記念館です。
先を急ぐので、写真だけ撮らせてもらって、前を通過。
長流寺。慶長十二年(1607年)、開山の浄土宗のお寺です。
伊勢の人・覺譽というお坊さまが東国布教のおり、ここに草庵を結んだのが始まりと伝えられていますが、天保七年(1836年)十月の火事で全焼。再建されたのは元治元年(1864年)。
長流寺に祀られている流山七福神のうち、恵比寿天。
長流寺境内から眺めた赤城山(赤城神社)です。右の青いシートは改修中の光明院本堂。
馬橋へ行くため、平和台駅から流鉄に乗りました。
通勤の行き帰りには必ず越えなければならない流鉄の踏切で毎朝見ている電車ですが、乗るのは二度目。
二両編成の二両目に乗ったら、誰もいませんでした。
乗客の大部分は平和台から三つ目の幸谷駅で降りて、JR(新松戸)に乗り換えるため、改札口に近い先頭車両に集まっているのです。
馬橋到着は十五時五十五分。仁王尊股くぐり終了まであと五分。
平和台駅で電車を待っているときから間に合わないのはわかっていましたが、時間を見るためにコートのポケットから何度も携帯電話を出していたので、同じポケットに入れていた切符を落としてしまったようです。流鉄はスイカに対応していないので、切符を買わなければならないのです。
改札口に到るまでに、立ち止まってポケットをまさぐること数分。いくら捜しても見つけられず、もう一度百九十円也を払うしかない、と諦めたとき、ちょうど四時となりました。
馬橋駅から萬満寺まではセカセカと歩いても、およそ五分かかります。私が着いたときにはすでに参詣人の姿はありませんでした。
山門の向こうに屋台の青テントが見えますが、商売人たちも帰り支度をしていました。
萬満寺本堂。
本堂側から見た中門。ここに仁王尊がおわします。
無病息災が叶うという股くぐりはできませんでしたが、ムクロジに会えたこと、その実を二つも得られたことで、私には充分に価値のある休日になりました。
さらにもう一つうれしかったこと……。
馬橋駅で料金を払おうとしたら、買った切符の金額を訊かれ、答えが正解だったからか、お金をとられなかったことです。
駅員の名札をちゃんと見ておけばよかった。中気除不動尊霊場
最新の画像[もっと見る]
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
2024年六月の薬師詣で・中野区
8ヶ月前
-
 2024年五月の薬師詣で・豊島区
9ヶ月前
2024年五月の薬師詣で・豊島区
9ヶ月前
-
 2024年五月の薬師詣で・豊島区
9ヶ月前
2024年五月の薬師詣で・豊島区
9ヶ月前
-
 2024年五月の薬師詣で・豊島区
9ヶ月前
2024年五月の薬師詣で・豊島区
9ヶ月前










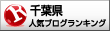







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます