仙佳作天童楷書本黄楊彫駒です。
修復が完了しました。
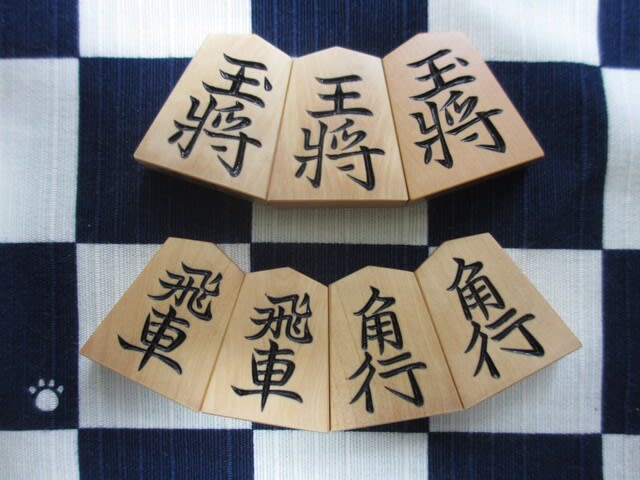
そのまま再販しても良かったのですが、
駒修復へのご理解に感謝の意を表し、
玉将1枚と余り歩兵1枚を加え、
桐製の平箱も付けました。
オークションに出しましたので、
よろしければご覧ください。
⇒ヤフオク
修復が完了しました。
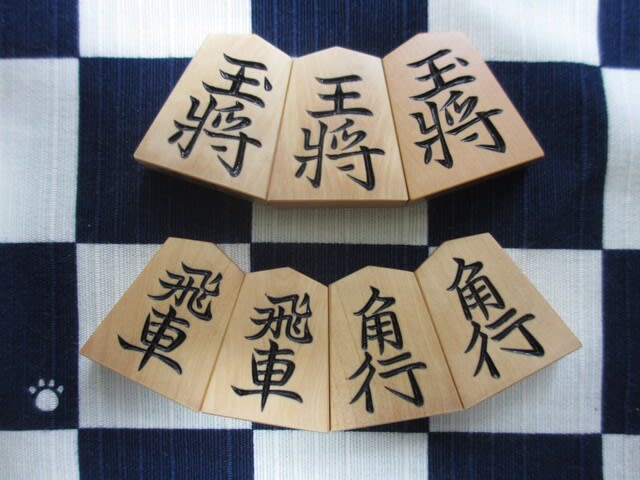
そのまま再販しても良かったのですが、
駒修復へのご理解に感謝の意を表し、
玉将1枚と余り歩兵1枚を加え、
桐製の平箱も付けました。
オークションに出しましたので、
よろしければご覧ください。
⇒ヤフオク




















































