クサギ

豊田市の家下川のクサギ。
8月6日、もうすぐ正午の撮影です。
真っ黒な雲が出ています。

家下川の堤防に数か所、群れて咲いています。

ここから本題。
クサギのシベですが、雄しべと雌しべで活動時期が異なります。
上の画像の3つの花でいうと、一番上が雌しべが1っ本だけまっすぐ前へ出ています。
下の2つの花では雄しべがまっすぐ前へ伸びていて、雌しべは垂れ下がっています。

この画像では 皆おしべが元気です。
一本だけ先に葯のついていないシベが下を向いていますが、それがめしべです。
順番ですが、まず雄しべたちがまっすぐ伸びて活動します。

ある時期が過ぎると、上のように、雄しべはくるっと丸くなり、こんどは雌しべがまっすぐ伸びます。

(電線が邪魔ですが)
上の花はおしべがまだ伸びていますが、雌しべも伸びだしているので、ちょうど交代時期のようです。
ボタンクサギ

ボタンクサギもボタンのような花を咲かせるクサギ属なので、雌雄シベの挙動は同じはずです。
ちょっと調べてみましょう。

端っこの方にシベが一本だけ出ている花が多いです。一本だけ伸びているシベは めしべです。

めしべが伸びている花は やはり雄しべがくるっと巻いています。

手前の花は雄しべと雌しべの両方が伸びています。交代期のようです。
奥の花は雌しべだけが伸びています。

蜜はラッパ状の花の奥にあるため、長い口吻(こうふん)を持っている昆虫しかありつけない仕組みになっています。
蜜は開花とともに分泌しだし、めしべ活動期になっても出し続けます。そして雌しべが受粉すると分泌を停止するようです。(住吉 啓三・川窪 伸光「クサギClerodendrum trichotomum Thunb.の雄性先熟と花蜜分泌」.pdf)
.

豊田市の家下川のクサギ。
8月6日、もうすぐ正午の撮影です。
真っ黒な雲が出ています。

家下川の堤防に数か所、群れて咲いています。

ここから本題。
クサギのシベですが、雄しべと雌しべで活動時期が異なります。
上の画像の3つの花でいうと、一番上が雌しべが1っ本だけまっすぐ前へ出ています。
下の2つの花では雄しべがまっすぐ前へ伸びていて、雌しべは垂れ下がっています。

この画像では 皆おしべが元気です。
一本だけ先に葯のついていないシベが下を向いていますが、それがめしべです。
順番ですが、まず雄しべたちがまっすぐ伸びて活動します。

ある時期が過ぎると、上のように、雄しべはくるっと丸くなり、こんどは雌しべがまっすぐ伸びます。

(電線が邪魔ですが)
上の花はおしべがまだ伸びていますが、雌しべも伸びだしているので、ちょうど交代時期のようです。
ボタンクサギ

ボタンクサギもボタンのような花を咲かせるクサギ属なので、雌雄シベの挙動は同じはずです。
ちょっと調べてみましょう。

端っこの方にシベが一本だけ出ている花が多いです。一本だけ伸びているシベは めしべです。

めしべが伸びている花は やはり雄しべがくるっと巻いています。

手前の花は雄しべと雌しべの両方が伸びています。交代期のようです。
奥の花は雌しべだけが伸びています。

蜜はラッパ状の花の奥にあるため、長い口吻(こうふん)を持っている昆虫しかありつけない仕組みになっています。
蜜は開花とともに分泌しだし、めしべ活動期になっても出し続けます。そして雌しべが受粉すると分泌を停止するようです。(住吉 啓三・川窪 伸光「クサギClerodendrum trichotomum Thunb.の雄性先熟と花蜜分泌」.pdf)
.














































































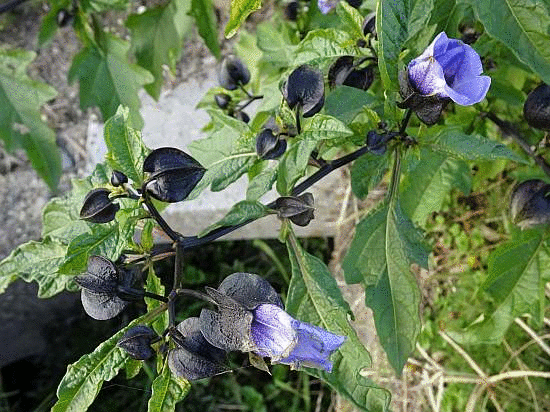
























 花弁の基部から
花弁の基部から


























