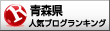ルーツ
2018年07月29日 | 食
短太系きゅうりで一番有名なのは「加賀太きゅうり」。
加賀百万石の人気、金沢の人気も手伝って知名度はNo.1です。
かつて加賀藩で食べられていキュウリとお思いでしょうが
実は加賀にこの種子が持ち込まれたのはなんと昭和11年。
東北の短太系きゅうりの種子を持ち込んだところ
地元で栽培していたきゅうりと交雑して誕生してます。
ここで気になるのが親となった「東北の短太系きゅうり」。
もしかしたら青森県八戸市の糠塚地区で栽培されていた
在来種「糠塚きゅうり」かもしれません。
しかし糠塚きゅうりはシベリア系太系きゅうりと呼ばれます。
ということはこの糠塚きゅうりも昔、
シベリアから入ってきたのかもしれません。
ルーツを探っていけばとても面白い自由研究ができるかもしれません。
ご覧ください。今年も店頭に太くて短い「糠塚きゅうり」が並び始めました。
暑い夏、真っ只中です。
加賀百万石の人気、金沢の人気も手伝って知名度はNo.1です。
かつて加賀藩で食べられていキュウリとお思いでしょうが
実は加賀にこの種子が持ち込まれたのはなんと昭和11年。
東北の短太系きゅうりの種子を持ち込んだところ
地元で栽培していたきゅうりと交雑して誕生してます。
ここで気になるのが親となった「東北の短太系きゅうり」。
もしかしたら青森県八戸市の糠塚地区で栽培されていた
在来種「糠塚きゅうり」かもしれません。
しかし糠塚きゅうりはシベリア系太系きゅうりと呼ばれます。
ということはこの糠塚きゅうりも昔、
シベリアから入ってきたのかもしれません。
ルーツを探っていけばとても面白い自由研究ができるかもしれません。
ご覧ください。今年も店頭に太くて短い「糠塚きゅうり」が並び始めました。
暑い夏、真っ只中です。