読者の方の中にもギター弾きが多いと思う
メンテで特に注意しているポイントはあるだろうか?

ネットなど『ギターのメンテナンス』で検索してみると色々な意見が見つかるのだ
概ね間違った情報というものは少ないように感じるが・・・
中には『思い込み』的な偏った意見もあるようなので
今回は私のメンテ方法についてご紹介したいと思うのだ
個人的にはメンテは非常に重要な作業だと考えているのだ
頑張って良いギターを手に入れてもメンテが不十分では良いギターも台無しなのだ
実はこのような人が意外にも多いようだ
今回は4本のエレキを同時にメンテしたのだ
楽器店のお兄さんのように所有するギターが100本を越えるような場合には気が付いた時に行えば良い気がする
「来週のライブに備えてメンテしておこうかなぁ・・?」
というタイミングで行っているようだ
私の場合には本数が少ないだけに常にすべてのギターを『最善の状態』に保っておきたいのだ
使用頻度もほぼ同等なのだ
まずはストラトなのだ

弦交換の際にフレットの減りなどヤスリで調整することもあるのだ
冬場のメンテにおける必須の作業は指板のリフレッシュに尽きると思う

冬場に人間の肌が乾燥するようにギターも常に湿度の影響を受けているのだ
メーカー出荷時にそれなりにオイルを塗布しているので放置しておいても重大なトラブルになることは少ない
ギターを大切にしたいという人はオイルは必須なのだ
オイルにもオレンジオイルとレモンオイルがあるのだ
「違いは何?」
という方も多いと思う
オレンジオイルは汚れ落としがメインなのだ
一方のレモンオイルには汚れ落としの効能は期待できないのだ
両方とも試したのだが特に違いは感じられなかったのだ
そもそも、指板が手垢などでコテコテに汚れているような人は演奏以前の問題なのだ
面倒を見ながらギターに接しているという場合には特に問題になるような事はないと思う
ちなみにオイルの塗り方が間違っている人が多いようだ
正しい塗り方は指板にタップリとオイルを塗り、そのまま10分ほど放置するのだ
相手が木材だけにオイルの染み込みに少々時間がかかるのだ
「フレットに悪影響はないの?」
という方も多いと思う
経年劣化でフレットと指板の間に僅かな隙間があくことがあるが・・・
原因は『指板の痩せ』なのだ
これはどんなに手入れをしてもどんなギターにも起こるものなのだ
指板の痩せを防ぐ意味でも乾燥は大敵だという事なのだ
年に4回ほどで良いという書籍もあるが・・・
個人的には弦交換2回の一度程度のオイル塗布が望ましいと思うのだ
乾燥が著しいと言う場合にはもっと多頻度でも構わないと思うのだ
適度にオイルが染みた指板は感触や艶も良くなるのだ
ストラトの弦交換で面倒なのが裏ブタの取り外しなのだ
私の場合にはちょっとした工夫で蓋をしたまま弦交換しているのだ

ブリッジに厚紙を挟むことでブリッジを固定するのだ

これによって通し穴がカバーから顔を覗かせるのだ

通年、カバーを外している人がいるようだが個人的には嫌いなのだ
最初から付いているものは付けておきたいと思うのだ
トレモロのスプリングも弦のゲージとセットアップが完了すれば狂うことは少ないのだ
「あれ? またチューニングが狂ってるよ~」
という場合にはセットアップが不十分だという事なのだ
キモは
”弦のテンションとスプリングのテンションの釣り合い・・”
なのだ
ストラトは好きだけどチューニングが不安定だから嫌だ・・
という人も多いのだ
クラプトンを真似てブリッジを固定している人もいるようだが・・
正直な話、ストラトの美味しい部分をスポイルしている事になるのだ
目指すべきはジェフベックのクオリティなのだ
次はレスポールなのだ

レスポールもストラトと同様にオイルをタップリと塗布したのだ
購入時には木目に深みがないように感じたのだが最近は良い具合に色が定着しているのだ
オイル効果なのだ
楽器店のお兄さんが厳選した数本をさらに私が選定したレスポールなので良いのは当然なのだ
レギュラーラインのレスポールを云々言う人がいるようだが・・・
どれほどギターを知っているのだろうか?
ちょっとだけ残念な人々だと感じてしまう
調整が不備なカスタムショップ製よりも
メンテが充分に施されたレギュラーラインの方が良い音がすると思う
あくまでもヴィンテージのそれに拘ったモデルよりも現代的にアレンジされたレスポールの方が良いと思う

以前にもご紹介したがナシュビルタイプのサドルは本当に秀逸だと思う
「ナシュビルだとヴィンテージの音がしないんだよね~」
という人がいるが・・・・
素人ギター弾きにサドルの違いが分かるのだろうか?
そんな言葉に振り回されている人も多いように感じるのだ
トーカイとアリアも同様に弦交換とオイル塗布を行ったのだ
4本共にネックの状態は良好なのだ
最近はまったくネックが動かなくなったのだ
私の書斎の環境にエレキが順応したという証なのだ
ネックの反りに悩まされている方も多いと思う
そんな場合には気長にギターに付き合うしか方法はないのだ
「面倒臭いなぁ・・・」
という人はそれまでなのだ
ある意味でギターは生き物なのだ
メンテを疎かにされたギターが良い音で鳴ってくれるはずもないのだ
十分にメンテが行き届いたギターは初心者が弾いてもそれなりに鳴るものなのだ
ネックの状態と共にギター弾きの『永遠の悩み』が弦高調整なのだ
「結局、弦高ってどのくらいにすればいいの?」
ネットでも多く寄せられる質問事項なのだ
弦の太さと弦高は弾き易さに大きく影響する部分なのだ
音色と調整の傾向をまとめてみたい
太いゲージで弦高を上げた状態が最も良い鳴りのギターになるのだ
当然ながらエレキも弦楽器なのだ
いかに弦がストレスなく振動するか?
が重要なのだ
ネックは順反り、弦高は高く、使用弦も太いもの・・
これがベストな状態なのだ
しかしながら、楽器だけに『弾き易さ』も重要なのだ
特に弦高はマックスの状態から音色と弾き易さを検討しながら煮詰めていくのだ
弦高にも標準があるのだ
一般的には12フレット付近、1弦側が1.5㎜、6弦側が2.0㎜と言われているのだ
ポイントは0.5㎜という差なのだ
6弦側を調整してもこの数値は維持すべきなのだ
巻き弦が太く、プレーン弦が細いという特殊なゲージ以外にはこのバランスがベストだといえるのだ
面倒でもネックの調整の度に弦高は入念にチェックすべきだと思う
最近の私のセッティングをご紹介したいのだ

1弦側が1.32、6弦側が1.87なのだ
不要なピックを張り合わせて目安にしているのだ
厳密には接着剤の厚みが加わっていると思うのだ
その辺りはアバウトだが・・
極力、薄く接着しているので概ねこの数値になっていると思われる

撮影の為に寝かした状態だが実際にはギターを立てた状態でピックが固定される感じなのだ

ギターごとに微調整する人も多いと聞くが・・・
私の場合には気に入ったポイントが見つかった場合にはすべてのギターに適応するようにしているのだ
演奏上、都合が良いのだ
弦高が決まった状態で最終的にオクターブ調整に至るのだ
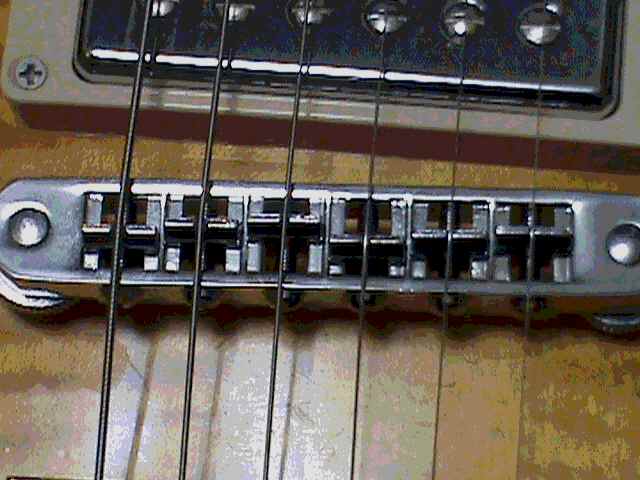
ギターごとに個体差があるがサドルの正しい配置の一例のだ
細い弦から太い弦にかけて徐々にサドルが後方にズレるのだ
4弦が3弦の前に位置するのは良いのだ
プレーン弦と巻き弦の振動幅の違いなのだ
読者の皆さんもご自分のギターをチェックしていただきたい
まったく異なるという場合には一度、楽器店で診断してもらうことをお薦めしたい
サドルが回り切ってしまうという状態も何らかのトラブルを抱えている場合が多いのだ
ネックなのか? ブリッジなのか? フレットなのか?
そもそもギターの品質なのか?
メンテとは無関係だが最近のお気に入りのピックはダンロップ製のULTEXなのだ

非常に気に入っているのだ
数種類の厚みを試してみたのだが・・・
最終的に1.0㎜が気に入ったのだ

これ一枚でカッティング、アルペジオ、ソロが弾けるのだ
ナイロンのピックと比較しても消耗が少ないように感じられるのだ
少し擦り減った感じも悪くない使用感なのだ
しばらくはこのピックを愛用する事になりそうなのだ
ダダリオの弦と共にダンロップのピックも品質が安定している
どこの楽器店でも購入できるという気軽さも良いと思うのだ

オマケでバランスド弦が付いてきたのだ

弦のテンションを極力、均一にするように選定された弦なのだ
通常の010~のセットとは微妙に異なるのだ
過去に何度か使った事があるのだが私は弾き難いのだ
とりあえず弦が切れた時のスペアとして取ってあるのだ
010~と共通している弦もあるのだ
まぁ、そんな感じなので迷っている方は参考にしていただきたい
ギターは試行錯誤の連続なのだ
色々とネット検索している方も多いと思うが・・・
何を信じるか?
という部分が難しいところなのだ
ギター雑誌などでプロのセットアップが紹介されている事も多々ある
「俺も同じセッティングにしてみようかな?」
というのも悪くないと思う
プロを手本にアレンジしてみるのも楽しいと思うのだ
私も影響を受け易いタイプなのだ
「俺も真似してみようかな?」
という感じで色々なセッティングにチャレンジする事も多いのだ
ちなみにネットの素人意見は参考程度なのだ
「世間ではどんな事が流行っているのかな?」
「素人ギター弾きの多くは何に悩んでいるのかな?」
ある意味ではブログのネタの参考にしているのだ
話が前後するが・・・
弦高調整のポイントは『演奏スタイル』なのだ
自分がどんな演奏がメインなのか?
これが重要なのだ
極端な例だが・・
ボトルネックを用いたスライド奏法とスィープ奏法のような速弾きではセッティング大きく異なる
ソロが主体なのか?
バッキングが主体なのか?
でも弦高が異なるのだ
この辺りの見極めが非常に奥深いのだ
速弾きならば極力、弦とフレットの距離が近い方がメリットが大きいのだ
素早い押弦にも対応し易いのだ
一方、アルペジオやカッティングならばむしろ弦高が高い方が弾き易い
さらには弦の鳴りも良くなる傾向があるのだ
数年前の私は楽器店のお兄さんも驚くほど低い弦高が好みだったのだ
1弦側で1.0㎜以下というギターもあったのだ
とにかく速く弾く事だけに燃えていた時期なのだ
最近は好きなギタリストの傾向も変わってきたのだ
ジミーペイジ、エリッククラプトン、レイヴォーン、ジェフベック、ナイルロジャースetc・・
ギターの匠ばかりだが・・

超絶速弾き系のギタリストとは対峙する存在なのだ
”ギターを歌わせる達人たち・・・”
という表現が適切だと思うのだ
共通しているのは太めの弦を用い弦高は高めだという事なのだ
ご自分のギターの音に納得していないという方は
一度セッティングを根本から見直してみては如何だろうか?
特に低い弦高に慣れている場合には一度標準値にしてみる事をお薦めしたい
激的に弦の鳴りが向上すると思うのだ
さらには予算が許す方は機材も見直す事をお薦めしたい
1万円台のトランジスタアンプでペチペチと弾いている方は良いマルチを使ってみては如何だろうか?

自分が使っているから言うのではないが・・・・
GT-100はかなりギター観が変わるマルチだと思う
「デジタルもモデリング技術もここまできたか・・」
ヘッドフォン環境ならば、まさに真空管の空気感を再現できるのだ
スタジオなどの真空管(トランジスタも可)にライン出力する事も可能なのだ
ギターはUSA製が良いと思うが・・・
周辺機器は間違いなく日本のメーカー製が良いと太鼓判が押せるのだ
実際に店頭でライバルメーカーの機器を試してみたのだが音色も使い勝手もGT-100だと思う
少々値が張るのが難点だが・・・
「ギターを極めたい!」
「ギターを一生の趣味にしたい!」
というくらいの意気込みがあるならば安い買い物だと思うのだ
zoom派だという方も一度は試していただきたい
ギター同様に周辺機器も価格相応なのだ
zoomも愛用している私だが・・
”コストパフォーマンスが良い・・”
というのがzoom機器の最大の売りなのだ

ローランドやPodとは基本的にコンセプトが異なるのだ
長々と書いてしまったが・・・
長文が好きな常連読者の方にはご満足いただけたと思う
繰り返しになるが・・・
”太い弦と高い弦高は音の張りを生み出す・・・”

という事でツェッペリンの名曲の触りをちょこっとだけ・・

メンテで特に注意しているポイントはあるだろうか?

ネットなど『ギターのメンテナンス』で検索してみると色々な意見が見つかるのだ
概ね間違った情報というものは少ないように感じるが・・・
中には『思い込み』的な偏った意見もあるようなので
今回は私のメンテ方法についてご紹介したいと思うのだ
個人的にはメンテは非常に重要な作業だと考えているのだ
頑張って良いギターを手に入れてもメンテが不十分では良いギターも台無しなのだ
実はこのような人が意外にも多いようだ
今回は4本のエレキを同時にメンテしたのだ
楽器店のお兄さんのように所有するギターが100本を越えるような場合には気が付いた時に行えば良い気がする
「来週のライブに備えてメンテしておこうかなぁ・・?」
というタイミングで行っているようだ
私の場合には本数が少ないだけに常にすべてのギターを『最善の状態』に保っておきたいのだ
使用頻度もほぼ同等なのだ
まずはストラトなのだ

弦交換の際にフレットの減りなどヤスリで調整することもあるのだ
冬場のメンテにおける必須の作業は指板のリフレッシュに尽きると思う

冬場に人間の肌が乾燥するようにギターも常に湿度の影響を受けているのだ
メーカー出荷時にそれなりにオイルを塗布しているので放置しておいても重大なトラブルになることは少ない
ギターを大切にしたいという人はオイルは必須なのだ
オイルにもオレンジオイルとレモンオイルがあるのだ
「違いは何?」
という方も多いと思う
オレンジオイルは汚れ落としがメインなのだ
一方のレモンオイルには汚れ落としの効能は期待できないのだ
両方とも試したのだが特に違いは感じられなかったのだ
そもそも、指板が手垢などでコテコテに汚れているような人は演奏以前の問題なのだ
面倒を見ながらギターに接しているという場合には特に問題になるような事はないと思う
ちなみにオイルの塗り方が間違っている人が多いようだ
正しい塗り方は指板にタップリとオイルを塗り、そのまま10分ほど放置するのだ
相手が木材だけにオイルの染み込みに少々時間がかかるのだ
「フレットに悪影響はないの?」
という方も多いと思う
経年劣化でフレットと指板の間に僅かな隙間があくことがあるが・・・
原因は『指板の痩せ』なのだ
これはどんなに手入れをしてもどんなギターにも起こるものなのだ
指板の痩せを防ぐ意味でも乾燥は大敵だという事なのだ
年に4回ほどで良いという書籍もあるが・・・
個人的には弦交換2回の一度程度のオイル塗布が望ましいと思うのだ
乾燥が著しいと言う場合にはもっと多頻度でも構わないと思うのだ
適度にオイルが染みた指板は感触や艶も良くなるのだ
ストラトの弦交換で面倒なのが裏ブタの取り外しなのだ
私の場合にはちょっとした工夫で蓋をしたまま弦交換しているのだ

ブリッジに厚紙を挟むことでブリッジを固定するのだ

これによって通し穴がカバーから顔を覗かせるのだ

通年、カバーを外している人がいるようだが個人的には嫌いなのだ
最初から付いているものは付けておきたいと思うのだ
トレモロのスプリングも弦のゲージとセットアップが完了すれば狂うことは少ないのだ
「あれ? またチューニングが狂ってるよ~」
という場合にはセットアップが不十分だという事なのだ
キモは
”弦のテンションとスプリングのテンションの釣り合い・・”
なのだ
ストラトは好きだけどチューニングが不安定だから嫌だ・・
という人も多いのだ
クラプトンを真似てブリッジを固定している人もいるようだが・・
正直な話、ストラトの美味しい部分をスポイルしている事になるのだ
目指すべきはジェフベックのクオリティなのだ
次はレスポールなのだ

レスポールもストラトと同様にオイルをタップリと塗布したのだ
購入時には木目に深みがないように感じたのだが最近は良い具合に色が定着しているのだ
オイル効果なのだ
楽器店のお兄さんが厳選した数本をさらに私が選定したレスポールなので良いのは当然なのだ
レギュラーラインのレスポールを云々言う人がいるようだが・・・
どれほどギターを知っているのだろうか?
ちょっとだけ残念な人々だと感じてしまう
調整が不備なカスタムショップ製よりも
メンテが充分に施されたレギュラーラインの方が良い音がすると思う
あくまでもヴィンテージのそれに拘ったモデルよりも現代的にアレンジされたレスポールの方が良いと思う

以前にもご紹介したがナシュビルタイプのサドルは本当に秀逸だと思う
「ナシュビルだとヴィンテージの音がしないんだよね~」
という人がいるが・・・・
素人ギター弾きにサドルの違いが分かるのだろうか?
そんな言葉に振り回されている人も多いように感じるのだ
トーカイとアリアも同様に弦交換とオイル塗布を行ったのだ
4本共にネックの状態は良好なのだ
最近はまったくネックが動かなくなったのだ
私の書斎の環境にエレキが順応したという証なのだ
ネックの反りに悩まされている方も多いと思う
そんな場合には気長にギターに付き合うしか方法はないのだ
「面倒臭いなぁ・・・」
という人はそれまでなのだ
ある意味でギターは生き物なのだ
メンテを疎かにされたギターが良い音で鳴ってくれるはずもないのだ
十分にメンテが行き届いたギターは初心者が弾いてもそれなりに鳴るものなのだ
ネックの状態と共にギター弾きの『永遠の悩み』が弦高調整なのだ
「結局、弦高ってどのくらいにすればいいの?」
ネットでも多く寄せられる質問事項なのだ
弦の太さと弦高は弾き易さに大きく影響する部分なのだ
音色と調整の傾向をまとめてみたい
太いゲージで弦高を上げた状態が最も良い鳴りのギターになるのだ
当然ながらエレキも弦楽器なのだ
いかに弦がストレスなく振動するか?
が重要なのだ
ネックは順反り、弦高は高く、使用弦も太いもの・・
これがベストな状態なのだ
しかしながら、楽器だけに『弾き易さ』も重要なのだ
特に弦高はマックスの状態から音色と弾き易さを検討しながら煮詰めていくのだ
弦高にも標準があるのだ
一般的には12フレット付近、1弦側が1.5㎜、6弦側が2.0㎜と言われているのだ
ポイントは0.5㎜という差なのだ
6弦側を調整してもこの数値は維持すべきなのだ
巻き弦が太く、プレーン弦が細いという特殊なゲージ以外にはこのバランスがベストだといえるのだ
面倒でもネックの調整の度に弦高は入念にチェックすべきだと思う
最近の私のセッティングをご紹介したいのだ

1弦側が1.32、6弦側が1.87なのだ
不要なピックを張り合わせて目安にしているのだ
厳密には接着剤の厚みが加わっていると思うのだ
その辺りはアバウトだが・・
極力、薄く接着しているので概ねこの数値になっていると思われる

撮影の為に寝かした状態だが実際にはギターを立てた状態でピックが固定される感じなのだ

ギターごとに微調整する人も多いと聞くが・・・
私の場合には気に入ったポイントが見つかった場合にはすべてのギターに適応するようにしているのだ
演奏上、都合が良いのだ
弦高が決まった状態で最終的にオクターブ調整に至るのだ
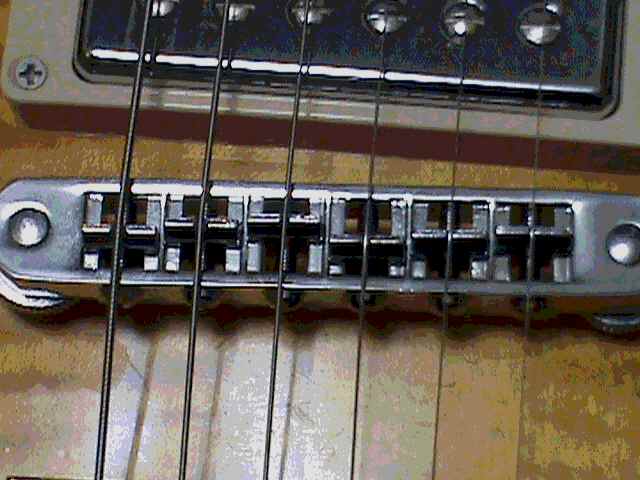
ギターごとに個体差があるがサドルの正しい配置の一例のだ
細い弦から太い弦にかけて徐々にサドルが後方にズレるのだ
4弦が3弦の前に位置するのは良いのだ
プレーン弦と巻き弦の振動幅の違いなのだ
読者の皆さんもご自分のギターをチェックしていただきたい
まったく異なるという場合には一度、楽器店で診断してもらうことをお薦めしたい
サドルが回り切ってしまうという状態も何らかのトラブルを抱えている場合が多いのだ
ネックなのか? ブリッジなのか? フレットなのか?
そもそもギターの品質なのか?
メンテとは無関係だが最近のお気に入りのピックはダンロップ製のULTEXなのだ

非常に気に入っているのだ
数種類の厚みを試してみたのだが・・・
最終的に1.0㎜が気に入ったのだ

これ一枚でカッティング、アルペジオ、ソロが弾けるのだ
ナイロンのピックと比較しても消耗が少ないように感じられるのだ
少し擦り減った感じも悪くない使用感なのだ
しばらくはこのピックを愛用する事になりそうなのだ
ダダリオの弦と共にダンロップのピックも品質が安定している
どこの楽器店でも購入できるという気軽さも良いと思うのだ

オマケでバランスド弦が付いてきたのだ

弦のテンションを極力、均一にするように選定された弦なのだ
通常の010~のセットとは微妙に異なるのだ
過去に何度か使った事があるのだが私は弾き難いのだ
とりあえず弦が切れた時のスペアとして取ってあるのだ
010~と共通している弦もあるのだ
まぁ、そんな感じなので迷っている方は参考にしていただきたい

ギターは試行錯誤の連続なのだ
色々とネット検索している方も多いと思うが・・・
何を信じるか?
という部分が難しいところなのだ
ギター雑誌などでプロのセットアップが紹介されている事も多々ある
「俺も同じセッティングにしてみようかな?」
というのも悪くないと思う
プロを手本にアレンジしてみるのも楽しいと思うのだ
私も影響を受け易いタイプなのだ
「俺も真似してみようかな?」
という感じで色々なセッティングにチャレンジする事も多いのだ
ちなみにネットの素人意見は参考程度なのだ
「世間ではどんな事が流行っているのかな?」
「素人ギター弾きの多くは何に悩んでいるのかな?」
ある意味ではブログのネタの参考にしているのだ
話が前後するが・・・
弦高調整のポイントは『演奏スタイル』なのだ
自分がどんな演奏がメインなのか?
これが重要なのだ
極端な例だが・・
ボトルネックを用いたスライド奏法とスィープ奏法のような速弾きではセッティング大きく異なる
ソロが主体なのか?
バッキングが主体なのか?
でも弦高が異なるのだ
この辺りの見極めが非常に奥深いのだ
速弾きならば極力、弦とフレットの距離が近い方がメリットが大きいのだ
素早い押弦にも対応し易いのだ
一方、アルペジオやカッティングならばむしろ弦高が高い方が弾き易い
さらには弦の鳴りも良くなる傾向があるのだ
数年前の私は楽器店のお兄さんも驚くほど低い弦高が好みだったのだ
1弦側で1.0㎜以下というギターもあったのだ
とにかく速く弾く事だけに燃えていた時期なのだ
最近は好きなギタリストの傾向も変わってきたのだ
ジミーペイジ、エリッククラプトン、レイヴォーン、ジェフベック、ナイルロジャースetc・・
ギターの匠ばかりだが・・

超絶速弾き系のギタリストとは対峙する存在なのだ
”ギターを歌わせる達人たち・・・”
という表現が適切だと思うのだ
共通しているのは太めの弦を用い弦高は高めだという事なのだ
ご自分のギターの音に納得していないという方は
一度セッティングを根本から見直してみては如何だろうか?
特に低い弦高に慣れている場合には一度標準値にしてみる事をお薦めしたい
激的に弦の鳴りが向上すると思うのだ
さらには予算が許す方は機材も見直す事をお薦めしたい
1万円台のトランジスタアンプでペチペチと弾いている方は良いマルチを使ってみては如何だろうか?

自分が使っているから言うのではないが・・・・
GT-100はかなりギター観が変わるマルチだと思う
「デジタルもモデリング技術もここまできたか・・」
ヘッドフォン環境ならば、まさに真空管の空気感を再現できるのだ
スタジオなどの真空管(トランジスタも可)にライン出力する事も可能なのだ
ギターはUSA製が良いと思うが・・・
周辺機器は間違いなく日本のメーカー製が良いと太鼓判が押せるのだ
実際に店頭でライバルメーカーの機器を試してみたのだが音色も使い勝手もGT-100だと思う
少々値が張るのが難点だが・・・
「ギターを極めたい!」
「ギターを一生の趣味にしたい!」
というくらいの意気込みがあるならば安い買い物だと思うのだ
zoom派だという方も一度は試していただきたい
ギター同様に周辺機器も価格相応なのだ
zoomも愛用している私だが・・
”コストパフォーマンスが良い・・”
というのがzoom機器の最大の売りなのだ

ローランドやPodとは基本的にコンセプトが異なるのだ
長々と書いてしまったが・・・
長文が好きな常連読者の方にはご満足いただけたと思う

繰り返しになるが・・・
”太い弦と高い弦高は音の張りを生み出す・・・”

という事でツェッペリンの名曲の触りをちょこっとだけ・・

















