今日の樹木花は、「ギンヨウアカシア(銀葉アカシア)/ ミノザ)」の花です、此の花も早春を彩る黄色い花です。
今年は、寒い日が続いた所為か、開花が、大分、遅れました。(下図 )
蕾は、”黄金" の粒です、開花を待ちました。
<「ギンヨウアカシア」(銀葉アカシア」>
開花は、3月頃からです、蕾が、膨らみ初めています、宛ら、”金の玉” ですか
開花期には、総状花序に黄色い花が、多数咲き集います。
名前の通り、葉が、灰銀色ですので、灰色のキャンバスに金の粒を鏤めた様相です。
「ミモザ」とも称していますが、正確には、「ミモザ」は、「オジギソウ」含羞草 / 眠り草 / タッチミーノット / Mimosa pudica を
指すとのこと,で、似た花の「フサアカシア」<房アカシア/ Acacia dealbata>も「ミモザ」と称しますが
此も、正確には、間違っているとのことです。
葉や花が似ているので、間違って名付けたとか、現在では、「ミモザ」の名前は、両者の総称として使われています、
確か、砂糖菓子の粒々のトッピングも<ミモザ>と呼びますね。
両者は、似ていますが、見分ける方法として、羽状複葉小葉が、「ギンヨウアカシア」は
20枚位を対生させて、葉の色が、灰緑色に対した、「フサアカシア」の小葉は、40枚位を
対生させ、多少大きめの葉は、濃緑色です。
マメ科、アカシア属、半耐寒性常緑高木、オーストラリア原産、学名 Acacia baileyana
英名 Cootamundra Wattle、別名「ミモザ」、 「ミモザザアカシア」
「ゴールデンミモザ」、「ハナアカシア」


<他の画像>
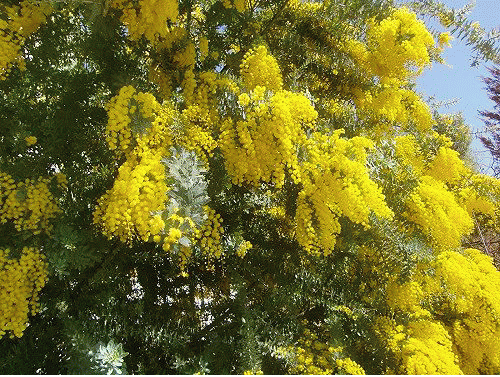
下図は、「ギンヨウアカシア」に似た花の「フサアカシア」です、「ギンヨウアカシア」も「フサアカシア」も
葉は、羽状複葉ですが、前者は、小葉が、5対に対して、後者は、10から20対位の違いが有ります。
亦、花や花が、後者の方が、大きい違いが























































