マタギに関する本は数々出ていますが、本書はそうしたマタギ関連書とは一線を画した格別の価値ある本だと思います。
検索しても書評が出てこないのが残念です。
 |
群馬藤原郷と最後の熊捕り名人狩野 順司文芸社このアイテムの詳細を見る |
本書で紹介されている熊捕り名人、吉野秀市さんのことを私は、古書で偶然見つけた松葉豊著『俺の仕事は俺一代』のなかで紹介された藤原郷の様々な職人達のひとりとして知りました。
そこで紹介された個性あふれる人々のなかでも、特に印象深い吉野さんのことについて1冊にまとめられた本が出たことは、私にとってもとても嬉しいことでした。
吉野秀市さんは、マタギなどの集団による巻狩りとは違って、ほとんど単独で猟をしてきた方です。
主に積雪期に穴にこもっている穴から熊を追い出して銃で仕留める方法です。
本書のタイトルにマタギという表現が使われていないことには好感が持てますが、一般に熊捕り猟一般をマタギと言ってしまうことにわたしたちは慣れてしまっています。
集団的な狩りの独自な手法を持った狩猟集団以外もすべてマタギと称することには、やはり無理があるのではないかと感じているのですが、かといって正しい正しくないといった議論するようなものではなく、広義のマタギと狭義のマタギの使い分けがされなくなっている程度のことであると思っています。
藤原郷で一般的に行われていた猟は、二人一組で数匹の猟犬を連れて穴熊を探し当てるものと、6、7人で行う囲いこみ猟だそうです。
もちろん、吉野さんも頑なに一人でばかり行動しえちたわけではなく、そうした人々と一緒に猟をすることもあったと思われます。
しかし、単独を原則としていた吉野さんが、1シーズンに32頭も捕った実績をもち、
さらにその生涯では300頭もの熊を捕った。
しかも大きな怪我をすることもなく、それだけの実績をのこしたということは、
吉野さんが射撃の名手であったからではありません。
もちろん、その銃の腕は、一度も撃ち損じたことはないというほどのものでした。
しかし、いかなる射撃の名手であったとしても、射撃の腕だけでそれだけの熊を射止めることは決してできません。
それは、まず何よりも熊の棲息する上州武尊から至仏山に至る山域の自然を吉野さんが熟知していたことと、
そこで生活する熊の生態を知りつくしていたことにこそあるといえます。
それは、マタギをはじめとした猟をする人々誰もが目指していたことであるにもかかわらず、吉野さんほどそれを成し遂げた人はなかなかいませんでした。
そうした魅力を本書は、吉野さんとその周辺の藤原という地域の自然環境と歴史、また家族や村の人々を丹念に取材することで、わたしたちに実に生き生きと伝えてくれています。
それは新潟や福島などと比べて、マタギの間でも山が大きいといわれる群馬の恵まれた自然あってこその物語なのかもしれません。
藤原郷の山域というものが、ひと際熊の棲息にも適した場所であったことにもよるのでしょう。
しかし、その恵まれた自然とは、とりもなおさず厳しい自然ということです。
その冬の3月頃までの間に、単独で山に入り熊を追うということは、いかなる名人といえども、数々の危機を体験することなしになにごともなしえるものではなりません。
万が一の事態に備える周到さがあっても、それは決して十分な保障にはなりえません。
そのひとつひとつの体験に、私たちは強くひきこまれるのです。
厳しい自然を生き抜いてきた経緯は、決して命を懸けるなどという冒険談ではありません。
それはなによりも生活を懸けることが大前提であったからこそ、家族の待っているところに生きて帰ることこそが最大の目標であったのだと思います。
人の少ない山奥の村だからなのかもしれませんが、ひとりひとりの力、家族の支えや同業者や先達からの教え、宝川温泉をはじめとする地域をつくっていった人々とのつながりのひとつひとつが、とても輝いたものとして語りかけてきます。
熊捕りは、林業が衰退するのと同時に毛皮や熊の胆の値段も下がり、職業としては成り立たなくなりました。
残念ながらそうした大きな変化が日本中で起きてしまいましたが、その変化とは、つい最近のことです。
私は、上野村のことや、どう考えても群馬といえる足尾町のことをみてきたのと同じ限りない魅力を、吉野秀市さんらが生きてきた藤原郷に感じるのですが、今ある群馬の自然を知るためにも、
是非、みなさんに読んでいただきたい1冊です。
群馬出身の著者は、現在神奈川在住のようですが、出来ることなら一度お会いしてみたい方です。
以上、「正林堂店長の雑記帖」より転載・加筆
















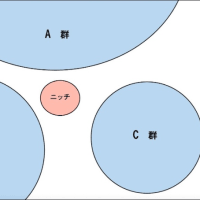

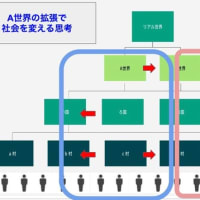

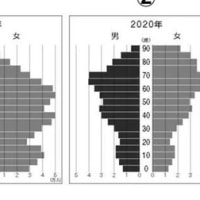






今騒がれているワシントン条約の問題ではないですが、クロマグロの件、捕鯨の件、宝石サンゴの規制など。
また里に下りてくる熊や鹿などこれもみんな愚かな人間の行動から。
真のマタギ、熊取名人は余分な猟はしなかった。捕られるがわもそれを心得、子孫の繁栄をしっかりからだに叩き込んで自然と(動物にとって人も自然の一部だったかも)共存していたとおもう。