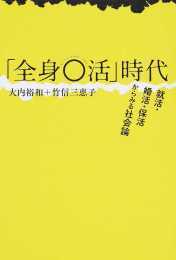大間原発をめぐって対岸の函館市が、国と電源開発に対して建設の差し止めなどを求めた訴訟【注】の、第1回口頭弁論が7月3日、東京地裁であった。
冒頭、原告側意見陳述で、工藤壽樹・函館市長は、国と電源開発への不信感を露わにした。
「きわめて横暴で、強圧的なやり方だ」
大間原発から函館市まで、津軽海峡を挟んで最短23km。事故が起きれば大きな被害を受ける。
市は、3・11後に30km圏内の自治体として避難計画の作成を国から義務づけられたが、大間原発への「同意権」はないまま。工事が2012年10月に再開された際も、「電源開発は一方的に通告しに来ただけ」【工藤市長】。
工藤市長は、大間原発の問題点を列挙し、「無期限凍結」を訴えた。
(a)世界初の「フルMOX」方式(毒性が非常に強いプルトニウムを使った燃料だけで動かす)で、危険性が高い。
(b)津軽海峡は領海が3カイリ(5.5km)しかなく、テロリストに狙われやすい。
(c)福島原発事故を招いたずさんな審査基準で許可されている。
市が訴訟の根拠に掲げるのは、の次の二つだ。重大事故によるこれらの権利への侵害を排除、予防するために原発の建設中止を求めている。
①地方自治体の存立を維持する権利(地方自治権)
②市有財産の財産権
口頭弁論では、国の代理人も異例の意見陳述に立ち、訴えを却下するよう主張した。
①’地方自治権は憲法が保障する自治体固有の権利ではない。
②’自治体の財産権は個人の財産権のようには保護されず、市には原告適格がない。
これに対して市の弁護団は、次のように反論する。この点が最初の争点になるだろう。
①''福島の事故では自治体の「生命」が失われており、存立権を実体ある権利として認めるべきだ。
②''改正原子炉等規制法には「国民の財産の権利」が明記され、市にも原告適格がある。
【注】「【原発】函館市の大間原発建設差し止め訴訟 ~自治体初~」
□小石勝(ジャーナリスト)「「大間原発の無期限凍結を」 函館市長が不信感表明」(「週刊金曜日」2014年7月18日号)
↓クリック、プリーズ。↓



冒頭、原告側意見陳述で、工藤壽樹・函館市長は、国と電源開発への不信感を露わにした。
「きわめて横暴で、強圧的なやり方だ」
大間原発から函館市まで、津軽海峡を挟んで最短23km。事故が起きれば大きな被害を受ける。
市は、3・11後に30km圏内の自治体として避難計画の作成を国から義務づけられたが、大間原発への「同意権」はないまま。工事が2012年10月に再開された際も、「電源開発は一方的に通告しに来ただけ」【工藤市長】。
工藤市長は、大間原発の問題点を列挙し、「無期限凍結」を訴えた。
(a)世界初の「フルMOX」方式(毒性が非常に強いプルトニウムを使った燃料だけで動かす)で、危険性が高い。
(b)津軽海峡は領海が3カイリ(5.5km)しかなく、テロリストに狙われやすい。
(c)福島原発事故を招いたずさんな審査基準で許可されている。
市が訴訟の根拠に掲げるのは、の次の二つだ。重大事故によるこれらの権利への侵害を排除、予防するために原発の建設中止を求めている。
①地方自治体の存立を維持する権利(地方自治権)
②市有財産の財産権
口頭弁論では、国の代理人も異例の意見陳述に立ち、訴えを却下するよう主張した。
①’地方自治権は憲法が保障する自治体固有の権利ではない。
②’自治体の財産権は個人の財産権のようには保護されず、市には原告適格がない。
これに対して市の弁護団は、次のように反論する。この点が最初の争点になるだろう。
①''福島の事故では自治体の「生命」が失われており、存立権を実体ある権利として認めるべきだ。
②''改正原子炉等規制法には「国民の財産の権利」が明記され、市にも原告適格がある。
【注】「【原発】函館市の大間原発建設差し止め訴訟 ~自治体初~」
□小石勝(ジャーナリスト)「「大間原発の無期限凍結を」 函館市長が不信感表明」(「週刊金曜日」2014年7月18日号)
↓クリック、プリーズ。↓