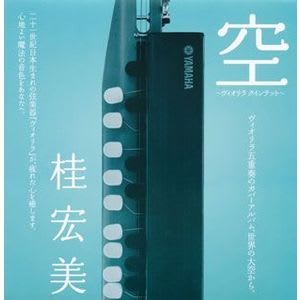高校3年、卒業間近の頃、A君が「将来、国連の職員になろうと思っているんだ。どう?」と聞いてきた。「とても良い志望だね!」と賛意を示したら満足そうに去っていった・・。同じクラスの生徒ではなかったので卒業後、交信はなくそのままだった。
最新発行の高校同窓会名簿で確認してみた。残念、「住所不明者」になっている。
『国連を問う』(川上洋一著、NHKブックス)を読みました。1993年発行の書ですが、当時すでに加盟国184カ国(現在193カ国)。内容的には、敵国条項なども変わっていないし今もそのまま通用することばかり。見方を換えればこれは20数年前と比べて国連の機能は余り進歩していないということにもなるのではないでしょうか。
United Nationsは直訳すれば「連合国」、中国語でも「聨合国」。日本の訳者が「国際連合」としたのは、実に美しい響きを与えた。私達の語感では「国際」に重きを感じ平和なイメージを持ちます。それはそれで良いのですが、いまだに憲章53条、107条の敵国条項は残ったまま。「敵国」は日本、ドイツ、イタリア、ハンガリア、ルーマニア、ブルガリア、フィンランド、いずれも第二次大戦の枢軸国だ。これも「拒否権」が邪魔をしている。憲章改正には常に5大国の同意が必要となっているからだ。
安保理常任理事国の拒否権は、伝家の宝刀。大国と大国の対立には国連は無力となる。「国連は人類を天国に行く機関でなく地獄に落ちるのを防ぐ機関」(ハマーショルド2代事務総長)
オランダ・ハーグに国際司法裁判所があるものの、ここでの判決に強制力はない。当事国が認めなければ、ハイそれまでヨ。
国連は人類の発明したもっとも弱い政治組織。主権はもちろんのこと立法、司法、行政、どれも懲罰の権限はない、と著者は嘆く。欠陥の多い脆弱な組織・・。かと言ってそれに代わる機関はなし。「されど国連」なのだ。
著者は学生時代に描いていた国連のイメージと、ニューヨークで取材して触れた現実の隔たりが執筆の動機としている。
本書で国連の理想と現実が良く理解できた。
高校時代のA君、もし国連の関係に勤めていたならどのような経験をされたか、ぜひ聞いてみたいものです。
 |
国連を問う (NHKブックス) |
| 川上洋一(朝日新聞前NY支局長) | |
| 日本放送出版協会 |
USA for Africa - We are the World