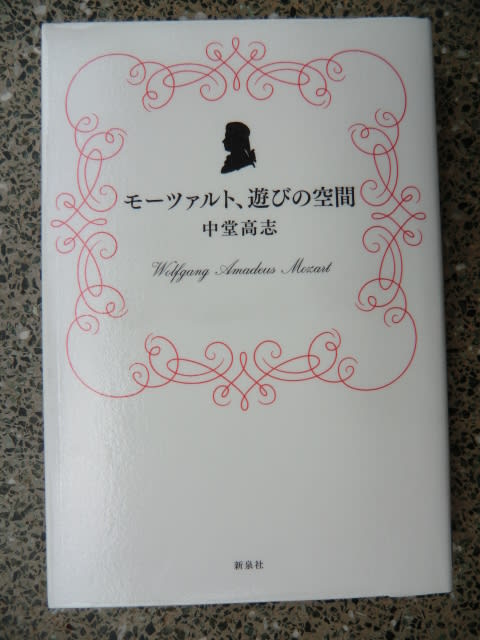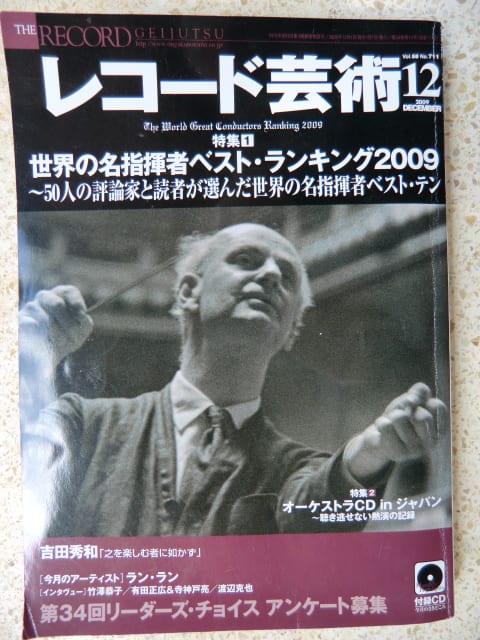前々回からの続きです。
わずかクルマで10分ほどの所にお住いの「Y」さんは我が家のオーディオのご意見番というか審判役としてとてもありがたい方である。
いつもお見えになるたびに何らかの収穫があるので「顧問料」を払いたくなるほどだ(笑)。
そして去る7日(土)は二つのテーマに絞っての試聴会だった。まずはこのほど我が家に戻ってきた「2A3シングル」アンプからいこう。
✰ 「2A3」シングルアンプ
テスト用のスピーカーはグッドマンのユニットを主体にした「3ウェイシステム」。目下の一番のお気に入りである。
ポイントは3種類の「6DE7」(前段管兼ドライバー管)のどれがスピーカーとの相性がいいかに尽きる。
画像のとおり試聴の順番は左から「レイセオン」「RCA」「NEC」に差し換えての試聴。
結果からいえばレイセオンがトップだった。
「音に艶があって音楽的な表現力がほかに比べて一枚上です。」
次が「NEC」で、「いかにも日本製らしい律儀さが伺えますが、レイセオンと比べるともう一つ積極的な表現力が欲しくなります。」
一番評価が低かったのは「RCA」で、「ネクタイをつけてかしこまった印象です。ちょっと溌溂とした元気が足りない印象を受けました」。
「出来るだけ生に近づいた音が好き」と仰るYさんならではの診断で、派手な音が嫌いでクラシック向きの音を好む方は「RCA」に肩入れされるかもしれないが、いずれにしろ「レイセオン」の優位性は動かないようだ。
こうなると「レイセオン」のスぺアが欲しくなりますなあ~(笑)。
一段落してから、実はと切り出した。
ここで前置きとして一言。
真空管アンプを大きく解剖すると「トランス類」(電源、出力、インターステージ)、次に「真空管」(前段管、出力管、整流管)、そして「その他」(回路、コンデンサー、抵抗、線材など)から構成されている。
音決めの重要度の比率から、あえて言わせてもらうと順番に「4:4:2」ぐらいかなと個人的には思っている。
何が言いたいかというと、縁の下の力持ち的な「トランス」類はとても大切な存在だということ。
「この図体の大きな出力トランスはタムラ製です。NHKで使われていたものだそうですが、アナウンサーの声が明瞭に聴こえるようにと、周波数帯域を欲張ることなくやや中音域に比重を置いたツクリになっている気がしますが、もっと高音域方向へのレンジが欲しい気もします。このトランスの感想はいかがですか?」
「これで十分じゃないでしょうか。高音域の抜けも不自然さはありませんよ。質のいいツィーター(ワーフェデールのスーパー3:4000ヘルツ以上)がカバーしている感じですが、私はトランスを交換する必要はないと思います。」
というわけで、何となくひと安心(笑)。
それにしても、いつも欠点をズバズバ指摘されるYさんから「合格」のお墨付きをもらったのだから「2A3シングル」アンプの優秀さが偲ばれる。
前段管とドライバー管を兼ねたユニークなテレビ管「6DE7」と古典管「2A3:刻印VISSEAUX(フランス製)」との相性もバッチリのようだ。
これで一件落着、メデタシ、メデタシ(笑)。
続いて
「AXIOM80」から新たな「変則3ウェイ」への所感について。

使用したアンプは我が家で一番広い周波数レンジを持つ「300Bシングル」アンプ。
「まるで鳥の羽毛のように中高音域が軽くなりましたね。周波数レンジが広がった印象です。以前よりも明らかにバランスが良くなり聴きやすくなりました」
グッドマンのスコーカー(口径10センチ)も、ジェンセンの「ツィーター」もいきなり出番がやってきてリリーフとして目を見張るような大活躍に恐れ入った。
どうやらこの分では「不動のレギュラー」になりそうですよ(笑)。
この内容に共感された方は励ましのクリックを →