中央銀行の超金融緩和が招く
2015年8月25日
1万8000円割れ。世界的株安という恐怖のどろ沼にまた、足を入れてしまったのでしょうか。政府、金融機関を含め関係者は、固唾を飲んで市場を凝視しています。バブル崩壊は震災の予知に似て、崩壊してみてからでないと、本当にバブル崩壊だったのかどうかが分らないところに難しさがあります。
アメリカのバーナンキ連邦準備制度理事会(中央銀行)議長でしたか、バブルが発生しているから、金融政策の舵取りを変えよ(もう引き締めせよ)の声に、「バブルは崩壊してみて始めて分る。中央銀行の役割は、崩壊してからの後始末(金融緩和策)にある」と居直りました。正直というか無責任というか。その後者でしょう。バブルを見破れず、政策当局が放置し、経済的惨事を招いたことが何度あったか、おびただしい数だったことを歴史が証明しています。
バブルの崩壊は地震津波に似る
バブルは大きな津波のようでもあります。船に乗って海上で揺られているときは、巨大な地震津波が発生していることに気づかず、海岸にたたきつけられ、船が破壊されて始めて「津波だったのだ」と、恐怖を意識します。中国バブルは明らかに崩壊しました。さらに日米欧を含めた全世界に怒涛のように波及していくのか。
バブルの崩壊時には次々に連鎖反応が起きます。「株の急落におののき、一斉に売りがでて、売りがでるから株はさらに下落する」、「資産価格の急落で、実際の景気、実体経済にマイナスの影響が生じる。それがまた株の続落を誘う」。悪循環です。今回もそうなるのかどうか。見極めるのに、もう少し時間がかかります。
過去の経験の反省こそ
はっきりしているのは、政府、中央銀行は安易な株下落対策をとってはならないことです。今朝の新聞をみますと、「政権に影響が懸念。政府、与党に景気テコ入れを求める声」という記事が早速、載っていました。「株高はアベノミクス(経済政策)を評価する指標」という関連記事を拝見しました。問題がある動きですね。
考えるべきことは、過去の経験への反省です。バブル崩壊に慌てふためき、過剰な金融緩和政策や財政刺激策をとってきたことが、結局、経済にとって弊害の方を大きくしました。その当座は景気対策につながっても、次にバブルが発生し崩壊する際には、市場に供給された過剰なマネー、財政赤字の拡大による過剰な国債が傷を深くするのです。
発行した国債の回収は無理
景気がよくなれば国債を回収できる、というのはウソでしょう。国債の発行額以上の税収が上がる時代ではもうありません。さらに、景気が好転し、ある程度、税収があがってきても、選挙に勝ちたい一心の政治家が歳出に回してしまいます。日本の場合、それが積もり積もって、先進国で最悪の財政状態(1000兆円の国家債務)になっているのです。政治家は真実を語るべきです。
金融緩和の罪も重いですね。米国はリーマンショック(国際金融危機、住宅バブル崩壊)対策で実施した超金融緩和のツケをいまだに回収できないでいます。「9月か秋にも金利引き上げ」という観測が、今回の中国バブルの崩壊で「先送りか」になっています。ぐずぐずしているうちに、次のバブル崩壊、株下落の局面にぶつかってしまい、打つべき手を打つ機会を失うのです。
「あれほど警告していたのに」
日本の場合は、「デフレ脱却のため」と称して、日銀が史上空前の規模で国債の大量購入を続けています。「早く出口戦略(金融緩和の停止、国債の売却)を」という声は、これでまたかき消されるでしょう。「日銀はもう国債の大量購入をやめられないだろう。止めた瞬間、市場は崩壊する」とみられています。「あれほど警告されていたではないか」と、安倍首相や黒田日銀総裁の責任が問われる日もくるでしょう。
延命策、救済策のつもりが、経済に重荷を背負わせだけになりかねません。次の延命策や救済策が必要なときに、その規模を大きくしなければならないからです。深みにはまっていくのです。
後戻りできない迷路か
日本ばかりでなく、世界共通の現象のようにも見えます。人類は後戻りできない迷路に迷い込んだのでしょうか。信じがたい規模の金融緩和と国債の大量発行という迷路です。抜けだすのは容易ではありません。このままでは破局を座視して、過去のツケを帳消しにするしか手がありません。目先の株価対策より、世界的な規模の過剰マネーの回収、民主主義の対価とされる国債発行の抑制への道のりを考えるべきでしょう。











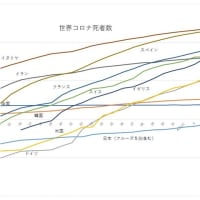









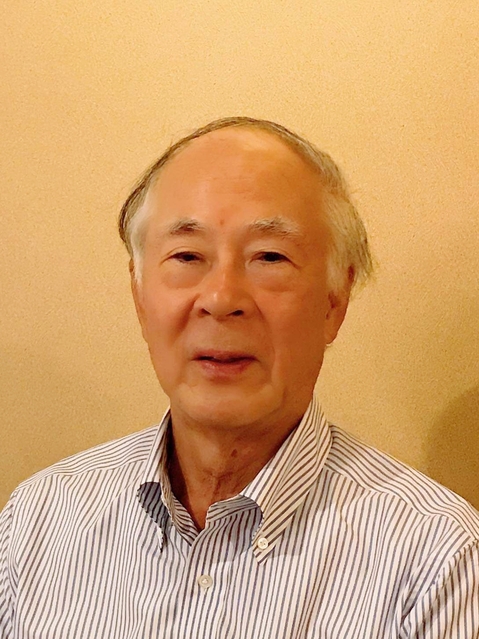

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます