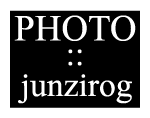かなり、いまさらになってしまいましたが、これは、書いておきたいと思っていたので、書かせていただきます。
仕事が忙しいのと、これ以前から残っていたネタを順次エントリーさせたので、この時期になりました。
こっそり待っていた方、すいません。
さて、本編の公演は、去る10月20日に開催。
翌21日には、モデレーターとして、浅田彰さんと、池田亮司さん本人とのアーティスト・トーク「datamatics をめぐって」が、同じ春秋座で行われました。
池田亮司氏については、ダムタイプ絡みで、以前から気になっていたアーティストであり、
2009年に、東京都現代美術館で行われた、「+/- [ the infinite between 0 and 1 ]」展を観たことがあります。
その際の感想は、↓こちらで書いています。
今回、特に、翌日に行われる、アーティスト・トークによって、より池田作品を理解できるのではないか?という想いもあり、2日連続の京都通いも、もろともせず、意欲的に通わせていただきました。
20日の本編では、
ステージ上に、4:3の比率ぐらいの大きなスクリーンだけがあり、そこに投影される映像と音楽を楽しむ、という形態の作品でした。
時間にして、約1時間ほど。
しかし、1時間とは思えない、内容の濃い時間を感じられ、音楽は心地良く、映像は見た目にも意味合い的にも奥行きを感じるもので、良い感じでした。
例えば、遠くから観ていると、テレビの砂嵐のような映像でも、近くで観ると、それはちゃんと意味を持った数字であったりと、無機質なものに見えながらも、実は、有機質なものであったりするわけです。
翌日のアーティスト・トークでは、普段、あまりお目にかかれない、「本人」も含め、
作品制作の元になるデータの一部(膨大な数のPDF)、制作工程の話などに加えて、今後の作品展開など、
いろいろな、こちらも内容の濃い話が続き、終わってみると、本編の公演時間より長い、1時間半でした。
しかしながら、池田さん本人は、どちらかと言えば、作品について、詳しく「語る」タイプの人ではなく、作品を観賞してくれた人が、作品自体を観賞したまま感じてもらい、観賞した人が良しとすれば良し、とする、
作品ですべてを伝えるのが基本的な考え方なので、今回のような機会は、かなり珍しかったのではないでしょうか?
ほとんど、浅田さんが話していた印象も強いですが、池田さんもちゃんと話されており、良いトークショーだったと思います。
このようなトークショーがうまい浅田さんならではといったところでしょうか。
どちらにしても、浅田さんをはじめ、企画・運営されたスタッフさん達に感謝です。
今後の作品展開のお話の中でも出ていた、新作のパフォーマンス作品「superposition」について、
今月中旬にも、フランスで公開されたようですが、日本では来年、今回と同じ京都芸術劇場・春秋座で公演予定であること、その新作について、池田作品では初めて、人がステージに上がる。ダムタイプ的なパフォーマンスになることが話され、さらに、池田さん本人より、「ダムタイプよりもカッコいい。」との発言が。
次作も大いに期待です。
関連リンク。--------
追記。--------
本題とは関係のない話ですが、浅田さんが、トークの流れで、話の例として挙げられた、先月発売された、坂本龍一の「THREE」について、「晩年のブラームス。」と評する発言がありました。
| Ryoji Ikeda: Datamatics | |
 | Kazunao Abe Maria Belen Saez de Ibarra Benjamin Weil Ryoji Ikeda Charta 2012-08-31売り上げランキング : 14328Amazonで詳しく見るby G-Tools |
TB。--------