京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸哉教授の講演を拝聴しました。若手研究者だった時代に、研究者の職を得るのにかなり苦労し、日本の大学に戻ってからは少ない研究資金で研究を続けることに苦しんだとの経験談を淡々と語りました。

山中さんは、日本人の中でノーベル賞の有力な候補者と考えられています。そして、再生治療(細胞移植治療)などの近未来の医学の実現を目指している点でも、多くの期待を受けている方です。山中さんは淡々と話しながら、真顔のままで意外と冗談を挟む人柄に親しみを覚えました。講演終了後に、名刺交換を希望する聴講者が列をつくっても、にこやかにいやがらずに名刺交換を続けている姿勢に、苦労人の横顔をみました。
山中さんは、12月6日夕方に科学技術振興機構(JST)の「世界を魅せる日本の課題解決型基礎研究」シンポジウムの招待講演「iPS細胞研究の進展」として講演されました。このシンポジウムの中心テーマは1年当たりに数億円という潤沢な研究開発費を得た有名な教授・研究者の研究開発実践論です。才気あふれる恵まれた方々の話で、大変面白かったです。これに対して、山中さんはiPS細胞を発見するまでは、かなり恵まれない境遇にいたことを淡々と語りました。山中さんの研究者としての苦労談を今回の講演で初めて知りました。
神戸大学医学部を卒業後に、国立大阪病院で臨床研修医を務めた際に「不器用なので手術の腕に自信が無くなり、研究者の道を選んだ」と語ります。大阪市立大学大学院の医学研究科博士課程を修了し、薬理学に魅せられて研究者として職探しをします。応募書類を送っても、臨床研修医から転身した分だけ研究者歴が短いために、断られ続けます。ある医学系学術誌に載っていたカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の グラッドストーン心血管研究所(Gladstone Institute)の研究員募集のお知らせに眼が留まり、駄目もとで応募します。1993年4月にグラッドストーン心血管研究所にポストドクトラルフェロー(いわゆる、ポスドク)として雇用され、プロの研究者としての第一歩を踏み出します。同研究所の米国人の“ボス”が多くの志願者の中から山中さんをなぜ選んだかは「今でも分からないが、研究戦略をしっかりと話したことが効いたと想像している」そうです。
グラッドストーン心血管研究所では「APOBEC1」遺伝子の作用効果を調べる研究テーマが与えられます。その実験には、遺伝子を改変した“トランスジェニュクマウス”を使いました。その後、日本に戻りたいと、研究者としての職探しを続け、1996年1月に 文部科学省系の日本学術振興会の特別研究員に採用され、月給約30万円の身分が与えられます。同年10月に大阪市立大学医学部助手に採用され、研究を続けます。この時に、年間100万円ぐらいの研究費しか獲得できず、「少ない研究費に苦労した」といいます。この時も、研究用にグラッドストーン心血管研究所が持ち帰ることを許可したトランスジェニュクマウスを利用します。お金が無いので100匹のマウスを自分で世話したそうです。これは大変苦労する作業です。
また、山中さんは「PAD」という病気にかかります。米国の恵まれた研究環境に比べて、日本の研究環境はあまりよくありません。PAD=Post American Depression 「米国帰りの憂鬱(ゆううつ)」というストレスに悩まされたそうです。「マウスを利用した研究内容は人間の病気を治す研究にはつながらない」と忠告してくれる研究者もいたそうです。1981年に英国でES(ヒト胚性幹細胞)細胞がつくり出され、1998年にES細胞が再生医療に使えるとの研究成果が発表され、山中さんはマウス利用の研究テーマを変えずに、「医学応用につながる研究テーマを考えて、研究上の悩みが解消した」といいます。
いろいろな大学の教員ポストに応募した結果、1999年12月に 奈良先端科学技術大学院大学の遺伝子教育研究センター助教授の職を獲得します。同大学院大学は、大学を持たないために、4月には他大学を卒業し入試に合格した大学院の修士1年生が入学してきます。入学した学生に自分の研究室に入ってもらうことが、教員としては重要なことになります。山中さんは、12月に移ってきたばかりで、学生に特にアピールする研究成果は特にありませんでした。
そこで、「ES細胞に必要な重要な遺伝子を見つける」という魅力ある研究テーマを考え、入学した大学院生に自分の研究テーマの面白さを訴えたそうです。

この結果、自分の研究室を持って初めての新学期に、3人の学生が山中研究室を志願してくれました。山中さんは「学生が来てくれて、正直ホッとした」そうです。その3人の中の一人だった高橋和利さんは、その後に山中研究室の助手になり、京大に一緒に移籍します。
その後、2007年11月に「ヒトの皮膚細胞からES細胞(胚性幹細胞)と遜色のない能力をもった人工多能性幹細胞(iPS細胞)の開発に成功しました」と発表します。

この画像は、多数のiPS細胞が集まってコロニーを形成しているものです。
「ヒトiPS細胞は患者自身の皮膚細胞から樹立できることから、脊髄損傷や若年型糖尿病など多くの疾患に対する細胞移植療法につながるものと期待されます」と、京大が発表し、山中さんはiPS細胞の研究開発に没頭します。
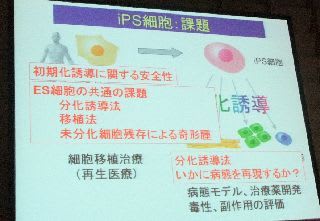
(やはり長くなったので、これ以降は明日にします)。

山中さんは、日本人の中でノーベル賞の有力な候補者と考えられています。そして、再生治療(細胞移植治療)などの近未来の医学の実現を目指している点でも、多くの期待を受けている方です。山中さんは淡々と話しながら、真顔のままで意外と冗談を挟む人柄に親しみを覚えました。講演終了後に、名刺交換を希望する聴講者が列をつくっても、にこやかにいやがらずに名刺交換を続けている姿勢に、苦労人の横顔をみました。
山中さんは、12月6日夕方に科学技術振興機構(JST)の「世界を魅せる日本の課題解決型基礎研究」シンポジウムの招待講演「iPS細胞研究の進展」として講演されました。このシンポジウムの中心テーマは1年当たりに数億円という潤沢な研究開発費を得た有名な教授・研究者の研究開発実践論です。才気あふれる恵まれた方々の話で、大変面白かったです。これに対して、山中さんはiPS細胞を発見するまでは、かなり恵まれない境遇にいたことを淡々と語りました。山中さんの研究者としての苦労談を今回の講演で初めて知りました。
神戸大学医学部を卒業後に、国立大阪病院で臨床研修医を務めた際に「不器用なので手術の腕に自信が無くなり、研究者の道を選んだ」と語ります。大阪市立大学大学院の医学研究科博士課程を修了し、薬理学に魅せられて研究者として職探しをします。応募書類を送っても、臨床研修医から転身した分だけ研究者歴が短いために、断られ続けます。ある医学系学術誌に載っていたカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の グラッドストーン心血管研究所(Gladstone Institute)の研究員募集のお知らせに眼が留まり、駄目もとで応募します。1993年4月にグラッドストーン心血管研究所にポストドクトラルフェロー(いわゆる、ポスドク)として雇用され、プロの研究者としての第一歩を踏み出します。同研究所の米国人の“ボス”が多くの志願者の中から山中さんをなぜ選んだかは「今でも分からないが、研究戦略をしっかりと話したことが効いたと想像している」そうです。
グラッドストーン心血管研究所では「APOBEC1」遺伝子の作用効果を調べる研究テーマが与えられます。その実験には、遺伝子を改変した“トランスジェニュクマウス”を使いました。その後、日本に戻りたいと、研究者としての職探しを続け、1996年1月に 文部科学省系の日本学術振興会の特別研究員に採用され、月給約30万円の身分が与えられます。同年10月に大阪市立大学医学部助手に採用され、研究を続けます。この時に、年間100万円ぐらいの研究費しか獲得できず、「少ない研究費に苦労した」といいます。この時も、研究用にグラッドストーン心血管研究所が持ち帰ることを許可したトランスジェニュクマウスを利用します。お金が無いので100匹のマウスを自分で世話したそうです。これは大変苦労する作業です。
また、山中さんは「PAD」という病気にかかります。米国の恵まれた研究環境に比べて、日本の研究環境はあまりよくありません。PAD=Post American Depression 「米国帰りの憂鬱(ゆううつ)」というストレスに悩まされたそうです。「マウスを利用した研究内容は人間の病気を治す研究にはつながらない」と忠告してくれる研究者もいたそうです。1981年に英国でES(ヒト胚性幹細胞)細胞がつくり出され、1998年にES細胞が再生医療に使えるとの研究成果が発表され、山中さんはマウス利用の研究テーマを変えずに、「医学応用につながる研究テーマを考えて、研究上の悩みが解消した」といいます。
いろいろな大学の教員ポストに応募した結果、1999年12月に 奈良先端科学技術大学院大学の遺伝子教育研究センター助教授の職を獲得します。同大学院大学は、大学を持たないために、4月には他大学を卒業し入試に合格した大学院の修士1年生が入学してきます。入学した学生に自分の研究室に入ってもらうことが、教員としては重要なことになります。山中さんは、12月に移ってきたばかりで、学生に特にアピールする研究成果は特にありませんでした。
そこで、「ES細胞に必要な重要な遺伝子を見つける」という魅力ある研究テーマを考え、入学した大学院生に自分の研究テーマの面白さを訴えたそうです。

この結果、自分の研究室を持って初めての新学期に、3人の学生が山中研究室を志願してくれました。山中さんは「学生が来てくれて、正直ホッとした」そうです。その3人の中の一人だった高橋和利さんは、その後に山中研究室の助手になり、京大に一緒に移籍します。
その後、2007年11月に「ヒトの皮膚細胞からES細胞(胚性幹細胞)と遜色のない能力をもった人工多能性幹細胞(iPS細胞)の開発に成功しました」と発表します。

この画像は、多数のiPS細胞が集まってコロニーを形成しているものです。
「ヒトiPS細胞は患者自身の皮膚細胞から樹立できることから、脊髄損傷や若年型糖尿病など多くの疾患に対する細胞移植療法につながるものと期待されます」と、京大が発表し、山中さんはiPS細胞の研究開発に没頭します。
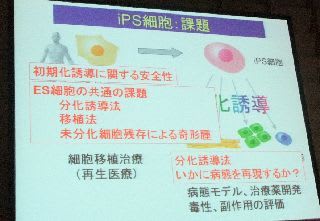
(やはり長くなったので、これ以降は明日にします)。









