東京農工大学の教員の方々が単行本「企業研究資金の獲得法」 を執筆されました。かなり刺激的なタイトルです。最近の大学教員が考えている素直な声をまとめた内容と思いました。本書は平成22年12月25日に丸善から発行されました。
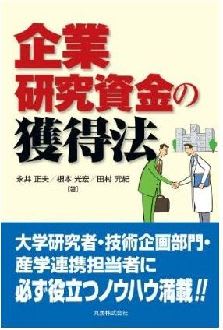
大学教員以外の方は、この単行本がどんな目的で発行されたのか、あまりよく分からないのではないかと思います。この本は、大学教員が自分が追究したい研究を行うために必要な研究資金を企業からどうやって獲得するかという、ある書のハウツー本です。しかし、単なるハウツー本ではありません。現在の大学がどんな状況に置かれていて、それを打開するにはどうすればいいのかまで書き込んだ本だと思います。
誤解してはいけないのは、「大学教員が企業に研究資金を求めるとは何事か、不謹慎である」と怒ってはいけないということです。一昔前の国立大学は研究室に配属される学生1人当たりに教育・研究費として100万円ぐらい配布されていました(と、指導教授から聞きました)。ところが、本書は「最近は中堅大学(地方大学)の各研究室は1年間当たり約20万円しか配布されない」と説明します。以前に比べてずいぶん減ったものです。これでは、研究用の試料も買えません。
本書は原則、中堅の国立大学(正確には、国立大学法人)を前提に話が展開されています。この前提条件で話を進めます。研究室に配布される教育・研究費が大幅に減った理由は、文部科学書が各国立大学法人に運営費用として配布する運営費交付金を2004年度以降、毎年1%ずつ減らしてきたからです。実際には、教員の方から「1年間に1%以上減らされている」という声をよく聞きます。この運営費交付金は、教員や事務員の給料などの人件費、学生を教育する諸経費、各研究室の研究費などに費やされます。大学を会社と考えると、毎年、事業経費が1%ずつ減らされていることになります。
本書がいう「各研究室は1年間当たり約20万円配布される」の中身は具体的にはよく分かりませんでした。ある教授から「最近の大学は設備やシステムなどの設備費がかなりかかる」と伺いました。校内のLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)やプリンター、プロジェクターなどの情報システム経費や冷房・暖房、電源代などの光熱費が予想以上にかかるようです。大学の各学科・各学部は、こうした共通設備費を負担した後に、各研究室に研究費を配布すると「学生1人当たり約20万円を配布する程度」と伺いました。本書が伝える「1研究室当たり20万円」は、こうした設備費などの必要経費を引いたものかどうか分かりません。しかし、どの教員・研究室も研究費不足に困っていることは事実です。
自分が所属する大学から配布される研究費が不足していては、各教員は研究ができません。このため、一般的には各教員は文部科学省系の日本学術振興会が提供する「科学研究費補助金」に応募します。選ばれると数100万円の研究費を獲得できます。この科学研究費補助金は有力大学の教員で確率的には数年に1回獲得できる程度です。このため、各教員は独創的、先駆的と思われる研究テーマを提案し続けます。さらに、優れた研究成果を上げた教員は競争的研究資金と呼ばれる大型の研究開発費に応募し続けます。文部科学省系の科学技術振興機構(JST)が提供する「戦略的創造研究推進事業」の「ERATO」「CREST」や経済産業省系の新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の各事業のものです。金額が大きいものは1件当たりに1年間に数億円が研究開発資金として提供されます。
現在、日本には大学教員と呼ばれる人が約18万人いるそうです(文科省の数字はこれよりやや少ないです)。教授や准教授、講師、助教と呼ばれる人です。最近は特任教授や特別研究員などと呼ばれる方も大学にはいます。必ずしも教員=研究者ではありませんが、大雑把にいって大学には10数万人の研究者がいるようです。このため、科学研究費補助金と各種の競争的研究資金が全員には行き渡りません。
ここまでがイントロです(長いイントロでした)。現在、大学には共同研究という制度があります。企業などの外部組織と研究内容を打ち合わせて研究するものです。文部省などの公的な研究資金ではなく、企業などから研究資金を出してもらって研究するものです。よく「大学が企業の下請けになって研究するとは」という批判が出ます。企業の研究提案内容に従って、その作業を受け持つのであれば、確かに下請けです。しかし、多くの大学教員は企業からの研究内容に相談に対して、研究内容は教員が提案し、研究計画を立てます。つまり、解決してもらいたい問題に対して、その解決法は教員が考え出し、実行します。この場合は下請けではなく、問題を解決する支援者です。必要な経費を受け取って、研究するだけです。大学教員は世の中にどんな問題があるかは分からないことが多いのです。「こんな解決困難な問題があるのですが、その解決法を教えてほしい」との企業のニーズに応えるのが真の共同研究です。
本書によると、大学の共同研究費は平均220万円です。平成21年度は共同研究費が1件当たり1年間分で1000万円以上のものは695件ありましたが、共同研究件数の50%近くが同100万円未満だったそうです。共同研究費が100万以下の場合は、一般的には多くが試料代などに費やされ、その研究にかかった人件費などは事実上ゼロとなります。教員自身が研究の実験作業を請け負うことは少なく、学生に頼むケースが多いために、人件費ゼロでも成立すると推定されます。その教員の研究室などが持つ研究施設や装置を使って高度な研究ができるケースが多く、企業側からみれば、そうした施設・装置を自分で用意しない済みます。結果的に安上がりになります。共同研究を引き受ける教員としてみれば、社会の実際のニーズが分かる点で、企業との共同研究は歓迎なのかもしれません。
ただし、平均220万円の共同研究費は、本書の第1章によると平成20年度の共同研究費の大学別では、東京大学が518万円、京都大学が476万円、大阪大学が370万円と平均値を超す有名大学があり、国立大学の格差もかなりありそうです。こうした有名大学に1000万円以上の共同研究が集中しているようです。
(長くなりましたので、続きは明日に)
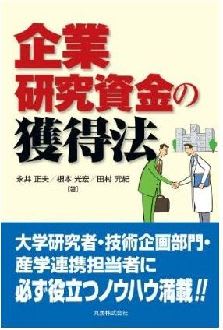
大学教員以外の方は、この単行本がどんな目的で発行されたのか、あまりよく分からないのではないかと思います。この本は、大学教員が自分が追究したい研究を行うために必要な研究資金を企業からどうやって獲得するかという、ある書のハウツー本です。しかし、単なるハウツー本ではありません。現在の大学がどんな状況に置かれていて、それを打開するにはどうすればいいのかまで書き込んだ本だと思います。
誤解してはいけないのは、「大学教員が企業に研究資金を求めるとは何事か、不謹慎である」と怒ってはいけないということです。一昔前の国立大学は研究室に配属される学生1人当たりに教育・研究費として100万円ぐらい配布されていました(と、指導教授から聞きました)。ところが、本書は「最近は中堅大学(地方大学)の各研究室は1年間当たり約20万円しか配布されない」と説明します。以前に比べてずいぶん減ったものです。これでは、研究用の試料も買えません。
本書は原則、中堅の国立大学(正確には、国立大学法人)を前提に話が展開されています。この前提条件で話を進めます。研究室に配布される教育・研究費が大幅に減った理由は、文部科学書が各国立大学法人に運営費用として配布する運営費交付金を2004年度以降、毎年1%ずつ減らしてきたからです。実際には、教員の方から「1年間に1%以上減らされている」という声をよく聞きます。この運営費交付金は、教員や事務員の給料などの人件費、学生を教育する諸経費、各研究室の研究費などに費やされます。大学を会社と考えると、毎年、事業経費が1%ずつ減らされていることになります。
本書がいう「各研究室は1年間当たり約20万円配布される」の中身は具体的にはよく分かりませんでした。ある教授から「最近の大学は設備やシステムなどの設備費がかなりかかる」と伺いました。校内のLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)やプリンター、プロジェクターなどの情報システム経費や冷房・暖房、電源代などの光熱費が予想以上にかかるようです。大学の各学科・各学部は、こうした共通設備費を負担した後に、各研究室に研究費を配布すると「学生1人当たり約20万円を配布する程度」と伺いました。本書が伝える「1研究室当たり20万円」は、こうした設備費などの必要経費を引いたものかどうか分かりません。しかし、どの教員・研究室も研究費不足に困っていることは事実です。
自分が所属する大学から配布される研究費が不足していては、各教員は研究ができません。このため、一般的には各教員は文部科学省系の日本学術振興会が提供する「科学研究費補助金」に応募します。選ばれると数100万円の研究費を獲得できます。この科学研究費補助金は有力大学の教員で確率的には数年に1回獲得できる程度です。このため、各教員は独創的、先駆的と思われる研究テーマを提案し続けます。さらに、優れた研究成果を上げた教員は競争的研究資金と呼ばれる大型の研究開発費に応募し続けます。文部科学省系の科学技術振興機構(JST)が提供する「戦略的創造研究推進事業」の「ERATO」「CREST」や経済産業省系の新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の各事業のものです。金額が大きいものは1件当たりに1年間に数億円が研究開発資金として提供されます。
現在、日本には大学教員と呼ばれる人が約18万人いるそうです(文科省の数字はこれよりやや少ないです)。教授や准教授、講師、助教と呼ばれる人です。最近は特任教授や特別研究員などと呼ばれる方も大学にはいます。必ずしも教員=研究者ではありませんが、大雑把にいって大学には10数万人の研究者がいるようです。このため、科学研究費補助金と各種の競争的研究資金が全員には行き渡りません。
ここまでがイントロです(長いイントロでした)。現在、大学には共同研究という制度があります。企業などの外部組織と研究内容を打ち合わせて研究するものです。文部省などの公的な研究資金ではなく、企業などから研究資金を出してもらって研究するものです。よく「大学が企業の下請けになって研究するとは」という批判が出ます。企業の研究提案内容に従って、その作業を受け持つのであれば、確かに下請けです。しかし、多くの大学教員は企業からの研究内容に相談に対して、研究内容は教員が提案し、研究計画を立てます。つまり、解決してもらいたい問題に対して、その解決法は教員が考え出し、実行します。この場合は下請けではなく、問題を解決する支援者です。必要な経費を受け取って、研究するだけです。大学教員は世の中にどんな問題があるかは分からないことが多いのです。「こんな解決困難な問題があるのですが、その解決法を教えてほしい」との企業のニーズに応えるのが真の共同研究です。
本書によると、大学の共同研究費は平均220万円です。平成21年度は共同研究費が1件当たり1年間分で1000万円以上のものは695件ありましたが、共同研究件数の50%近くが同100万円未満だったそうです。共同研究費が100万以下の場合は、一般的には多くが試料代などに費やされ、その研究にかかった人件費などは事実上ゼロとなります。教員自身が研究の実験作業を請け負うことは少なく、学生に頼むケースが多いために、人件費ゼロでも成立すると推定されます。その教員の研究室などが持つ研究施設や装置を使って高度な研究ができるケースが多く、企業側からみれば、そうした施設・装置を自分で用意しない済みます。結果的に安上がりになります。共同研究を引き受ける教員としてみれば、社会の実際のニーズが分かる点で、企業との共同研究は歓迎なのかもしれません。
ただし、平均220万円の共同研究費は、本書の第1章によると平成20年度の共同研究費の大学別では、東京大学が518万円、京都大学が476万円、大阪大学が370万円と平均値を超す有名大学があり、国立大学の格差もかなりありそうです。こうした有名大学に1000万円以上の共同研究が集中しているようです。
(長くなりましたので、続きは明日に)









