2013年11月4日号の日経ビジネス誌は、特集「会社の寿命 老化を防ぐ3つの処方箋」を載せています。
30年前に、日経ビジネス誌の1983年9月19日号は特集「会社の寿命は30年」を掲載し、企業が繁栄を謳歌できる期間はわずか30年と主張し、「会社の寿命は30年」説が話題になりました。それから30年経ち、会社の事業が高収益を出すのが短命化しているという通説を実証するために、今回の特集特集「会社の寿命」が企画されたそうです。
今回の「会社の寿命 老化を防ぐ3つの処方箋」では、「もはや寿命は18年」と、企業が繁栄を享受できる期間の短命化を示しています。
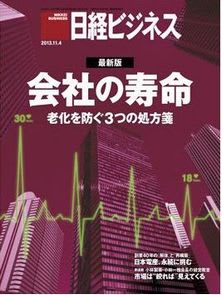
同誌は、企業が繁栄する期間を計る手法として、1890年以降の各企業の売上高と総資産額から、繁栄している企業100社のランキングを作成し、そのランキングに入ってから圏外に去るまでの平均滞在期間を調べるやり方をとったそうです。この上位100社ランキングにランクインしてから去るまでの期間を、企業が「繁栄できる期間」と定義したそうです。
この手法では、今回の最新の「会社の寿命」は約27年との結論になったそうです。30年前の“会社の寿命30年”に比べると、確かに約3年短くなっています。しかし、最近の日本の電機大手企業の事業不振を考えと、「3年しか短くなっていないのか」というのが素直な感想です。
さらに、今回の特集では各企業の売上高と総資産額のランキングとは別に、時価総額の企業ランキングを作成し、企業の繁栄期間を割り出してみたそうです。
その結果が「日本企業が輝いている期間は18.07年」との結論になりました。
日本でもIT(情報技術)事業の会社は“ドッグイヤー”と、従来の1年間は、IT分野では7年に相当し、技術革新などが7倍速く進むといわれてきました。
IT分野以外の日本企業も、家電製品などのコモディティー化によって付加価値が下がり、事業収益を大幅に落とした家電分野の電機企業、同時にIT分野の技術進化の速さによって製品の短命化にあえいだ半導体事業の電機企業も重なります。
日本のデフレ不況が続いて低価格競争にあえいできた小売り事業の企業、公共事業費の削減にあえいだ建設・土木企業などと、事業不振にあえいだ企業が続きます。
こうした実情を考えると、「日本企業が輝いている期間は約18年」説は納得感があります。今回の特集は、何となく感じていたことを、実データを基に、数値化してくれた点に意味があります。
同特集はさらに、帝国データバンクの協力の下で、企業が創業してから倒産するまでの厳密な意味での“企業の存続期間”も試算した結果が載っています。
この試算結果は、「2003年の日本企業の平均寿命は31.6歳、2013年の同平均寿命は34.9歳」と、平均寿命が伸びていることが示されています。
この試算結果をそのまま受け入れて、その中身を考えると「日本企業の中には本来ならば市場から退場を余儀なくされるゾンビ企業が存命し、日本企業の新陳代謝が進んでいない」という恐い見方が浮かび上がります。これはこれで、恐いことです。
30年前に、日経ビジネス誌の1983年9月19日号は特集「会社の寿命は30年」を掲載し、企業が繁栄を謳歌できる期間はわずか30年と主張し、「会社の寿命は30年」説が話題になりました。それから30年経ち、会社の事業が高収益を出すのが短命化しているという通説を実証するために、今回の特集特集「会社の寿命」が企画されたそうです。
今回の「会社の寿命 老化を防ぐ3つの処方箋」では、「もはや寿命は18年」と、企業が繁栄を享受できる期間の短命化を示しています。
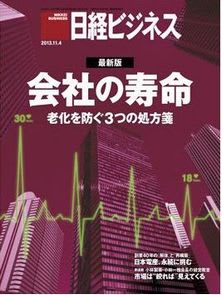
同誌は、企業が繁栄する期間を計る手法として、1890年以降の各企業の売上高と総資産額から、繁栄している企業100社のランキングを作成し、そのランキングに入ってから圏外に去るまでの平均滞在期間を調べるやり方をとったそうです。この上位100社ランキングにランクインしてから去るまでの期間を、企業が「繁栄できる期間」と定義したそうです。
この手法では、今回の最新の「会社の寿命」は約27年との結論になったそうです。30年前の“会社の寿命30年”に比べると、確かに約3年短くなっています。しかし、最近の日本の電機大手企業の事業不振を考えと、「3年しか短くなっていないのか」というのが素直な感想です。
さらに、今回の特集では各企業の売上高と総資産額のランキングとは別に、時価総額の企業ランキングを作成し、企業の繁栄期間を割り出してみたそうです。
その結果が「日本企業が輝いている期間は18.07年」との結論になりました。
日本でもIT(情報技術)事業の会社は“ドッグイヤー”と、従来の1年間は、IT分野では7年に相当し、技術革新などが7倍速く進むといわれてきました。
IT分野以外の日本企業も、家電製品などのコモディティー化によって付加価値が下がり、事業収益を大幅に落とした家電分野の電機企業、同時にIT分野の技術進化の速さによって製品の短命化にあえいだ半導体事業の電機企業も重なります。
日本のデフレ不況が続いて低価格競争にあえいできた小売り事業の企業、公共事業費の削減にあえいだ建設・土木企業などと、事業不振にあえいだ企業が続きます。
こうした実情を考えると、「日本企業が輝いている期間は約18年」説は納得感があります。今回の特集は、何となく感じていたことを、実データを基に、数値化してくれた点に意味があります。
同特集はさらに、帝国データバンクの協力の下で、企業が創業してから倒産するまでの厳密な意味での“企業の存続期間”も試算した結果が載っています。
この試算結果は、「2003年の日本企業の平均寿命は31.6歳、2013年の同平均寿命は34.9歳」と、平均寿命が伸びていることが示されています。
この試算結果をそのまま受け入れて、その中身を考えると「日本企業の中には本来ならば市場から退場を余儀なくされるゾンビ企業が存命し、日本企業の新陳代謝が進んでいない」という恐い見方が浮かび上がります。これはこれで、恐いことです。









