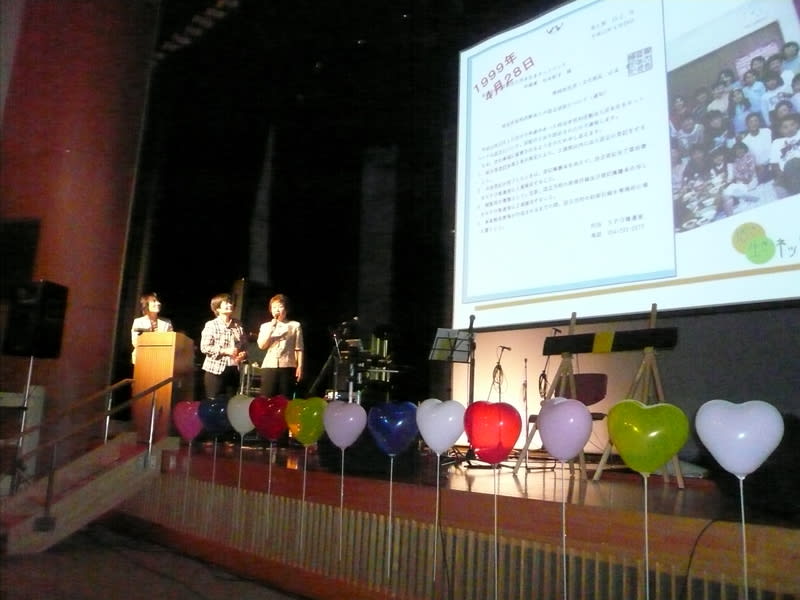今日はお昼にNPO法人活き生きネットワーク理事長の杉本彰子さんを、岡部町のごはん処・ゆとり庵にご案内しました。いただいたのは、森町の究極のコシヒカリ新米。4年前の浜名湖花博の地酒テイスティングサロンで、かの料亭青柳の小山料理長とコラボしたとき、静岡一うまい米を用意してほしいと頼まれ、手を尽くして取り寄せたのが、このコシヒカリでした。新米が出回るひと月足らずで売り切れてしまい、私も実際いただくのは4年ぶり。プロのごはん炊き職人の手によってツヤツヤと炊き上がった新米は、口中でほんのり甘味が広がり、適度な粘り気もあって、おかずや箸休めもまったく要らないほど。彰子さんは2膳、私は3膳、夢中でおかわりしてしまいました。肝炎治療中の彰子さんは「ごはんをおかわりするのは何年ぶりかな」と自身の食欲にビックリしていました。
夜は、店頭で売っていた塩むすび3種(静岡産なつしずか、磐田産こしひかり、会津産こしひかり)の食べ比べをし、品種の違い、産地の違いが、塩だけで食べることでさらに顕在化することを実感。おいしく炊けた米は冷めてもうまいことも、よ~く解りました。「米だけでも、これだけ奥が深いんだものね、真弓ちゃんが酒にこだわる気持ちもよく解るわ」と彰子さん。
彰子さんをごはんランチにお誘いしたのは、活き生きネットワークが運営するケアハウス「喜楽庭」で、障害を持つ通所者の方に仕事の機会を与えたいと、かねてからおにぎりかお弁当の製造販売を考えていたから。NPOの収益事業、とりわけ飲食の商売は難しい面も多いようですが、どうせやるなら、働く人々が自信と誇りが持てるようなものを作ってほしい・・・そんな思いからでした。
プロが厳選した米を釜で炊き上げるゆとり庵と同じレベルの商売は、もちろん不可能です。それでも「まずは高齢者さんや障害者さんに食べさせてあげたいわ!」とお土産に何パックも買い求める彰子さんを見ていたら、いいモノ、おいしいモノを観て味わって心がはずむ・・・そんな体験が、人が生きていくにはホントに大切だなって思いました。商売につなげるにしても、作り手自身がいいモノの価値を実感して、「自分も作ってみたい、お客さんを喜ばせたい」という気持ちになることが出発点じゃないかと。
ここ数日、テレビで北京パラリンピックを観ながら、オリンピック以上に感動してウルウルしています。高い目標を目指し、自らの限界に挑む彼らは、健常者と何ら変わりのない一流のアスリートであり、健常者の指導経験のあるコーチが手を抜かず、トコトン指導しています。活き生きでも、挑戦するなら高い目標を持って、ホントにおいしいもの、長続きするものに取り組んでほしいと思います。
さて、過去ブログでも紹介したとおり、来週27日(土)から11月3日(月・祝)までの約1ヵ月間、島田市お茶の郷博物館で、松井妙子先生の染色画展が始まります。染色作家生活32年の中から、厳選した40点が再結集。松井先生の分身ともいえるフクロウ、カワセミ、魚などをモチーフに、自然や生き物や故郷への賛歌を温かく謳い上げる作品ばかりです。
松井先生は、27日(土)、10月5日(日)、11日(土)、19日(日)、25日(土)、11月2日(日)、3日(月・祝)に会場へいらっしゃる予定です。先生とお話ししながら作品を眺めていると、大袈裟でなく、ホントに心が浄化される思いがします。ぜひ足をお運びください。