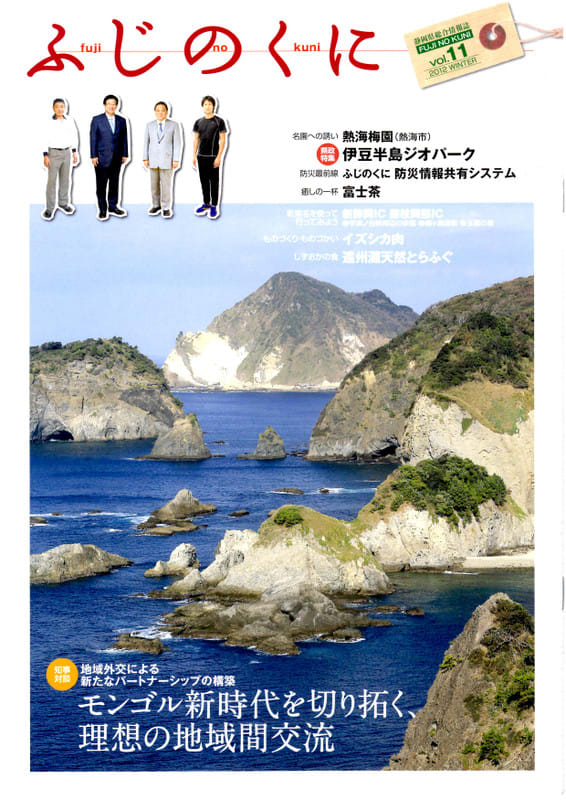このところ読書熱に冒されています。AmazonのKindle paperwhite をようやく使いこなせるようになって、一気に10冊購読・読破しました。10冊分を持ち歩くことを想像したら、200g程
度のタブレットに収まるってやっぱり便利です。
部屋の本棚もすでに容量オーバーで、どれをブックオフしようか迷っている状態ですから、今後は、電子書籍化された本はKindle で読むようにしていこうかな。それに、紙の本もそうだけど、Amazonの良さって、購入した本の著者や同ジャンルの関連本を自動的におすすめリスト表示してくれる点。これでずいぶん本選びの幅が広がり、また深まっていく感じがします。
とはいえ、物書きを生業にしている身、外出時に本屋さんで過ごす時間は、他の場所では得られない宝物のような時間です。
先日も、セノバで映画を見ようとして上映終了時間を確認したら、仕事の打ち合わせに間に合わないと判って観るのをあきらめ、立ち寄った5階の丸善で、『酒をやめずにやせる技術』(木下雅雄著・扶桑社新刊)、『山田錦物語~人と風土が育てた日本一の酒米』(兵庫酒米研究グループ編著・神戸新聞総合出版センター刊)を偶然見つけてゲット。2階にあるカフェで読んでいるうちに、映画2本分の満足感が得られました。Amazonは、関連本をより奥深く発掘できるけど、本屋さんでは偶然の出会いが愉しめますね!
よくカフェで受験勉強する学生の“長居”が可か不可かって話を聞きますが、正直な話、カフェや電車内のように適度に喧騒のある場所って、ものすごく自分の世界に集中しやすいんですね。読書も、自宅よりはるかに、はかどります。
願わくば、自宅では得られないゆったり、ぜいたくな読書タイムが満喫できるよう、コーヒーはマシンではなくハンドドリップでていねいに淹れてほしいし、イスやテーブルの配置も、独り客がくつろげるようなレイアウトにしてほしいな。音楽は耳に心地のよいクラシックかジャズで。
昔はそんな、読書におあつらえ向きの珈琲専門店が街中にいくつもあったけど、今は味気ないチェーン店の味気ないマシンコーヒーばっかりになっちゃいましたね・・・。セノバの2階にあるカフェも、せっかく「くれあーる」さんの特選珈琲豆使用って謳っているのにマシンで淹れてあるからイマイチ。これで一杯600円ってどうなんだろう・・・。家でも「くれあーる」のコーヒーを飲んでいるけど、やっぱり自分でひきたてをハンドドリップするほうが美味い。
これだけ通販が発達すると、わざわざ店でモノを買う、時間を買うという行為には、目的以上のプラスαの満足感がなければ、リピーターにはなりにくい・・・つくづくそう思います。
さて、今、Kindle でハマっているのが、高橋昌一郎さんの『理性の限界』『知性の限界』『感性の限界』シリーズ。小難しい論理哲学を、架空のパネルディスカッション仕立てで、学生や一般市民が専門家とディベートしながら解説してくれるんです。
たとえば「ゲーテルの不完全性定理」の解説では、こういう例題が。
ナイト(正直者)とネイプ(嘘つき)の2種類の住人しか住んでいない島がある。島民Xが「自分はネイプです」と言ったとすると、Xは、はたしてナイトかネイプか?
Xがナイトなら、嘘をつくはずがないから、ネイプだろうし、Xがネイプなら、正直に言うはずがないから、ナイトということになります。つまり、この島の住民は、真実と嘘しか発言しないのに、「自分はネイプです」という発言は存在できない。「自分はナイトではない」「自分は嘘つきです」という発言も存在しない。一般市民が「なら、いったい何を基準に真偽を定めるのか」と疑問を呈する。そこから、「命題論理」とか「ペアノの自然数論」の話に展開していきます。途中で何度も挫折しそうになるけど(苦笑)。
別の例題では、大学教授の掲示板に次のような告知が。
「月曜日から金曜日のいずれかの日にテストを行う」
「どの日にテストを行うかは、当日にならなければわからない」
これを見た学生Aは、いつ、ぬきうちテストがあるかわからないから、毎日勉強しなきゃ、と考えた。一方、学生Bは「もし月~木曜までに行われなければ、金曜に行うはずだが、“当日にならなければわからない”という条件に反するから、金曜にテストはない。月~水曜までに行わなければ木曜に行うはずだが、同様の理由で木曜にもない。で、月・火に行わなければ水曜となるが、同様にテストは不可能。結局テストは行われない」と判断した。
ところが教授は金曜日にテストを行った。反発した学生Bに、教授は「君が、今日はテストがないと思っていたなら、ぬきうちテストは成立するだろう」と応えた。
すると別の学生Cが「私はそう先生が答えると思って準備をしてきた」といい、教授は「だったら私が嘘つきになってしまうから、テストはやめよう」と言い、また別の学生Dは「僕は先生がそう応えると思ったから準備はしていない」と言い、教授は「だったらテストをやろう」と・・・。この会話は延々と続いて結論が出ません。
ここで「おおーっ」と思ったのは、この無限循環論が、ノイマンとモルゲルシュテルンの『ゲーム理論と経済活動』という論文で取り上げた、シャーロック・ホームズとモリアーティー教授が対決した「最後の事件」と同じ構造だったこと。まさか、ついこないだまで夢中になって読んでいたホームズ本がここでリンクするとは・・・。
「最後の事件」では、ホームズが犯罪王モリアーティの魔手から逃げようと、ロンドンのビクトリア駅から大陸連絡急行列車に乗ります。停車駅はカンタベリーとドーバーだけ。当初、ホームズはドーバーで下車して船でヨーロッパ大陸へ渡る予定でしたが、追いかけてくるモリアーティーにとっては“想定内”です。ならばその裏をかこうと、ホームズはカンタベリーで途中下車し、難を逃れた。小説ではそうですね。しかし、もし、モリアーティーがさらに上手で、ホームズがカンタベリーで途中下車することを見越していたら、彼も降りて追いつくはず。しかししかし、ホームズがさらにもう一回り裏をかき、ドーバーまで行ったとしたら、大陸へ無事渡れる。ところが、モリアーティーがそのことも見抜いていたら・・・、堂々巡りが永遠続きます。
ゲーム理論は、プレーヤー双方の利得が相殺されてゼロになる「ゼロサムゲーム」を取り扱っています。このゲームで最も合理的な戦略は、「ミニマックス作戦」。つまり、自分の損失を最小限におさめる=勝とうとするよりも負けない戦略、だそうです。
この戦略を発展させたのが、「ナッシュ均衡」。一方のプレーヤーが最適な戦略をとったとき、他方のプレーヤーもそれに対応する戦略があることを証明したんですね。ちなみにジョン・ナッシュは数学者として初のノーベル経済学賞を受賞した人で、映画『ビューティフル・マインド』でラッセル・クロウが演じました。「ナッシュ均衡」、私のレベルでは解説不可能なので、興味があったらこちらを。
ぬきうちテストの話に戻ると、もし、最初に「教授は嘘をついた」と責めた学生Bに、教授が「だったら私の嘘を信じた君は正気者か?」と問えば、Bは自分に自信がなくなってしまいます。かりに、Bが「教授は嘘つきだ」と信じるとすると、教授の発言の否定(・・・つまりテストを行う)を信じることになる。『自分は嘘つき」という発言は、どう転んでもパラドックスを生じさせてしまうわけです。
学生Bは論理的に解釈しようとして、ぬきうちテストの罠、つまり不完全性定理に陥ってしまいましたが、一方、教授の発言を深く考えず、真面目にテスト勉強をしていた学生Aのほうが、結果的に賢かったということになります。最も非合理的な戦略が、実は最も合理的な戦略になっているってことですね。対戦型ゲームやドラマのネタによく出てきそうです。
もし「ゲーテルの不完全性定理」「ナッシュ均衡」なんてキーワードが全面に出ていたら、絶対に触手しなかった本ですが、パネルディスカッション風の対話形式で、しかも、シャーロック・ホームズやビューティフル・マインド等、一般の人に馴染んでいる大衆カルチャーを上手に取り入れて解説してくれる。この体裁自体、大変参考になりました。言葉の理解には限界があるという内容だけに、ライターという仕事の存在意義を考える、よい機会にもなっています。
それにしても、脳と視力が疲弊する読書タイム、やっぱり、美味しいコーヒーと心地よい音楽が欲しいですね。ついでにクイックマッサージとか占いなんかのコーナーが併設されていたら、リピーターになるんだけどなあ・・・。ようするに、通販で済ませないで店まで出向くっていうのは、人の手間がちゃんとかかっているサービスを求めるってことだと思います。あくまで個人的意見ですが。