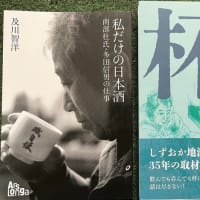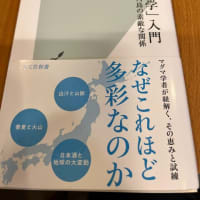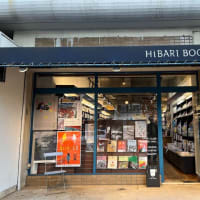報告が遅れましたが、昨年末、JA静岡経済連発行の情報誌『スマイル』48号が発行されました。今回はバラとトルコギキョウの特集です。

中でも書き応えがあったのが、専門家に聞く【スマイルマイスター】のコーナー。元静岡県農業試験場で花卉栽培技術のスペシャリストとして活躍された、水戸喜平さんの解説です。酒の世界でいう、河村傳兵衛先生みたいな方ですね。
専門的な内容で難しくて、何度も校正をお願いした労作ですが、それだけに、書いた内容がしっかりアタマに入り、いい勉強になりました。
静岡県がなぜバラの有数産地になったのか、今、市場でひっぱりだこという静岡県産トルコギキョウの人気の秘密などを、できるだけ簡易な言葉でまとめてみました。ぜひご一読ください。
なお、スマイル本誌は、JA各支店やファーマーズマーケットで無料配布中です。見つけたらぜひお持ち帰りください。バラやトルコギキョウの花束があたるクイズコーナーもありますよ!
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
海の向こうからやってきた花を日本に根付かせた<o:p></o:p>
静岡県のバラとトルコギキョウ栽培<o:p></o:p>
花の女王・バラと、これに迫る人気のトルコギキョウ。静岡県はともに日本屈指の栽培技術と生産量を誇る花の主産地です。今回は県の花卉栽培における技術普及にかかわった水戸喜平さんに、両品目の栽培の歩みを振り返って解説してもらいます。<o:p></o:p>
解説/水戸喜平さん(元静岡県農業試験場花卉専門技術員)
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
バラ<o:p></o:p>
日本のバラ栽培は、明治維新後に西洋文明が入ってきたとき、富裕層を中心に観賞用のガーデンローズとして東京・横浜一帯から始まり、温暖な栽培適地・千葉県房総半島や静岡県伊豆半島あたりに広まりました。県内では趣味の園芸家からブームに火が付き、大正時代に本格的な露地切花栽培がスタート。戦前・昭和初期には国内のバラ切花生産の3分の1を占めるまでになります。当時の主産地は静岡市の谷津山周辺・長沼~瓦場一帯。中でも曲金の小林鑑一氏は関東大震災の年(大正12年)、神奈川県でバラの温室栽培技術を習得し、静岡市の切花バラ生産の先駆者となりました。<o:p></o:p>
戦後は伊豆、庵原、駒越(三保)、島田、浜松はじめ県内全域で切花バラ栽培が始まります。私は昭和41年から農業試験場(現県農林技術研究所)で花卉の栽培技術研究に携わってきました。折からの高度経済成長期、暮らしの洋風化とともにギフトやブライダル市場から洋花の需要が高まり、日本的なキクから、カーネーションやバラ等が主役に躍り出た時代です。清水庵原地区のみかん産地では、みかんの幼木が成木になるまでの約10年間、畝間にバラを植える生産者もいました。彼らはその後、みかんからバラへと本格的に切り替え、生産者が増え、全国有数の産地になっていきました。<o:p></o:p>

昭和40年代は農業政策と工業技術の発展によって大型のビニールハウスによる周年栽培が進みました。掛川では早くから個々の生産者が団結して温室生産団地を形成し、果樹の共同選果場や野菜の共同出荷場にならってバラ専門の共選・共販体制を整えました。<o:p></o:p>
平成に入ると、品種の需要も多様化します。高度経済成長期やバブル景気の時代は、ブライダルやイベント等の大口需要に影響されてきたのが、少しずつ小口の家庭消費も増加し、バラなら何でもよいという時代ではなくなりました。各産地はJAがマーケティングを担当し、消費者ニーズに合った品種を検討し、共販体制で特色ある産地形成に努めました。<o:p></o:p>
バラは、日本ばら切花協会という生産者の全国組織を持ち、生産者間の情報交換や技術研鑽が活発です。「日ばら協会」は静岡県が発祥地で、全国会員はピーク時、1500人を超え、現在は半減していますが、それでも静岡県の会員数は他県に比べれば突出しています。<o:p></o:p>
長年培ってきた栽培技術と“信頼される産地化”への取り組みは、時代が変わろうとゆるぎないと思っています。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
トルコギキョウ<o:p></o:p>

トルコギキョウは北米ロッキー山脈南部の草原が原産です。日本には昭和初期にアメリカから伝わりました。<o:p></o:p>
トルコギキョウという名前は、ふっくらした花の形がトルコ人のターバンに似ている、イスラムのモスクに似ている、紫の花の色がトルコ石やキキョウに似ている等と諸説ありますが、キキョウではなく、リンドウ科ユーストマ属の花。欧米では学名のユーストマ、旧名のリシアンサスが一般的な呼び名です。<o:p></o:p>
欧米では品種改良が進まなかったトルコギキョウは、日本の育種栽培技術によって復活します。当初は紫色の品種しかなかったものを、昭和40年代あたりから静岡県磐田市の鈴木政一さんをはじめ、長野県、千葉県等の生産者の育種によって改良が進み、種苗会社も参戦して短期間に数多くの優秀なF1(雑種強勢)品種が誕生しました。<o:p></o:p>
県内では昭和60年以降、静岡大学農学部の大川清教授が提唱した低温育苗技術と県農業試験場(当時)、農林大学校、花卉園芸組合連合会(通称・花卉連)の研究会、農林事務所普及員の協力により、冬季の暖地栽培技術が定着します。この間、10年にわたり、大川先生、花卉専技(注)、花卉連で国内のトルコギキョウの文字情報を資料文献集として冊子化し、全国に情報提供しました。静岡市の石川正雄さんは大川教授から直接指導を受け、平成3年、最も伝統があるといわれる花の品評会『関東東海花の展覧会』で、トルコギキョウでは初めて農林水産大臣賞を受賞しました。<o:p></o:p>
トルコギキョウは育苗技術、栽培技術、そして販売体制が短期間に一気に整い、産地化に成功した日本でも稀有な花です。静岡県の代表品目のひとつとして今後の発展が大いに期待できるでしょう。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
全国の花卉(全体)生産額ランキング/2010年度<o:p></o:p>
①愛知県 ②千葉県・福岡県 ④静岡県<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
バラ生産額ランキング/同<o:p></o:p>
① 愛知県 ②静岡県 ③福岡県<o:p></o:p>
トルコギキョウ生産額ランキング/同<o:p></o:p>
①長野県 ②福岡県 ③静岡県<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
(注)花卉専技……県行政、普及、試験研究の各職種やJA等の団体と花卉に関する技術的なサポートや連携をし、スムーズに業務が遂行できるようにする県職員の役職通称名(現在は廃止)。<o:p></o:p>