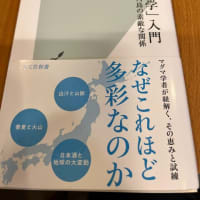11月15日(日)、東京恵比寿の日仏会館で、フランス国立極東学院東京支部主催のシンポジウム【一休とは何か~この妖怪に再び取り組む】が開かれました。白隠研究の大家・芳澤勝弘先生(花園大学国際禅学研究所教授)が一休さんを“妖怪”と称し、その一筋縄ではいかない生き様に切り込まれると聞いて、楽しみに馳せ参じました。
今、テレビのゴールデンタイムでお坊さん出演のバラエティ番組やトレンディドラマ?が放送されるなど、ちょっとした仏教ブームだそうですが、日本の歴代のお坊さんで、一般庶民から“○○さん”と親しく呼ばれるのは、一休さん、白隠さん、良寛さんの3人くらい。中でも一休さんの知名度はダントツですね。私なんかリアルタイムでアニメの一休さんにかじりついていた世代ですから、大人になって一休さんのこの肖像画を観たときは、呆気にとられてしまいました。聞けば晩年は酒に溺れたり若い女性にのめりこんだ破戒坊主。・・・なのに日本でイチバン有名なお坊さん。確かにつかみどころのない“妖怪”かもしれませんね。

今回のシンポジウムは、ヨーロッパで唯一といってよい一休研究の専門家・ディディエ・ダヴァン先生(フランス国立極東学院東京支部長)が企画され、東京五島美術館で開催中の一休展(こちら)を監修された芳澤先生のご尽力で実現した、おそらく史上初めて、一休宗純を本格的に取り上げたシンポジウムだそうです。現在、好評発売中の別冊太陽「一休―虚と実に生きる」に寄稿された研究者が次々に登壇し、10時から18時までみっちり、かなり密度の濃い研究発表をされました。素人にはとてもついていけない専門家レベルの内容でしたが、アニメの一休さんが、この肖像画の一休さんになるまで、どんな人生を送られたのか、それが日本の禅宗史の中でどんな意味を持つのか、ほんのさわりの一部分だけでも触れることのできた刺激的な時間でした。

ここでは各先生方の発表の中から、私なりに面白く感じた一休さんを読み解くキーワードを3つ挙げたいと思います。
瞎驢と滅法
臨済宗の祖師・臨済義玄は、亡くなるとき、“自分の精神を絶やしてはならぬ”と言い、それを聞いた弟子の三聖和尚が「安心してください、自分が継ぎます!」と言って師匠お得意の“一喝”を真似た。それを見た臨済は「お前のような瞎驢(かつろ=盲目のロバ)によってわが法は滅却した」と歎いて亡くなったそうです。無能呼ばわりされた三聖をかばうため(=臨済宗の法系を守るため)、後世の人々は「いやいやこれは、師匠が本当は弟子を認め、叱咤激励した言葉だ」とポジティブ解釈したのですが、一休さんは「自分こそ瞎驢だ!滅法だ!」と宣言。自分の師匠からもらった印可(悟りを得た証明書)を破り捨ててしまいました。
素人ながら、禅とは、原理原則を示した聖典があって、師匠がそれを代々受け継いで、弟子に順を追って習得させ、お墨付きや資格証明を与える・・・という宗教ではないんじゃないかと思います。己の内にある仏性を己の力で磨き上げていく自律の宗教だろうと。一休さんはその本質をとらえ、形式的な嗣法を否定したのではないでしょうか。今、私はお手伝いしている福祉NPOの広報業務にプラスになればと「介護ヘルパー初任者研修」を受講中なんですが、介護の世界はずばり資格がモノを言う世界。初任者研修は130時間必須とか、介護福祉士は受験資格が実務3年以上とか、介護に限らず、現代社会の職能評価の大半は、資格の有無や実務経験数によって判断されます。でも、介護の現場でほんとうにモノを言うのは、形式的なマニュアルでははかりしれない“人間力”。ましてや、人の心を支える宗教家たる者の資質は、人間力そのものがすべてではないか・・・なんて考えてしまいます。
一休さんは、「立派な衣を着て禅を説く諸君は、みな名利(名誉と利益)のため。私は子孫たちが大燈国師の法をも滅却することを求める」と言ったそうです。大燈国師とは大徳寺を興した日本の禅宗随一の名僧。その教えを形式的に受け継いで名利を得るのはナンセンス。どんなに尊い教えでもいったんリセットしてゼロから興せ(=滅宗興宗せよ)。「殺仏殺祖(=釈迦や達磨の教えもリセットせよ)」というほどの強烈な思想を持っていた臨済義玄の精神に、一休さんは殉じていたようです。祖師の精神を“滅却”するなんて、キリスト教やイスラム教ではあり得ない話。このことを、パリのテロ事件の翌日にフランス人研究者主催のシンポジウムで教えられたことに、私自身、強烈な印象を受けました。
ら苴(らしょ)
ら苴(ら=くさかんむりに石3つ)とは、「小汚い、不風流、がさつ、野暮、奔放」という意味。瀟洒の反対語とされています。もとは「川僧ら苴、浙僧瀟洒(=四川の山僧は小汚くがさつ。都に近い浙江あたりの僧はこざっぱりして洗練されている)」という言葉から来ているそう。私の好きな映画『ロード・オブ・ザ・リング』や『ホビット』の登場人物に喩えるなら、ドワーフとエルフの対比に近いかな。分かる人にしか分からないと思うけど(苦笑)。
でも一休さんは「ら苴」がお気に入りで、自作詩集『狂雲集』には「ら苴とはわが一休門派の宿業。女色に加え勇色(男色)も耽る」「ら苴の生涯は酒好き、色好き、唄も好き」なんて詩も残しています。それでもって、髭面でボサボサ頭の肖像まで描かせたのですから、まさに“確信犯的ら苴”です。「不風流を意味する“ら苴”こそ、一休にとっての風流。印可をありがたがって華やかな高座に昇るエリート僧に対する強烈なアンチテーゼ」と芳澤先生。滅宗興宗の精神に通じるようですね。
ちなみに会場から、一休さんの破戒ぶりは後小松天皇のご落胤という出自が影響しているのでは?という質問がありましたが、この当時、皇族や公家の関係者が出家する例は珍しくなく、一休さんだけが特別な存在というわけではなかったようです。
一休派
一休さんは印可を徹底拒否した人ですから、弟子たちにも「自分の後継者はいない、自分の禅を背負う者は自分以外にいない」と言い切っていました。晩年、高齢で病に伏せった一休さんに弟子たちが必死に「誰かを後継者に指名してくれないと先生の教えが絶えてしまいます!」と詰め寄り、根負けした一休さんが没倫という弟子の名を上げ、皆が喜び勇んで没倫にそれを伝えると「馬鹿なことを言うな、先生の長年の言動をみていれば、ウソをついたかモウロクしたか、そのふりをしているかだ、この愚か者めが!」と一喝。で、一休さんが亡くなった後、途方に暮れた人々は、一休の墓が建てられた酬恩庵に年1回集まって、何か困り事があったら皆で話し合って解決しようということにした。一休遠忌に酬恩庵評議を行なうこの結衆スタイルが、なんと、明治33年まで開かれていたと記録に残っているそうです。僧衆と俗衆が協働で僧坊や寺庵の運営を支え、地域コミュニティの中で地に足のついた宗教活動を行なったんですね。
発表者の矢内一磨先生(堺市博物館学芸員)は「彼らは大徳寺塔頭の真珠庵に“本部”を置き、一貫して黒衣のまま、大徳寺歴代に出世することなく、大徳寺を護り続けた。そこには語録や印可とはまったく隔絶した禅文化を見ることができる。これも法燈の存続に他ならない」と述べられました。一休さんには後継者がいなかったと言われていますが、一休派のこのやり方はきわめて進歩的で、一休さんの系譜らしいと思いました。
ほか、一休さんが同世代の人々にどんなふうに評価されていたのか、とか、一休さんは京都五山のエリート衆とは一線を画したものの若い頃は五山文学に影響されて詩の修業をしていたこととか、戦後の左派知識人が一休さんを反体制のシンボルにしたことは江戸時代に「とんちばなしの一休さん」のイメージを造ったことと同じで、時代によって一休像が書き換えられる現象についてなど等、多面的な研究成果が発表されました。主な論点は別冊太陽に紹介されていますので、ぜひお手にとってみてください。