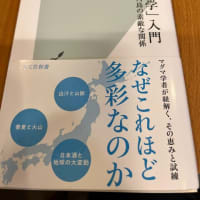気づけば、またしばらくブログ更新をさぼっていました。バイトを始めて以来、休みゼロの暮らしが2ヶ月。肉体疲労で免疫機能が低下したせいか、帯状疱疹まで出来てしまいました。気持ちと体がリンクできていない状態に、ちょっと驚いています。こうして人は少しずつ老いを実感していくんですねえ。もう10月がもう終わってしまうのか・・・早いなあ。
季節が変わったと実感するのは、冷蔵庫に冷たいお茶をストックする習慣がなくなったこと。暑い時期はお茶を急須で淹れて瓶ボトルに移して冷ましておくのですが、今月半ばぐらいから急須のお茶を熱いまま飲むようになりました。今、飲んでいるのは取材先の伊東で買った「ぐり茶」。沸かしたてのお湯で乱暴に淹れても結構美味しいので、すぐに飲みたい!ってな時は重宝します。
今月は静岡県のお茶の手揉み技術の取材があり、静岡がお茶どころになったマンパワー=茶師の技の価値について改めて深い感動を覚えました。県史に造詣の深い中村羊一郎先生が編集した『静岡県指定無形文化財・八流派の手揉茶技法』という冊子に、次のような記述があります。読んでいるうちに、手揉茶の蒸し技術と日本酒の麹造り、茶師と杜氏の置かれた状況に多くの共通点があると実感しました。
『静岡県指定無形文化財・八流派の手揉茶技法』 中村羊一郎編 (社)静岡県茶手揉保存会発行
●流派の発生とその意義
静岡県の基幹産業のひとつである煎茶の生産は、幕末における開国を契機とする貿易開始とともに飛躍的に増大し、一時は我が国からの輸出品目で生糸につぐ第二位を占めるほどになった。
その背景には牧之原や三方原台地の開墾に見られるような茶園の拡大という生産基盤の整備があったが、それと並んで良質の茶を安定して生産するための製茶技術の開発にも注目しなければならない。
静岡県の製茶技術は近世までの先進地である山城(宇治)や近江(朝宮・土山)や伊勢(水沢)などから導入されたが、その技術を身につけた者たちがさらに自ら工夫をこらすことによって、より高品質な茶を効率的に生産するための製法が考案されていった。
このような製茶技術に長じた職人は茶師と呼ばれ、各地の農家に雇われた。自分が製茶した茶が、買取に来た商人によってただちに評価されるという厳しさの中で、少しでも高価に売れる茶を揉まなければならない。(中略)ときにはその地位を奪おうとやってきる旅の茶師と対決して、自らの優位性を示さなければならないこともあった。
こうした実践を重ねる中で評価を高めた茶師は、県や業界の推薦を受けて各地に招かれ、伝習所を開設し、自らの技術を多くの若者に伝授していく。弟子たちは伝習の記念として師匠に大きな幟を贈り、グループの結束を図った。師匠格の茶師は、焙炉場の軒先にこの幟を高く掲げて自らの技量を誇示し、まわりからはノボリモチと呼ばれて尊敬された。これが静岡県独特の茶手揉み流派発生の原因のひとつである。
(中略)
それぞれの流派の開祖は自らの技術に絶対の自信をもった。それは生産地によって茶葉の性質が微妙に異なっており、自分の揉み方こそがそれにもっとも適しているという信念があったからである。
たとえば南向きの日照時間の長い肥えた土地の茶は肉厚であり、反対に日が当たりにくい山間地域の茶は肉が薄い。そういった茶葉をよい茶に仕上げるためには、いつ、どんな風に力をこめたらよいのか、時間をどれだけかけるかというような具体的な相違点が生じてくる。つまり多様な流派発生のもうひとつの背景として考えられるのは、生産地域の特色を活かした独自の工夫が互いの相違点を浮き彫りにしたということである。
それが伝習所において結ばれた師匠と弟子という人間関係と重なり合って集団としての強い自己主張となり、ひいては独自性の象徴として流派名が唱えられるようになっていったのである。
なお明治10年代には輸出の好調さに乗じて日干し番など煎茶とはいえない下級茶や偽茶、着色茶などの不良品が大量に出荷され、アメリカから制裁を受けたことがあり、県はいっときの利益を追わず、良質な茶を生産するよう厳しく指導した。優れた手揉み技術の開発は、こうした茶業界の動向とも無縁ではなかったろう。
*静岡県指定無形文化財の八流派=青透流(志太)、小笠流(中遠・浜松)、幾田流(富士以東)、倉開流(北遠)、川上流(静岡)、鳳明流(静岡・岡部)、興津流(清水)、川根揉切流(川根)
●蒸し加減の表現からみた八流派の差異
「蒸し」は緑茶製造の第一歩で、品質を左右する重要な操作である。生葉の性質によって蒸籠に入れる生葉の量、箸の使い方、蒸し時間などを加減しなければならないが、要は、蒸し葉の香気によって適度を知ることである。
若蒸しは青臭さや苦渋味が残り、貯蔵中に変質しやすい。蒸し過ぎれた鮮緑を欠き、香気が冴えず、蒸し葉がべとついて揉みにくく、肌荒れや小玉を生じやすい。近頃、深蒸しの傾向があるが、滋味の点では勝るが、香気・水色に難点があり、一得一失である。
目で蒸すな鼻で蒸せ
黄色に蒸して青く揉め
蒸す前に芽の質を見よ
つまり、蒸しの加減はおのれの鼻をじゅうぶんにきかせよ、というのである。8つの流派とも生葉を蒸す時間は30秒前後と変わらず、箸でかき混ぜていったん蓋をする。その後の処理をどんなふうに表現しているか比較してみる。
「青透流(志太)」 蓋の間から甘涼しい香りが出たら2~3回蓋をたたいて取り出し・・・
「小笠流(中遠・浜松)」 蓋をして芳香の出た頃、蓋を打ちながら匂いをかぎ・・・
「幾田流(富士以東)」 蓋を打ちながら芳香の発生を確認し取り出し・・・
「倉開流(北遠)」 蓋を打ちながら匂いをかぎ、芳香が出たら甑から外し・・・
「川上流(静岡)」 蒸気が上がってきたら方向を確認し、1~2回蓋を打って・・・
「鳳明流(静岡・岡部)」 蓋を2~3回打ちながら嗅ぎ、芳香を確認し取り出す
「興津流(清水)」 蓋をして甘香りの出たとき蓋を前2回・後1回たたきつつ速やかに出し・・・
「川根揉切流(川根)」 蓋をして20秒前後経て芳香が確認できたら取り出し急冷する
6つの流派が「芳香」といい、青透流は「甘涼しい香り」、興津流は「甘香り」と表現している。芳香だけでは漠然としているが、甘涼しいというのもなかなか微妙な表現である。国語辞典にもない特徴的な言い方が、いつから使われているのだろうか。
(中略)
明治38年式製法大要には「蒸しの適度をもっとも容易に知る方法は、青臭きを去り、甘く涼しき香を発し、蒸葉滑らかとなりて箸に付着するを以って適度とす」とあり、以降の指導書に引き継がれていく。(中略)「甘涼しい」という業界用語としての表現が、「青臭さ」と対置される芳香の中身であった。逆に言えば「甘涼しい」の概念を共有化することによって、各流派の独自性が薄れていったといえるのではなかろうか。

どうでしょう。酒造りの技術的なことを少しかじったことのある人なら、製茶のノウハウがすんなり会得できるんじゃないでしょうか。実際、志太杜氏の中には、酒造りが終わってから川根で茶師を務めた人もいました。
鼻で香りを嗅ぎ分けて蒸し加減を調整する=香りや指の感触で麹の切返しや出麹のタイミングを計る、「甘涼しい」という言葉で香りの概念が統一された=「香りよく軽快で丸い」酒質の静岡酵母の出現で静岡酒の概念が統一された経緯など等、相通じるところが多いですよね。
冊子の最後で、中村先生が次のようにまとめておられました。
「現在の製茶機械の性能はきわめて高く、かつての名人の腕前に匹敵するほどになった。しかし、自動化されたとはいえ、茶葉の微妙な差異、わずかな温度差などを判断しながら機械を操作することで、より高品質の茶を作ることができる。
”お茶の心を知れ”と茶師は言った。機械を操作する人にもそっくりあてはまる至言である。そしてなによりも茶は食品であるという事実をしっかりと噛み締めておかねばならない。今ほど生産者が心をこめた食品が求められる時代はない。
茶手揉み技術が多くの人に継承されていくことは、良質茶の生産に寄与すること大であるとは言うまでもないが、実は食品と人間とが直接的なつながりを持ち続けるという点においてこそ、きわめて大きな意味があるといえるのである」
・・・ふるさと静岡に、美味しい茶と酒がある悦び、美味しい茶と酒を生み出す職人がいる誇りと幸せを噛み締めたいと思います。