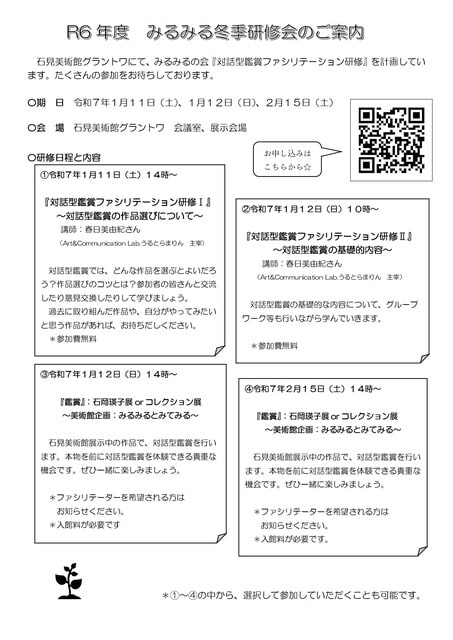作品:「パルコ:あゝ原点。」(1977年)
「石岡瑛子Iデザイン」展 「みるみると石岡瑛子を見てみる?」の対話型鑑賞会
https://www.grandtoit.jp/museum/ishioka_eiko_idesign_iwami
日 時:2025年1月12日(日)14:00~14:30
場 所:島根県立石見美術館 講義室
参加者:19名(みるみるメンバー8名)
ファシリテーター:房野伸枝

アートディレクション:石岡瑛子、PARCOポスター「あゝ、
《作品の選定について》
この展覧会のキービジュアルの一つでもあったこの作品は、パルコという1970年代のファッションを牽引するファッションビルの広告です。私はまず、その横長の大画面と鮮やかな色彩に目が留まり、日本の広告なのに、なぜ、この写真と、キャッチコピーなのか?という疑問が浮かびました。それを明らかにしたいという好奇心と、この作品にまつわるエピソードに惹かれ、対話を通してみんなでこの作品を解釈していきたいと思ったのでした。
~この作品にまつわるエピソード~
70年代に入り、石岡瑛子はインドやアフリカなどへの関心とともに、民族衣装に焦点を当て、日本のファッションを原点から捉えなおそうとしていたそうです。この作品はそうしたコンセプトでインドにある村の女性を撮影したものです。しかし当初、その撮影は村の男性の合意なしには許可されず、数週間も待った後、砂漠の向こうから色鮮やかな衣服に身を包んだ赤ちゃんから年配者まで、様々な世代の女性が一斉にやってきたところを写真にとらえたものです。男性優位の村社会の中にあっても、女性たちはあんなにも美しく、鮮やかに着飾り、堂々とこちらに歩いてくる光景に撮影クルーは思わずため息を漏らしたとのこと。このエピソードは「あゝ原点。」というキャッチコピーのゆえんでもあります。
私には写っている人物は全員女性に見えていたので、様々な国でそれぞれの装いがあり、女性が衣服をまとう喜びがどの地域でもあるということが「原点」というコピーに込められていると感じました。そこが、男性優位の社会であろうとも、女性なりの主張が込められていると考えましたし、次の鑑賞作品「角川書店:女性よ、テレビを消しなさい 女性よ、週刊誌を閉じなさい」ともリンクすると考えました。上のエピソードについては、鑑賞のどのタイミングで開示するかを図りながら進めるつもり。以下時系列に従って鑑賞を要約しながら、ファシリテートの意図や反省点をまとめてみたいと思います。

《鑑賞の流れの要約》
・は鑑賞者の発言 Fはファシリテーターの発言
( )はファシリテーターの意図や振り返りでの反省点
①人物について
・人がたくさんいる。
F:それはどんな人で、どんな様子?どこからそう思いましたか?
(パラフレーズで詳細なディスクリプションを促したが、さらに細やかなディスクリプションが必要だった。)
・女性が多いが男性や赤ちゃんもいる。(根拠をもって男性もいるという発言から、男性がいると感じている人を否定する要素は出したくなかったので、エピソードの情報提供は控えることにした。性別についての発言があった時点で、もっと性別について鑑賞者へ投げかけていれば、さらに詳細なディスクリプションができたのだが、そうしなかったのが残念。ここでは情報は伝えずに見えていることから鑑賞を深め、パルコの広告であることと、「原点」というコピーを掘り下げることにした。)
・黄色や赤、緑や、模様など鮮やかな衣装。どうやって染めたのかな?お祭りかな?特別な日のように見える。
F:カラフルで日常というよりは非日常で、着飾っているということでしょうか。
・赤色が鮮烈。塩田千春の作品に通じる。塩田の作品からも、情熱や生命感、プリミティヴなものを感じるが、それと同じものを感じた。コマーシャリズムのためなのだろうが、どこで使われたのだろう?ポスター?当時の流行もあったか、人類の原点、アフリカを意識しているのでは。
F:情熱や原始的なものを感じるということを話してくださいました。(この作品に直接関わらないアーティストとの類似点に関しての発言。他の鑑賞者が混乱することを避けるために無関係な要素は排除してパラフレーズした。)
②文字について
・「原点」って何の原点だろう?
・「PARCO」とあるので、パルコというファッションビルのポスターであろう。
・商業目的のポスター。 パルコは当時のファッションの先端的存在で、ビルを飾る広告。人目を引くための形、構成、文字。
・キャッチフレーズ「あゝ原点。」の「。」にこだわりを感じそれが気になる。
③再度人物について
・妊婦もいるし、赤ちゃんから年寄りまでいろんな世代の人がいる。女性を対象にしていると感じる。(①でしっかりディスクリプションをしていれば、ここでの繰り返しを避けることができたし、女性をモチーフにしている意味を深められたかもしれない。前述のエピソードを情報として伝えるチャンスになったかも?)
F:これまで人物、服装、文字、など見てきましたが、その他何か考えられることはないでしょうか?(小まとめして、そこからどう考えるか、他の視点への転換を促そうとした)ここはなんでしょうか?
④撮影場所や人物の様子について
・背景が気になる。背景は空なのか?青い(人工的な)背景なのか?地面が土のようなので、外だと思うがどこなのか?
・ほとんどの人が目線をこちらに向けているので、日常を切り取ったというよりは、このトリミングで、写真に写りに来ている。そういうモデルとしての意思を感じる。(「意思」について、どこから?というパラフレーズがあるとよかった。)
F:ほとんどの人の顔がこちらを見ているということから、こういう並びでこちらに向かっている。作品のモデルとして写りに来ているのではないか。それは日常ではなく、モデルとして写真に写ろうとしているということでしょうか。
・こちらに向かってきているということの根拠が明らかにされていないまま、そうであるかのように話が進むのは問題があるのでは。集合写真にも見えるが、向かってきているのか、静止しているかで、この状況のとらえ方が変わると思う。
F:今のご指摘から、向かってきているというのはどこから?(根拠を明確にしていないという指摘から聞き直した)
・視点の高さはみぞおち当たりなので、地平線がそのあたりに見えるはずだが、実際の地平線はかなり低い位置。向こうから向かってきているのなら、地平線がもっと上にないと遠近法としておかしい。ということは向こうが崖なのではないか。向かっているようには見えない。(この発言について、遠近法という専門的な内容もあったので、他の鑑賞者と共有できているのか、確認が必要だった。)
・足が浮いているし、脚の曲がり具合から、こちらへ歩いているように見える。
(場所について考えてもらう場面で、人物の様子についての話になった。もう少しリンキングすれば深められるチャンスだったかもしれない。)
⑤これまでの話から解釈へ
F:「あゝ原点。」や「PARCO」という文字とこれまでの話を踏まえて考えられることはありますか?
・このポスターはポスターの中の顔がこちらに向いていれば1970年代の時代背景を考えると、バブルの前の労働者へ、ファッションを楽しむということはこういうことなのだとキャッチな色、広告の変形サイズなどで目を引くものにしている。
F:ファッションの広告の被写体として、なぜ、こういう表現なのか、何の原点なのでしょうか。
・ファッションを楽しむ原点という意味では。70年代の日本はまだこういうカラフルな色彩ではなかったかも。
・黄色や赤などの鮮やかな衣装から、アフリカを想起させ、カラフルな一張羅の服を着ることを楽しむ人たちだと感じる。そういうファッションの原点が、高度経済成長時代後の日本人への訴えとして表現されている。
F:日本でもなく、西洋でもない国の写真を使って、着飾ってファッションを楽しもうということを主張しているということでしょうか。
・ここがアフリカだとしたら、人類がアフリカから始まっていることからも「原点」につながるのでは。
・人の骨格や顔からアジアっぽい、インドっぽい人に見える。とすれば、原点の意味合いも変わって、布が交易でアジアから広がったという、布の原点ともいえる。ファッションビルであるパルコの広告として、装いの原点とも考えることができるのでは。
F:作品を見ながら「あゝ原点。」の意味について、皆さんでいろいろ話をしてもらいました。ここがアフリカであれば人類発祥としての原点と考えることができ、インドであれば布の原点ともいえる。それらに共通するものとして、衣服を身にまとうファッションの原点として、この写真とキャッチコピーがパルコの広告として表現されたのではないか、という意見でした。この作品を通して、ファッション、装うということについて、皆さんで考えることができました。
《鑑賞者の感想》
〇赤、青、黄の色がまず飛び込んできた。 ~色の原点~
〇お祭りのように様々な楽しいことをファッションに反映して以降 ~ファッションの原点~
〇歩いているから ~未来に向かってGO~
〇「じっくり見る」ができて満足
〇「あゝ原点」というキャッチコピーや被写体の衣装、構図などから、はじめ見たときにとても強い印象を感じました。特に女性が中心に映り、何もない場所に色とりどりの艶やかなサテンなど、不自然さもありました。
〇他の方の意見を聞きながら、世代の違い、見方の違いを感じ、より自分の見方を深められたように感じます。(同様の意見2名)
〇作品を見てじっくり考えることがなかったので、勉強になった。面白かった。
〇場所や時代、民族から考えられることを結び付けていくのが面白かったです。今日は文字もあったので、そこを結び付けることさらに考えが深まりました。
〇商業広告としての作品をじっくり見ることができて、また、色彩についてとても印象的で面白かった。
〇画像の中身とコピー(テキスト)の間で発言が行ったり来たりすることをファシリがどう統合していくのかが肝かなと思いました。難しいですが…
《まとめ》
今回の展覧会の作品のほとんどは商業広告という、クライアントの意向と、デザイナー自身のコンセプトをギリギリにせめぎ合わせながらも、社会に疑問や主張を投げかけたような作品だと感じます。鑑賞した作品も、単なる宣伝のための広告ではなく、既存の価値観を揺さぶり、新しい価値観を見せつけ、広めようとする制作者の強い意志を感じます。今よりももっと男性優位な社会の第一線で活躍した石岡瑛子が、世の女性へ問いかけ、煽動しているような・・・。そうした熱を鑑賞者の皆さんと対話を通して共有したいと思いました。
対話や鑑賞者の感想にもあるように、何の原点であるのか、なぜこの被写体なのか、という問いをそれぞれが考え続け、様々な解釈が生まれ、共有することができたように思います。この機会を提供してくださった石見美術館、鑑賞会に参加してくださったみなさん、みるみるの仲間に深く感謝します。ありがとうございました。
振り返りで指摘されたことは今後にも生かし、限られた時間内に深い解釈まで進めることができるように頑張りたいと思います。