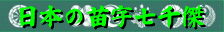漢二字(その多くが道義的な意味を持った)の名が盛んになったのは、
平安期に入って、三代目の50人の皇子女がいた嵯峨天皇のとき
からである。
【 嵯峨天皇による人名習俗の新改変 】
① 身分の高い生家出の后妃が産んだ場合〔皇族へ〕
皇子・・・漢二字(正負・秀良)
皇女・・・漢一字に子(正子・秀子)
② 身分の低い生家出の女性が産んだ場合〔源姓を賜り臣籍へ〕
皇子・・・漢一字(信〈まこと〉・弘〈ひろむ〉)
皇女・・・漢一字に姫(貞姫・潔姫)
唐風賛美の強かった嵯峨天皇による人名習俗の新たな改変は、
すべて唐風の模倣であった。それ以前にあっては、皇子女の名は、
おおむね乳母の生家の家の名が付けられていた。
桓武の山部、平城の安殿(あて)、嵯峨の神野、淳和の大伴など。
漢字二字を重ねて人の名とする習俗、またその上の一字を共通
にする行列字の習俗も古くからのものであり、現在に伝えられている。
②の場合、信(まこと)・弘(ひろむ)・常(ときわ)・寛(ひろし)・
明(あきら)・定(さだむ)らに一字名と源姓を賜うて臣籍に降ろした
のは、北魏の世祖が、同族の河西王の子、賀の人物の非凡を
認めて西平候に封じ、龍驤将軍に任じ、
「卿と朕とは源を同じうす。事に因って姓を分かつ。
今より源を氏となすべし」(『魏書』源賀伝)
と、源姓を与えた故事にならったものである。
嵯峨帝によって、創始された皇族子女の二字名・一字名の習俗
は、皇弟淳和帝が踏襲して定着し、今日に至っている。
漢二字のこの人名習俗は、後続のみならず、貴族からさらに武士
階級に及び、実名のことを「二字」とまで呼ぶまでに至った。
下層の庶民は、長く二字名を用いることをはばかったが、、
明治維新による四民平等の社会の到来とともに誰もが二字名、
一字名を望むがままに付けている。
 『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男 ;参考
『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男 ;参考
いつもありがとうございます。
名前の習俗
日本における名前の習俗も、歴史と共に変遷した。
『古事記』の伝える伝承によれば、天皇家のこの国土における
始祖は、高天原(たかまがはら)から九州は日向国高千穂に降臨
したいわゆる天孫(日の神天照大御神の孫)にして、正勝吾勝
勝速日天忍穂耳命(まさかつあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)の御子、
天津日高日子蕃能爾爾芸命(あまつひたかひこほのににぎのみこと)という。
神話の時代から歴史の時代に入ると短くなったものの、身辺卑近
の事物をかたっぱしから人の名としたのである。
例えば、中臣必登(ひと〈人のこと〉)・石川虫名(狢〈むじな〉)・
土師八手(はにしのやつで)・門部金(かどべのこがね)・
藤原愛発(あらち〈爆風のこと〉)・伊余部馬飼(いよべのうまかい)・
大中臣魚取(おおなかとみのなとり)・錦織壺(にしごりのつぼ)・
県犬養手襁(あがたいぬがいのたすき)・榎井靺鞨(えのいまつかつ)・
丹治大目(たじひのおおめ)・巨勢奈氏(なで〈撫でる〉)麻呂・
宮道阿弥陀(みやじのあみだ)・船小揖(ふねのこじか)など。
 『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男 ;参考
『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男 ;参考