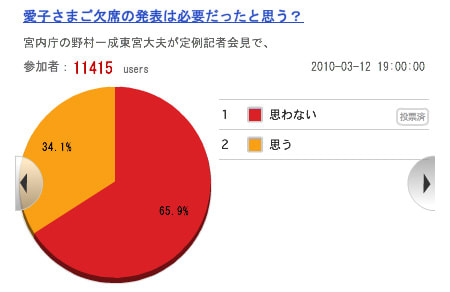きのうは建材商社・キムラさんの年に1度の展示会で講演。
集まるのはすべて建築関係者ということで、
北海道の住宅の歴史ネタと、北海道R住宅の情報について。
まぁ、ちょうど雑誌をやっているので
いろいろな写真が見られて、住宅もたくさん見ているだろうという
推定でお話しが持ち込まれるのですね。
私の方としては、終始一貫、「性能とデザインいい家大研究」
というこのブログで表現しているようなスタンスで
お話しし続けております。
そうやっていると、話を聞きたいなどという方も現れる。
まぁ、ありがたいというところであります。
なんにせよ、ひとと知り合う機縁をいただけるのは幸せ。
わたしの「北海道の住宅の歴史ネタ」では、
このブログで触れるような、歴史的な住宅、遺跡などを題材に
時空を超えて人間の居住環境を考えております。
たまたま歴史物が好きなので
勢い、こういうようなところに興味が至った、というところ。
まぁ、あんまり聞いたことがない視点なので、
逆に現代の住宅というモノを考えるきっかけにはなる。
そんな思いでいろいろ調査し続けている次第であります。
ただまぁ、牛歩の歩みでの研究ですので、すこしづつの展開(笑)。
ただ、歴史人口的なものも縦糸にして、
客観的なスタンスを心がけている次第です。
っていうようなことですが、
最新住宅設備・建材情報、
しかも、寒冷地北海道での開催ということで、
毎年、これを機会に北海道の視察、という本州地域のみなさんも多い。
省エネルギー関係では、毎年ユニークな商品が展示されていまして
楽しいものがあります。
写真は、蛍光灯の明るさをもっと引き立てるための「反射板」装置。
夏期の室内環境では、基本的には窓からの日射取得熱の制御が必要。
同時に、高断熱になっていくと、
室内発熱源からの発生熱も大きい。
そういう意味から、こういう装置的な工夫も面白い。
基本は省エネルギーですが、エネルギーの効率のいい利用、
っていうようなアプローチも大いに進んで欲しい分野だと思いますね。
北のくらしデザインセンター
NPO住宅クレーム110番|イザというときに役立つ 住まいのQ&A
北海道・東北の住宅雑誌[Replan(リプラン)]|家づくり・住まいの相談・会社選び