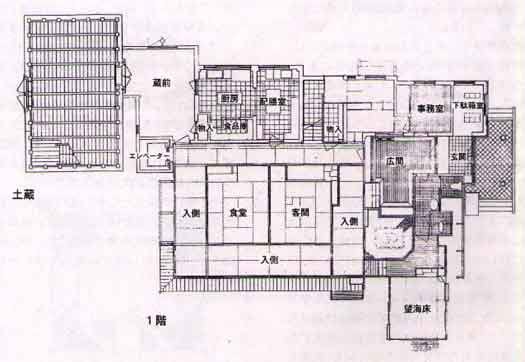住宅の賞というのはたくさんあります。
わたし自身もそういう賞の審査員をやったりしたこともある。
顧みていかに不明であったかと恥じらう自分がいます。
そういう経験からしても、やっぱりそれぞれ成立の仕方が違う個別の住宅に
「優劣」を付けるのは、相当ムリがあるようにいつも感じています。
きのうFacebookをチェックしていたら、秋田の建築家・西方里見さんが
自ら応募された賞の選考過程について、率直な意見を発言されていた。
わたしのような人間は、応募する作り手とは違う立場なので、
その内的な葛藤は、忖度することはできるけれど見えにくい部分もある。
けれど、言わんとしていることはおおむね共感出来ると思いました。
そんなことを考えていて、数日前の建築知識ビルダーズ主催の「エコハウス」
審査の時にゲストとして発言を求められた鎌田紀彦氏の発言を思い出した。
以下、録音データからその内容・要旨を。
「ボクは世の中に厚い断熱の建物を普及させようと思ってやってきたんですけど、
この審査に残った厚い断熱の住宅を見ていると感慨深いものがある。
しかし、このコンテストは厚い断熱を競うものではなく、エコハウスなのだという。
では「エコハウス」ってなんだ、なんの意味があるんだろうと考えさせられた。
何を競っているのかが疑問。エコハウスがなにを意味しているのか不明。
(中略〜北海道から応募した住宅へのコメントで)審査員の顔ぶれをを見て
どうしてこの人たちが北海道の住宅を審査できるのかと思った(会場爆笑)。」
かく言うわたしも、(会場爆笑)のあたりで激しく同意していた(笑)。
まぁ先生らしい一流のジョークではあったのですが、核心も突いているなぁと。
住宅の賞ということには大きな意義はあると思います。
とくにいま断熱ということが普及段階にある日本の温暖地においては
賞の存在自体が、そのことへの関心を呼び起こす大きな起爆剤になる。
この「エコハウス」賞がそういう役割を果たしてきていることはリスペクトします。
しかしその上で、住宅に優劣を付けるコンテストをやるのであれば、
その「判断基準」要素を常識的にわかるように明示すべきだと思う。
応募する側にとっては、非常に多くの設計制約を踏まえながら、
ある解に至った建物を、さらに非常な努力を払って「応募」している。
その努力に対して「優劣を付ける」には、明確な基準が示されなければならない。
ある北海道の住宅の賞の「講評」で、本州地域から来た審査者が、
応募者が住宅説明にQ値とかC値とか平明な数値を示して話しているというのに、
断熱気密について自らはほとんど知識がないと公言されていた。
断熱という基本を踏まえてデザインしている応募者対象に対して
失礼ながら、そこを知らないで住宅デザインを審査していることになる。
そのような住宅の賞のいまの現実を見ていると、人口の8割を占める温暖地側が、
人口規模の多寡のエセ「正統性」や恣意で順位を押しつけているだけではないかと。
それは中央に対して「鄙」は服従すべきと言っているようにも聞こえる。
住宅の賞というものに、どうも納得がいかない部分がある。
わたし自身もそういう賞の審査員をやったりしたこともある。
顧みていかに不明であったかと恥じらう自分がいます。
そういう経験からしても、やっぱりそれぞれ成立の仕方が違う個別の住宅に
「優劣」を付けるのは、相当ムリがあるようにいつも感じています。
きのうFacebookをチェックしていたら、秋田の建築家・西方里見さんが
自ら応募された賞の選考過程について、率直な意見を発言されていた。
わたしのような人間は、応募する作り手とは違う立場なので、
その内的な葛藤は、忖度することはできるけれど見えにくい部分もある。
けれど、言わんとしていることはおおむね共感出来ると思いました。
そんなことを考えていて、数日前の建築知識ビルダーズ主催の「エコハウス」
審査の時にゲストとして発言を求められた鎌田紀彦氏の発言を思い出した。
以下、録音データからその内容・要旨を。
「ボクは世の中に厚い断熱の建物を普及させようと思ってやってきたんですけど、
この審査に残った厚い断熱の住宅を見ていると感慨深いものがある。
しかし、このコンテストは厚い断熱を競うものではなく、エコハウスなのだという。
では「エコハウス」ってなんだ、なんの意味があるんだろうと考えさせられた。
何を競っているのかが疑問。エコハウスがなにを意味しているのか不明。
(中略〜北海道から応募した住宅へのコメントで)審査員の顔ぶれをを見て
どうしてこの人たちが北海道の住宅を審査できるのかと思った(会場爆笑)。」
かく言うわたしも、(会場爆笑)のあたりで激しく同意していた(笑)。
まぁ先生らしい一流のジョークではあったのですが、核心も突いているなぁと。
住宅の賞ということには大きな意義はあると思います。
とくにいま断熱ということが普及段階にある日本の温暖地においては
賞の存在自体が、そのことへの関心を呼び起こす大きな起爆剤になる。
この「エコハウス」賞がそういう役割を果たしてきていることはリスペクトします。
しかしその上で、住宅に優劣を付けるコンテストをやるのであれば、
その「判断基準」要素を常識的にわかるように明示すべきだと思う。
応募する側にとっては、非常に多くの設計制約を踏まえながら、
ある解に至った建物を、さらに非常な努力を払って「応募」している。
その努力に対して「優劣を付ける」には、明確な基準が示されなければならない。
ある北海道の住宅の賞の「講評」で、本州地域から来た審査者が、
応募者が住宅説明にQ値とかC値とか平明な数値を示して話しているというのに、
断熱気密について自らはほとんど知識がないと公言されていた。
断熱という基本を踏まえてデザインしている応募者対象に対して
失礼ながら、そこを知らないで住宅デザインを審査していることになる。
そのような住宅の賞のいまの現実を見ていると、人口の8割を占める温暖地側が、
人口規模の多寡のエセ「正統性」や恣意で順位を押しつけているだけではないかと。
それは中央に対して「鄙」は服従すべきと言っているようにも聞こえる。
住宅の賞というものに、どうも納得がいかない部分がある。