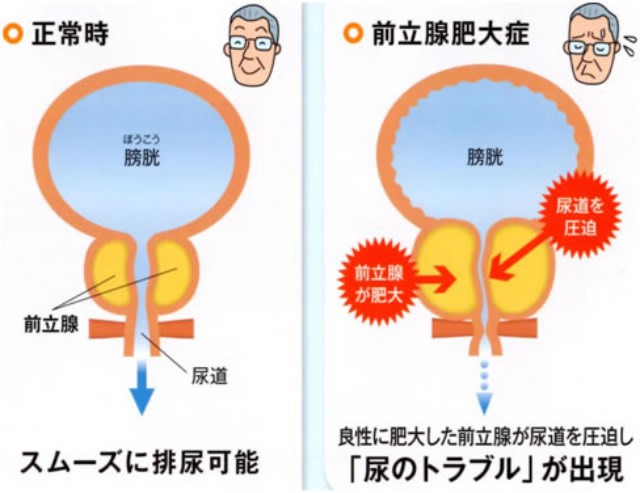今日で、盛岡道から仙台道に入る。これまては宿の予約を前もってしておいたので、無理でも頑張ってほぼ計画通り歩いてきた。しかし、40km超えや10時間超えは歩くより、宿に入ってからのブログアップが辛い。目がしょぼしょぼになってしまう。15時前後には宿に入り、夕食までにある程度メドをつけたい。そうでないと、ブログを終えてすぐ寝るだけになってしまう。
予備日はたくさんあるので、無理せずに、昼の段階でその日のゴールを決め、宿を探すことにした。
そのお陰で、今日は、街道を離れて仙台城址(青葉城)と東北最大の雷神山古墳を散策することができた。ゴールは計画より1つ手前の槻木宿とした。なお、仙台からは、宿場の間の距離が短いので、歩きに飽きが来ない。
仙台宿~長町宿
5:00にホテルを出る。街道の国分町通り付近は札幌のすすきののようなところで、朝帰りの若者がうようよいる。

まずは、盛岡道と仙台道の境となる芭蕉の辻を目指す。明治安田生命の前に芭蕉の辻が登場する。
ここには、芭蕉の辻と道標が並んで立っている。道標には「南 江戸日本橋迄 六十九次 九十三里 奥州街道」、「北 津軽三厩迄 四十五次 百七里二十二丁 奥道中」と刻まれている。ここでは、江戸から仙台までを奥州街道といい、これまて歩いてきた三厩までを奥道中といっている。正式な呼称は昔からなかったらしい。
「芭蕉の辻」の碑には、名称の由来が刻まれている。それによると「かってここに芭蕉樹があったがためと言い、また繁華な場所ゆえの場所の辻の訛ったものだとし、更に藩祖政宗が重く用いた芭蕉という虚無僧が一時居住していたためとも言われ定かにはわからない」とある。「正式には札の辻」であって、ここを通っているはずの歌人の芭蕉とは関係ないらしい。
仙台道をスタートする前に、せっかくなので、街道を離れて仙台城址(青葉城)を見に行くことにした。

20分ほどで広瀬川に架かる大橋を渡る。この広瀬川は天然の堀の代わりになっているのでこの城には堀がない。

橋を渡り、城址に入る手前に「片倉小十郎屋敷跡」の案内板がある。
しかし、自分が知っている片倉小十郎は、室蘭、登別、札幌市(白石区)の開拓の功労者である。
片倉小十郎は仙台伊達家筆頭の重臣で、代々城持ちの大名格として処遇された。白石藩の白石城である。徳川幕府は一国一城しか認めなかったが、伊達班には2城を認めたという。

復元された西御門?を上っていく。

みごとな本丸北壁石垣

下から10分ほど登って、本丸跡に到着し、伊達政宗公の銅像の前でシャッターを押してもらう。

本丸跡から朝日に眩しい仙台の町並みを眺める。
再び、芭蕉の辻に戻って、6:30、白河までの仙台道のスタートを切る。
城下町は敵からの攻撃に備えて道を鍵型に曲げて造っているので、その曲がり角が分かりづらい。スマホのガイドマップから目が離せない。

何度か曲がって進むと、東北大学構内の入口前を通る。

街道の面影を残す白壁の旧家も目に付く。

日本で最初の鉄筋コンクリートの橋の広瀬橋を渡ると、長町宿へと入っていく。しかし、まだ仙台市内である。
長町宿~中田宿

宿場内はビルばかりで街道筋の面影は何も残っていない。がしかし、現在の風景ということで長町三郵便局前の様子をカメラに納めて先に進むことにする。
長町駅前から太子堂駅までのビル街の広い県道を進み、東北新幹線のガードを潜る。太子堂駅前を過ぎたら、いっきに寂しい街道となる。
名取川を渡るといよいよ中田宿だ。

長い塀を回した家や白壁の旧家が2軒あるだけ(撮ったはずが写ってなかった)があるだけで、宿場の面影は全くない。写したはずの中の白壁の蔵造り家屋が、検段屋敷とのことだ。

中田宿で面白い信号を目にした。歩いていったら、車が止まってあるのに信号がない。きょろきょろしたら、頭上に初めて目にする信号があった。これは、知らないとまごまごしてしまいそうだ。
中田宿~増田宿
中田宿を出ると、宿場内をその先に進む。ほぼ直線の車道となった街道は見るものもなく、ただもくもくと進む。

増田宿に入っていくと、松の古木がある。明治天皇に随行してきた木戸孝允の和歌の中で「衣笠の松」と詠まれたことから、「衣笠の松」と命名されたと案内板に解説されている。樹齢数百年とのことだ。


交差点を渡りその先に進むと、左手に長い塀と門構えと蔵のある旧家・荘司氏の屋敷か現れる。庭を覗いて見たら「明治天皇増田御膳水」との石碑が立っている。
増田宿~岩沼宿


鞍館地区は、古代の古墳群や墳墓群が密集している地区だそうだ。東北最大の前方後円墳である雷神山古墳があるというので、街道からそれて見にいく。史跡公園になっていて、丸い小塚古墳もあった。雷神山古墳は長さが168mもあり、400年前後に築かれたようだ。仙台平野一帯を統治した地方豪族の墓だと解説されている。こんな大きな実物の古墳は初めて見たのでその大きさにビックリした。しかし、こんなに立派な墓なら誰々の墓と伝承があっても良さそうなのに、と素人的に考えてしまう。

小塚古墳の上から雷神山古墳の後円墳部分を眺める。

雷神山古墳の後円頂上から前方部分を眺める。

鞍館地区を抜けると集落が切れ、水田地帯の歩きとなる。右側にまだ白い蔵王連峰が見える。
国道4号へ合流して別れると、岩沼宿へと入っていく。その入口にかつやがあったので、昼食のカツ丼を食べる。
今日は、槻木宿まで歩けそうなので、宿を探した。2軒あったがいずれも満室とのこと。仕方ないので、槻木駅から電車で戻ることにして、岩沼宿のホテル原田を予約した。高級ホテルで素泊まり5900円とのこと。昨日2000円だったから、まあ良いかと・・・。
岩沼宿は旧家が良く目についた。



上掲のどれがどれだか分からなくなったが、小野酒造(渡辺家)の蔵屋敷、代表銘柄の「武隈」の看板が屋根に架かっている。相傳商店は、1821年創業の老舗の造り酒屋だが、酒粕を使った奈良漬けが評判の店だそうだ。街道を更に進み宿場の中心から大分離れた所でも塀と門構えのある旧家が現れる。

その先に、日本三稲荷・竹駒神社が現れる。携帯へ入ってみる。大きな神社だ。

境内の中に芭蕉の句碑もある。

大きな提灯の下がった山門にも驚く。
神社の境内からホテルが見えたので、リュックを預けて、槻木宿を目指した。
岩沼宿~槻木宿

静かな県道から国道4号に合流するが、阿武隈川の堤防の上を歩く。サクラがもう散り始めていた。

国道から別れる地点に四日市場の一里塚の表示板のみがあった。

槻木宿内を進んでいくと現代な家並が続くが、時折塀と門構えのある旧家が現れる。最初に現れる北条家は広大な敷地を有しているとのことだ。
中心地辺りが槻木駅近くなので、その入口を今日のゴールにした。
15:08の電車で岩沼駅まで戻り、コンビニで夕食を仕入れて、ホテルへ。結婚式場もある高級ホテルに泊まって、コンビニ弁当は年金生活者ならではの知恵?ちょっと侘しい・・・。
今日は時間的余裕はあったが、ネタが多く、ブログアップに手間どってすっかり遅くなった。目がしょぼしょぼ。どんな小さな文字でも見える我が眼に感謝しつつ、乱筆乱文失礼!
「8日目へ」のページへ
予備日はたくさんあるので、無理せずに、昼の段階でその日のゴールを決め、宿を探すことにした。
そのお陰で、今日は、街道を離れて仙台城址(青葉城)と東北最大の雷神山古墳を散策することができた。ゴールは計画より1つ手前の槻木宿とした。なお、仙台からは、宿場の間の距離が短いので、歩きに飽きが来ない。
仙台宿~長町宿
5:00にホテルを出る。街道の国分町通り付近は札幌のすすきののようなところで、朝帰りの若者がうようよいる。

まずは、盛岡道と仙台道の境となる芭蕉の辻を目指す。明治安田生命の前に芭蕉の辻が登場する。
ここには、芭蕉の辻と道標が並んで立っている。道標には「南 江戸日本橋迄 六十九次 九十三里 奥州街道」、「北 津軽三厩迄 四十五次 百七里二十二丁 奥道中」と刻まれている。ここでは、江戸から仙台までを奥州街道といい、これまて歩いてきた三厩までを奥道中といっている。正式な呼称は昔からなかったらしい。
「芭蕉の辻」の碑には、名称の由来が刻まれている。それによると「かってここに芭蕉樹があったがためと言い、また繁華な場所ゆえの場所の辻の訛ったものだとし、更に藩祖政宗が重く用いた芭蕉という虚無僧が一時居住していたためとも言われ定かにはわからない」とある。「正式には札の辻」であって、ここを通っているはずの歌人の芭蕉とは関係ないらしい。
仙台道をスタートする前に、せっかくなので、街道を離れて仙台城址(青葉城)を見に行くことにした。

20分ほどで広瀬川に架かる大橋を渡る。この広瀬川は天然の堀の代わりになっているのでこの城には堀がない。

橋を渡り、城址に入る手前に「片倉小十郎屋敷跡」の案内板がある。
しかし、自分が知っている片倉小十郎は、室蘭、登別、札幌市(白石区)の開拓の功労者である。
片倉小十郎は仙台伊達家筆頭の重臣で、代々城持ちの大名格として処遇された。白石藩の白石城である。徳川幕府は一国一城しか認めなかったが、伊達班には2城を認めたという。

復元された西御門?を上っていく。

みごとな本丸北壁石垣

下から10分ほど登って、本丸跡に到着し、伊達政宗公の銅像の前でシャッターを押してもらう。

本丸跡から朝日に眩しい仙台の町並みを眺める。
再び、芭蕉の辻に戻って、6:30、白河までの仙台道のスタートを切る。
城下町は敵からの攻撃に備えて道を鍵型に曲げて造っているので、その曲がり角が分かりづらい。スマホのガイドマップから目が離せない。

何度か曲がって進むと、東北大学構内の入口前を通る。

街道の面影を残す白壁の旧家も目に付く。

日本で最初の鉄筋コンクリートの橋の広瀬橋を渡ると、長町宿へと入っていく。しかし、まだ仙台市内である。
長町宿~中田宿

宿場内はビルばかりで街道筋の面影は何も残っていない。がしかし、現在の風景ということで長町三郵便局前の様子をカメラに納めて先に進むことにする。
長町駅前から太子堂駅までのビル街の広い県道を進み、東北新幹線のガードを潜る。太子堂駅前を過ぎたら、いっきに寂しい街道となる。
名取川を渡るといよいよ中田宿だ。

長い塀を回した家や白壁の旧家が2軒あるだけ(撮ったはずが写ってなかった)があるだけで、宿場の面影は全くない。写したはずの中の白壁の蔵造り家屋が、検段屋敷とのことだ。

中田宿で面白い信号を目にした。歩いていったら、車が止まってあるのに信号がない。きょろきょろしたら、頭上に初めて目にする信号があった。これは、知らないとまごまごしてしまいそうだ。
中田宿~増田宿
中田宿を出ると、宿場内をその先に進む。ほぼ直線の車道となった街道は見るものもなく、ただもくもくと進む。

増田宿に入っていくと、松の古木がある。明治天皇に随行してきた木戸孝允の和歌の中で「衣笠の松」と詠まれたことから、「衣笠の松」と命名されたと案内板に解説されている。樹齢数百年とのことだ。


交差点を渡りその先に進むと、左手に長い塀と門構えと蔵のある旧家・荘司氏の屋敷か現れる。庭を覗いて見たら「明治天皇増田御膳水」との石碑が立っている。
増田宿~岩沼宿


鞍館地区は、古代の古墳群や墳墓群が密集している地区だそうだ。東北最大の前方後円墳である雷神山古墳があるというので、街道からそれて見にいく。史跡公園になっていて、丸い小塚古墳もあった。雷神山古墳は長さが168mもあり、400年前後に築かれたようだ。仙台平野一帯を統治した地方豪族の墓だと解説されている。こんな大きな実物の古墳は初めて見たのでその大きさにビックリした。しかし、こんなに立派な墓なら誰々の墓と伝承があっても良さそうなのに、と素人的に考えてしまう。

小塚古墳の上から雷神山古墳の後円墳部分を眺める。

雷神山古墳の後円頂上から前方部分を眺める。

鞍館地区を抜けると集落が切れ、水田地帯の歩きとなる。右側にまだ白い蔵王連峰が見える。
国道4号へ合流して別れると、岩沼宿へと入っていく。その入口にかつやがあったので、昼食のカツ丼を食べる。
今日は、槻木宿まで歩けそうなので、宿を探した。2軒あったがいずれも満室とのこと。仕方ないので、槻木駅から電車で戻ることにして、岩沼宿のホテル原田を予約した。高級ホテルで素泊まり5900円とのこと。昨日2000円だったから、まあ良いかと・・・。
岩沼宿は旧家が良く目についた。



上掲のどれがどれだか分からなくなったが、小野酒造(渡辺家)の蔵屋敷、代表銘柄の「武隈」の看板が屋根に架かっている。相傳商店は、1821年創業の老舗の造り酒屋だが、酒粕を使った奈良漬けが評判の店だそうだ。街道を更に進み宿場の中心から大分離れた所でも塀と門構えのある旧家が現れる。

その先に、日本三稲荷・竹駒神社が現れる。携帯へ入ってみる。大きな神社だ。

境内の中に芭蕉の句碑もある。

大きな提灯の下がった山門にも驚く。
神社の境内からホテルが見えたので、リュックを預けて、槻木宿を目指した。
岩沼宿~槻木宿

静かな県道から国道4号に合流するが、阿武隈川の堤防の上を歩く。サクラがもう散り始めていた。

国道から別れる地点に四日市場の一里塚の表示板のみがあった。

槻木宿内を進んでいくと現代な家並が続くが、時折塀と門構えのある旧家が現れる。最初に現れる北条家は広大な敷地を有しているとのことだ。
中心地辺りが槻木駅近くなので、その入口を今日のゴールにした。
15:08の電車で岩沼駅まで戻り、コンビニで夕食を仕入れて、ホテルへ。結婚式場もある高級ホテルに泊まって、コンビニ弁当は年金生活者ならではの知恵?ちょっと侘しい・・・。
今日は時間的余裕はあったが、ネタが多く、ブログアップに手間どってすっかり遅くなった。目がしょぼしょぼ。どんな小さな文字でも見える我が眼に感謝しつつ、乱筆乱文失礼!
「8日目へ」のページへ