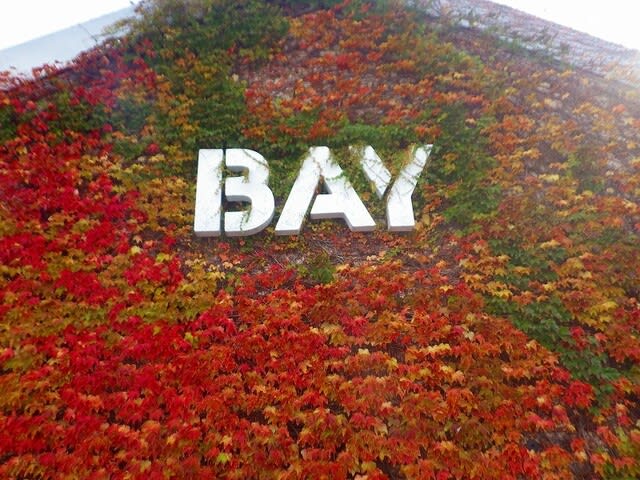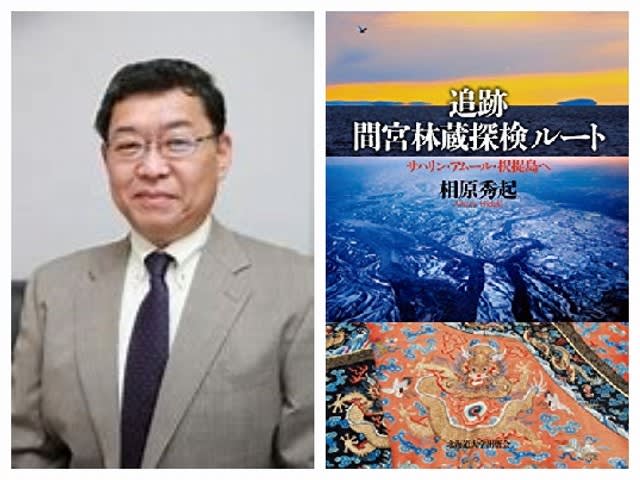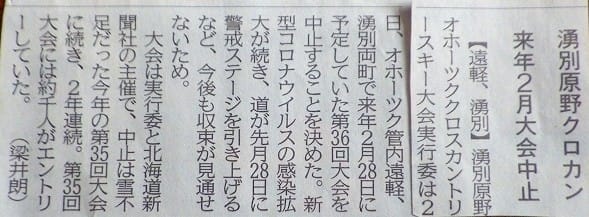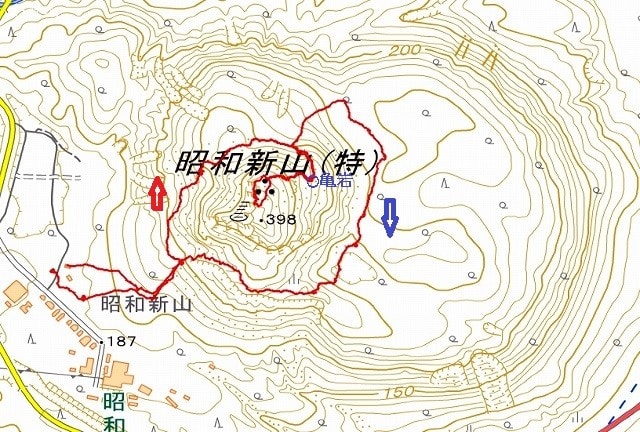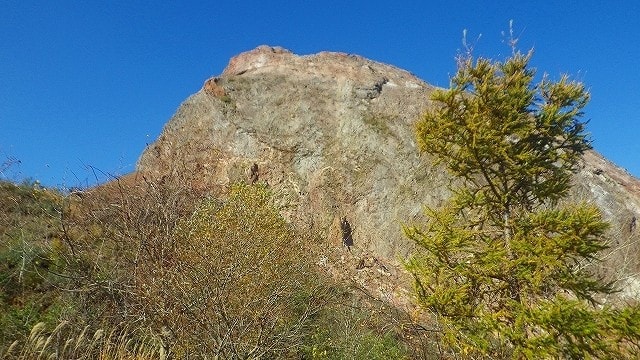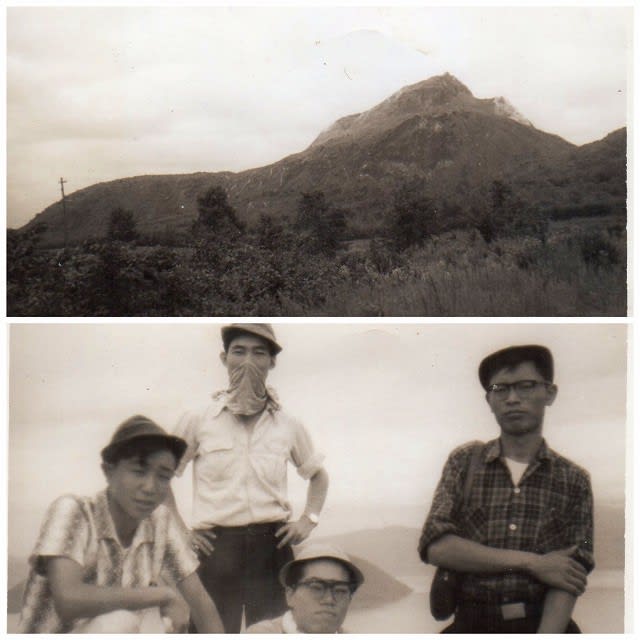これから山陽道(中国街道)の旅となるわけだが、どうも西宮からを西を山陽、または西国街道。大阪から西宮までを中国街道と呼んでいる例が多いので、ここでも西宮までを中国街道と呼んでおくことにしたい。
ホテルを6時に出て、近くの心斎橋から高麗橋近くの北浜駅まで、地下鉄で移動。乗り換えで手間取って、歩いても違わない時間になった。大都会は嫌いだ。
しかし、今日は距離が短かったので、13:40にはゴールすることができ、昨日のオーバーワークの分を取り戻した感じ。しかも、昨日までに比べて、見所も少なく、写真の選定で苦労することはなかった。
なお、省エネブログのために今日からは、これまで詳しく書いてきた宿場の説明は省き、文章やキャブションの中で触れることにする。
高麗橋~尼崎宿

7:00、昨日の京街道の終点の高麗橋からスタート。西国の道路元標となっているので、中国街道の始点でもある。

まもなく、ライオン像や塔の立つ重厚な「難波橋」を渡る。

ビルの谷間や広い道を進み、やがて、茶屋町に入ると、ビルの谷間に地名の由来となる「鶴の茶屋」の石碑が立っている。
 十三(じゅうそう)大橋の左側の歩道へ上がって行くと、
十三(じゅうそう)大橋の左側の歩道へ上がって行くと、
土手の上に大正9年の道標が立っている(左下)。「東 往来安全 池田 四里 伊丹 二里半」などと彫られている。
橋を渡ると、土手の左側に「十三の渡し跡」の石碑がたっていた(右下)。

府道10号線の高架下をくぐると、左手に「香具波志神社」がある。
神社の名前は孝徳天皇の行幸の際、詠んだ歌に由来するとか。中世には楠木正儀(正成の三男)が戦勝を祈願したり、戦国時代には三好長慶が鳥居一基を奉納している。

神社の前に店開きをしてある果物屋さんに挨拶をし、聞かれたので、歩き旅の話をしたら、ミカンを3個いただいた。四国遍路では、当たり前にあるお接待をここでいただくとは思わなかった。

やがて、神崎川に架かる神崎橋を渡る。川の向こうは尼崎市となる。

神崎川を渡って、旧街道の細い道へ入ったら、新しい家ではあるが、旧家とおぼしき立派な家が建っていた。この付近に渡し場があったので、祖先は当時から財をなした家かもしれない。

土手沿いに南下して、神崎橋の下をくぐって行くと、「身代一心地蔵尊」がある。説明板を読むと、新田義貞、楠正成軍と足利尊氏軍とが戦い、正成の軍は神崎の辺りから神出鬼没、一心をこめた戦いにより、圧勝し高氏軍は遂に九州へと逃げ延びる・・・・世にこれを神崎一心の戦いというと書かれていた。
 長洲中通3丁目の「大門川緑地公園」内に、大きな道標立っている。元の位置は当然違うと思うが、文化五年、「左 尼崎 西宮」、「右 尼崎 大坂」などとある。
長洲中通3丁目の「大門川緑地公園」内に、大きな道標立っている。元の位置は当然違うと思うが、文化五年、「左 尼崎 西宮」、「右 尼崎 大坂」などとある。
尼崎宿~西宮神社

やがて、尼崎市の市街地に入っていく。初めて中国街道についての説明板があった。

その先で、阪神高速3号線沿いの道となる。面白味のない道だが、この辺りが、尼崎宿の中心地だったという。 今はその面影すら感じられない。

高速道路沿いの道から離れて、旧街道へと入っていくと、西本町8丁目の右角に大きな「弘化3年の道標」が立っている。「左 西ノ宮兵庫」 「右 大坂道」 と彫られている。

 武庫川土手にぶつかる。ここは伝説「雉が坂」の場所である。天正10年、本能寺の変を知り備中から急ぎ引き返す秀吉一行がこのあたりまで来た時、農夫の知らせで川の向うを見ると、あわただしく雉が飛び立つのが見えたため、明智光秀の兵が待ち伏せしていることを知り、道を変えて難を逃れたという言い伝えが残る所。
武庫川土手にぶつかる。ここは伝説「雉が坂」の場所である。天正10年、本能寺の変を知り備中から急ぎ引き返す秀吉一行がこのあたりまで来た時、農夫の知らせで川の向うを見ると、あわただしく雉が飛び立つのが見えたため、明智光秀の兵が待ち伏せしていることを知り、道を変えて難を逃れたという言い伝えが残る所。
説明板によると、左側の坂は現在の坂で、右手へ上る坂が昔はあったようである。
 やがて、琴浦通りを進む。蓬川沿いの紅葉がきれいだったので、カメラに収めた。
やがて、琴浦通りを進む。蓬川沿いの紅葉がきれいだったので、カメラに収めた。
この先で、ネパールカレー屋を見つけたので、昼食にした。やはり、ネパール人が店主だった。久し振りにナンを食べた。

琴浦通りは、いつの間にか「旧国道」となり、今日のゴールの西宮神社まで続いていた。昔の中国街道がそのまま国道になったのだろう。左奥は甲子園球場である。

ゴールが近くなり、京都から大阪を通らないで、西宮まで来る西国街道との合流地点たが、標識はなかった。

13:40、今日のゴール、西宮神社の表大門に到着。

時間があるので、広い境内の中を見て歩いた。七五三の日らしく、七五三の子供たちと家族で大にぎわいだった。
この西宮の地名の由来にもなっている西宮神社だが、、古事記、日本書紀に書かれる・・・伊邪那岐、伊邪那美二柱の大神が最初に生み給いしお子は骨のない蛭児であり、吾が子をあわれと思いつつも、葦船に入れて海へ流してしまわれた。その流された蛭児の神が、この地あたりに流れ着き、祀ったのが西宮神社であるという。
天文3年(1534)の兵火により焼き尽された境内も、慶長9年(1604) から秀頼により拝殿、本殿等全て元に復したと言われています。国宝だった本殿は、先の空襲により焼失してしまったが、昭和36年、ほぼ元通りに復興された。
大阪からここまでを中国街道といい、明日からは山陽道となる。

ゴールから旧街道を5分ほど戻った所に、今日のホテルリブマックス西宮がある。移動の必要のない立地がうれしい。
チェックインできる15:00まで近くの公園で時間を潰した。
普段は高くて泊まらない6485円だが、GoToで4216円になり、やはり地域クーポン券が付いてきた。半額で泊まるようなもの。
早くゴールしたので、18時過ぎにはブログアップ完了。これから、夕食を食べに出て、早く寝ようと思う。
歩数計43000歩





































 追分には道標があり、
追分には道標があり、








 油掛通を左折すると京橋へ行くが、その手前を左に入った所に寺田屋事件で有名な「寺田屋」がある。再建されているが、現在も営業をしている宿屋である。坂本龍馬の定宿で、おりょうさんとの恋の宿としても知られている。
油掛通を左折すると京橋へ行くが、その手前を左に入った所に寺田屋事件で有名な「寺田屋」がある。再建されているが、現在も営業をしている宿屋である。坂本龍馬の定宿で、おりょうさんとの恋の宿としても知られている。

 伏見みなと公園の「伏見みなと橋」~ここは江戸時代の港ではなく、戦時中の河川輸送の為に造られたものだそうだ。「三十石船」をイメージしたベンチがあり、常夜燈も立ち、橋も架かっている。
伏見みなと公園の「伏見みなと橋」~ここは江戸時代の港ではなく、戦時中の河川輸送の為に造られたものだそうだ。「三十石船」をイメージしたベンチがあり、常夜燈も立ち、橋も架かっている。
 やがて土手を下り、
やがて土手を下り、