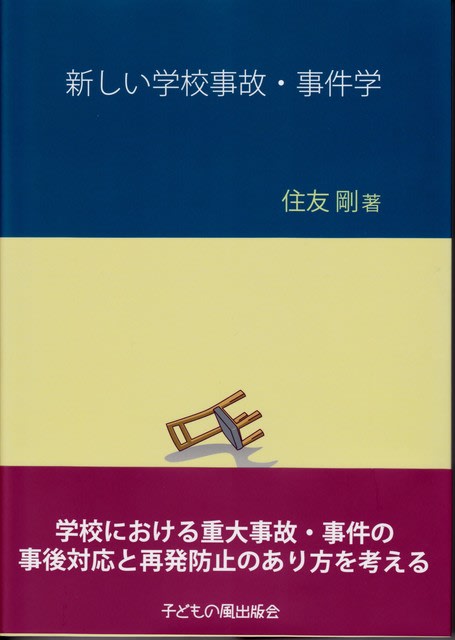昨日は朝から新幹線に乗って、文部科学省の安全教育推進室というところへ行ってきました。
ちなみに、ここの正式名称がほんと長くて・・・。なにしろ「文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課」のなかの「安全教育推進室」ですからねぇ。
でもこれって、たとえばどこかの自治体教育委員会の事務局がつかっているみたいに、「人権教育・安全課」「共生教育・安全課」という名称にしたらスッキリするのにねぇ。あるいは「すこやか・あんしん教育課」みたいなキラキラネームにするとか。他にもいろんな名前の付け方があると思うのに…。
でもまあ、正式名称はさておき、この安全教育推進室が、学校内外の子どもの事故防止や安全確保策、あるいは防災教育などを担当する文科省の部署であることにはまちがいありません。
そこへ何をしに行ったかといいますと…。3年前の2016年3月に文科省の「学校事故対応に関する調査研究有識者会議」で検討して、各地の教育委員会・学校現場に発信した「学校事故対応に関する指針」の運用の現状や課題について意見交換をするためです。
まあ、ここで詳しいことはあまり書けませんが…。でも、文科省の担当部署なりにはあの「指針」をつくった以上、責任をもっていろいろと動かねば…と思っておられるようで、その点では安心しました。
その上での話ですが、昨日も文科省でそういう伝え方をしたのですが、ちょうど建物の4階部分にあたる文科省から、3階部分の都道府県教委、2階部分の市区町村教委、そして1階部分の学校現場で起きている諸課題を、どこまで的確に把握しているのか。また、4階の文科省からリリースした「学校事故対応に関する指針」が、1階の学校現場ではどのように理解され、運用されているのかを確認しているのか。そういう点で、文科省なりにいろいろと調べて確かめたり、その確認の結果をふまえて対応を考えたりしなければいけない課題があるように、少なくとも私としては思っています。
また、学校事故・事件の被害者家族や遺族は、4階の文科省から1階の学校現場で起きていることを「なんとかしてほしい」と思ってくり返し陳情や意見書・要望書提出などを行うわけですが(なお、文科省の担当官は一応、提出された要望書や意見書を読んでいるようですし、陳情も話自体は聞いています)。でも、その3階~2階~1階に対して、4階にいる文科省から何を、どのように働きかけていけばいいのか。特に「教育の地方分権」という枠組みのなかで、何ができるのか。そこがよくわからないようにも見受けられました。
ただ、この安全教育推進室のみなさんは、先ほども書きましたが、「指針」をつくった以上は「なにか、やらねば」という思いは強く持っています。その点は、まちがいありません。でも、具体的なノウハウが見つからない、何から手をつければいいかわからない、そういうもどかしさがあるように感じました。
となれば・・・。変わらなければいけないのは、私たちの側ですね。文科省や地方教育行政の当局が学校現場に対して、具体的に「何を、どのような手順で、どのように働きかければいいのか?」というノウハウといいますか、「実務」の部分で、どれだけ実効性のある提案を出せるかどうか。文科省や地方教育行政を「けしからん!」と言うだけではなくて、こちら側から提案のかたちで、「実務的」に改善のポイントやハウトゥをしめして、どういう風に問題のある部分の是正をはたしていくのか。そこが今後、私たちの側にも問われているように思いました。
ちなみに安全教育推進室のみなさんのあいだで、どうやら私の書いた『新しい学校事故・事件学』(子どもの風出版会、2017年)が読まれているようです。「ありがたい話だなあ」って思います。
あと、併せて、2月に出る予定の『「いじめ防止対策」と子どもの権利』(鈴木庸裕・桝屋二郎との共編著、かもがわ出版、2020年)のチラシを安全教育推進室に置いてきました。ここから初等中等教育局の児童生徒課(=こちらが生徒指導施策、いじめ対策や自死予防に関することに取り組む部署です)にチラシがまわって、予約注文してくれるといいのですが・・・。