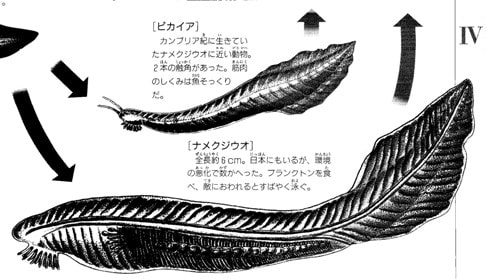私たち哺乳類のご先祖さまである哺乳類型爬虫類=単弓類は、12月23日(2億9千万年前)頃、古生代ペルム紀に大繁栄します。
(最近、哺乳類型爬虫類は、「爬虫類」と名がつくものの、実は爬虫類とは別のグループではないかという考えが強くなりつるあるようですが。)
しかし、12月24日(2億4千5百万年前)頃、古生代末に起った生物の大量絶滅によって、哺乳類型爬虫類もほとんど死滅してしまいました。
古生代末の大量絶滅は、中生代末の恐竜やアンモナイトの絶滅の規模をはるかに超えた大変なものだったようです。
ここで、もし私たちの直系のご先祖さまである哺乳類型爬虫類が一匹残らずダウンしてしまっていたなら、今の私たちはいなかったのですが、ご先祖さまたちの一部が、おそらく頑張りと幸運とでかろうじて生き延びてくれたのです。
これは、ほとんど奇跡といってもいいくらいのことです。
続いて、12月25日、中生代三畳紀に入り、他の爬虫類のなかまが恐竜へと進化します。
そして次の12月26日、ジュラ紀には、恐竜には巨大な体をもつものも現われ、それから長い間――1億年あまりも?――地球上を我がもの顔に歩いていたようです。
もちろん、それは草食性恐竜を支えるだけの植物があり、その草食性恐竜を食べる肉食性恐竜も生きられたということです。
さらにいえば、それだけの植物を生育させるような暖かい気候条件があったということでもあります。
そうした恐竜とほぼ並行して、辛うじて絶滅を免れた哺乳類型爬虫類から哺乳類が進化してきます。
しかし、先祖である哺乳類型端虫類が君臨していた生態系の頂点の座を恐竜に奪われ、哺乳類は、彼らの繁栄の陰でいわばひっそりと生きていかざるをえなくなりました。
最初の哺乳類は、ハツカネズミくらいの小さな動物だっただろうといわれています。
爬虫類や恐竜は、いわゆる「変温動物」で、周りの気温が下がると、体温も下がり、活動できなくなります。
それに対して、哺乳類は、「恒温動物」で、自力で体温を保つことができますから、温度が下がっても活動できます。
そういうわけで、小さな哺乳類は、温度が下がり恐竜の眠っている夜に活動することができたので、何とか生き延びることができたようです。
自分を変え、新しいライフスタイルを考案し、億年単位にわたって、ひそやかに、ささやかに、しかし粘り強くいのちを伝え続けている小さな哺乳類のご先祖さまのことを想像すると、私はちょっと胸がいっぱいになります。
(ただし最近、「羽毛恐竜」の発見が相次ぎ、小型肉食恐竜と鳥類との類縁関係が強く示唆され、少なくとも一部の恐竜は恒温だったのではないかという「恐竜恒温動物説」も有力になってきているそうです。)
さて、ここでも確認しておきたいことは、最初の哺乳類は、私たちの直系のご先祖さまだということです。
そして、哺乳類で初めて、はっきりとした情動・感情のセンターである大脳の辺縁系が出来ています。
喜びや悲しみといった感情は、私たち人間の発明したものでもなければ、独占物でもなく、哺乳類のご先祖さまから受け継いだものであり、他の哺乳類と共有しているんですね。
だから、私たちは、体温・血の冷たいヘビやトカゲではなく、温かいイヌやネコと気持ちが通じやすいという気がするのかもしれません。
例えば愛犬を飼っておられる方、彼らとはもうまちがいなく愛情のコミュニケーションが成り立っているとお感じになりませんか?
ともかく、哺乳類-大脳辺縁系の創発と共に、宇宙には喜びや悲しみや愛情といった感情が創発したのです。
こうして宇宙は、本能と衝動だけでなく、豊かな感情のある世界へと、まさにより豊かに美しく進化してきたのだといっていいでしょう。
人気blogランキングへ

(最近、哺乳類型爬虫類は、「爬虫類」と名がつくものの、実は爬虫類とは別のグループではないかという考えが強くなりつるあるようですが。)
しかし、12月24日(2億4千5百万年前)頃、古生代末に起った生物の大量絶滅によって、哺乳類型爬虫類もほとんど死滅してしまいました。
古生代末の大量絶滅は、中生代末の恐竜やアンモナイトの絶滅の規模をはるかに超えた大変なものだったようです。
ここで、もし私たちの直系のご先祖さまである哺乳類型爬虫類が一匹残らずダウンしてしまっていたなら、今の私たちはいなかったのですが、ご先祖さまたちの一部が、おそらく頑張りと幸運とでかろうじて生き延びてくれたのです。
これは、ほとんど奇跡といってもいいくらいのことです。
続いて、12月25日、中生代三畳紀に入り、他の爬虫類のなかまが恐竜へと進化します。
そして次の12月26日、ジュラ紀には、恐竜には巨大な体をもつものも現われ、それから長い間――1億年あまりも?――地球上を我がもの顔に歩いていたようです。
もちろん、それは草食性恐竜を支えるだけの植物があり、その草食性恐竜を食べる肉食性恐竜も生きられたということです。
さらにいえば、それだけの植物を生育させるような暖かい気候条件があったということでもあります。
そうした恐竜とほぼ並行して、辛うじて絶滅を免れた哺乳類型爬虫類から哺乳類が進化してきます。
しかし、先祖である哺乳類型端虫類が君臨していた生態系の頂点の座を恐竜に奪われ、哺乳類は、彼らの繁栄の陰でいわばひっそりと生きていかざるをえなくなりました。
最初の哺乳類は、ハツカネズミくらいの小さな動物だっただろうといわれています。
爬虫類や恐竜は、いわゆる「変温動物」で、周りの気温が下がると、体温も下がり、活動できなくなります。
それに対して、哺乳類は、「恒温動物」で、自力で体温を保つことができますから、温度が下がっても活動できます。
そういうわけで、小さな哺乳類は、温度が下がり恐竜の眠っている夜に活動することができたので、何とか生き延びることができたようです。
自分を変え、新しいライフスタイルを考案し、億年単位にわたって、ひそやかに、ささやかに、しかし粘り強くいのちを伝え続けている小さな哺乳類のご先祖さまのことを想像すると、私はちょっと胸がいっぱいになります。
(ただし最近、「羽毛恐竜」の発見が相次ぎ、小型肉食恐竜と鳥類との類縁関係が強く示唆され、少なくとも一部の恐竜は恒温だったのではないかという「恐竜恒温動物説」も有力になってきているそうです。)
さて、ここでも確認しておきたいことは、最初の哺乳類は、私たちの直系のご先祖さまだということです。
そして、哺乳類で初めて、はっきりとした情動・感情のセンターである大脳の辺縁系が出来ています。
喜びや悲しみといった感情は、私たち人間の発明したものでもなければ、独占物でもなく、哺乳類のご先祖さまから受け継いだものであり、他の哺乳類と共有しているんですね。
だから、私たちは、体温・血の冷たいヘビやトカゲではなく、温かいイヌやネコと気持ちが通じやすいという気がするのかもしれません。
例えば愛犬を飼っておられる方、彼らとはもうまちがいなく愛情のコミュニケーションが成り立っているとお感じになりませんか?
ともかく、哺乳類-大脳辺縁系の創発と共に、宇宙には喜びや悲しみや愛情といった感情が創発したのです。
こうして宇宙は、本能と衝動だけでなく、豊かな感情のある世界へと、まさにより豊かに美しく進化してきたのだといっていいでしょう。
人気blogランキングへ