旅から旅への生活、たまに帰れば家族と喧嘩、ヤクザな稼業、口は悪いが不思議と人に好かれる…って映画を観ました。
お、寅さんかい?
いいえ、クリントさんです。

『ミスティックリバー』から『グラン・トリノ』くらいまでを濃厚なワインとするなら、『運び屋』は軽口なハウスワインの味わい。どちらかといえば『トゥルークライム』や『ブラッドワーク』のころのノリに近い。とはいえ、そうした20年くらい前のハウスワインよりも、クリントの年月を経た上での今が反映されていてやはり独特の味わい深さがある。
物語的にちょっともやっとするのは、あの麻薬組織のその後は描かなくて良いのだろうかというところ。怒り狂って腹いせに家族を襲ったりしないのだろうか。
おそらく、映画の中で描いていないだけで、彼らは捕まったのかもしれないし、家族もDEAが厳重に警護して悪い奴らも手が出せなくなってるのかもしれない。映画の本筋とは関係ないからと意図的にオミットしたのかもしれない。
クリント映画では複数の当事者が関わるストーリーで、視点をある一つに限定することは珍しくないので、特にこのことを重大な欠点とするつもりはない。
ただし、私が『運び屋』を軽口のハウスワイン風と評したのは組織のその後を描かないからでなく、10年前のクリント映画なら描いたであろう「代償」や「業」が無いからだ。
クリント・イーストウッドの映画はいつも私正義を描いてきた。正義は国や社会が決めるのではなく、個人の判断だった。
しかし単に「俺が法だ」ドギューーン!って映画と違い、90年代以降は私正義の代償を描いていた。
『グラン・トリノ』の主人公の中盤の行動は感情的には理解できるが、彼はそのために大好きな女の子がレイプされる事態に直面する。まさに私正義の代償だ。
『ミスティックリバー』や『ミリオンダラー・ベイビー』は業を背負う物語だった。間違いだと気付いてももはや否定できなかったり、正しいと信じていてもそれを背負うのは辛かったり、そんな業があった。
しかし「運び屋」のクリントは、「家族が一番大事」というわりと陳腐な気づきに対して物語の中で代償を負わないし、業を背負い込むでも無い。
むしろストーリー序盤で提示された代償や業から解放されることになる。
(ここまで書いて思ったが『ブラッドワーク』も軽口映画と言ったがあれだってクリントは自身の心臓というあまりに重い業を抱えていくことになる物語でなにかダーティーハリー外伝っぽい刑事と異常者のサスペンスで見た当初は大喜びしたけど、00年代クリント作品的重さも内包した中々深い映画だったんだなーと)
でも何にせよ、いつ遺作になってもいいように真剣に…の割にユーモラスで神々しい映画を撮っていたゼロ年代クリントと比べると、逆に達観したような、もう語りたい事なんか大してないよ、人間って面白いなーと、ものすごいリラックス感があり、これはこれでクリントの境地では無いかとすら思える。
アメリカの映画批評サイトRotten Tomatoesでの支持率は60パーセントくらいとの事で、アメリカではあまり評価はされてないようだ。おそらく上記に書いたような軽さが原因だろう。
こないだ観た『ギルティ 』なんかは支持率100パーセントとかなんとか。
アメリカでクリントは過小評価されがちな傾向があると思うけど。
なに言ってんの?日本が過大評価してんだろ、特にキネ旬が、とアメリカ人に言い返されそうだが、まあでも「いいもんはいい」それだけだ。
アメリカ人がJ Jエイブラムズとかアレキサンダーペインとかデビッドラッセルとか持ち上げすぎな事の方がよっぽどわからん。
----
家族が大切とか言うクリントご本人は結婚、離婚を繰り返し、あまり家族想いでもない気もするが、だからこの映画のキャラは自分自身の投影なんだろう。
ゴシップニュースによると、クリントは最近20代の新恋人が出来たらしく、『運び屋』中盤の3pシーンとかも自身の投影という事で良いのかもしれない。
作劇においては前半の悪事に染まっていく過程はとても面白い。なぜそうなったのか?を90年代ゼロ年代はあまり語らなかったクリントだが10年代はそこまでの過程にも重きを置いているように思えて興味深い。
そしてクリントは作品で、字面だけ追えばポリコレ的にギリギリアウトな発言を繰り返す。でも彼と出会う人はなぜか彼を憎めない。文章ではうまく表現できない人間的魅力がある。映画内でクリントがインターネットをバカにする箇所がいくつかあるが、みなグーグルやツイッターで情報を簡単に仕入れ、文字や写真だけで判断する傾向にあるが、クリントが言いたいことは人間なんて合って喋ってみないとわからん、まず人と向き合え、と言うことだ。その点ではケン・ローチ『私は、ダニエル・ブレイク』にも通じるテーマだ。爺さんたちはみんなそんなことを思うのか。
----
キャスト陣雑感
ブラッドリー・クーパーの夢の企画「アメリカンスナイパー」を監督する交換条件で、今度俺が撮りたい映画に出ろよ、という約束でもしたのだろうか。
2人の会話シーンはとりたててすごい台詞でも映像でもないのに、何だかすごく印象深い。
モーフィアスアじゃなくてローレンス・フィッシュバーンも常連のような安定感あるが、考えてみるとミスティックリバー以来か
お恥ずかしいことにアンディ・ガルシアだってことにエンドロールまで気づきませんで
ダイアン・ウィーストは貫禄ですね
クリントのパートナーの女性が映画に登場するのって、スペースカウボーイ以来か
----
音楽について
今回クリント映画の音楽を、クリント本人か、クリントの息子か、あるいはレニー・ニーハウス以外の人物が手がけるという珍しいケース…と思ったけど『ハドソン川の奇跡』もそうだったし最近はあまり珍しくもないのか。
ともかく、今回の音楽はアルトゥロ・サンドバルという方で、どっかで聞いた名前だなと思ってて、映画終わってエンドロールでその名を見た時に突然思い出した。
デイブ・グルーシンのアルバムによく参加していたトランペット奏者だ。『ハバナ』サントラはのトランペットは特に素晴らしかった。
ただし映画音楽の作曲家としては、やや過剰というかドラマチックにしようとしすぎているように感じた。クリント・イーストウッド作曲のシンプルすぎて泣ける曲には到底かなわない。それでもエンドクレジットのトランペット主体のジャジーな曲はなんとなくイーストウッド好みの落ち着いた感じ。刑務所で悠々自適?に花を育てているクリントの顔が思い浮かぶようないい曲だった。
----
『運び屋』
監督 クリント・イーストウッド
脚本 ニック・シェンク
撮影 イブ・ベランジェ
音楽 アルトゥロ・サンドバル
出演 クリント・イーストウッド、ブラッドリー・クーパー、ローレンス・フィッシュバーン、ダイアン・ウィースト、アンディ・ガルシア
2019年3月 TOHOシネマズ六本木にて鑑賞
お、寅さんかい?
いいえ、クリントさんです。

『ミスティックリバー』から『グラン・トリノ』くらいまでを濃厚なワインとするなら、『運び屋』は軽口なハウスワインの味わい。どちらかといえば『トゥルークライム』や『ブラッドワーク』のころのノリに近い。とはいえ、そうした20年くらい前のハウスワインよりも、クリントの年月を経た上での今が反映されていてやはり独特の味わい深さがある。
物語的にちょっともやっとするのは、あの麻薬組織のその後は描かなくて良いのだろうかというところ。怒り狂って腹いせに家族を襲ったりしないのだろうか。
おそらく、映画の中で描いていないだけで、彼らは捕まったのかもしれないし、家族もDEAが厳重に警護して悪い奴らも手が出せなくなってるのかもしれない。映画の本筋とは関係ないからと意図的にオミットしたのかもしれない。
クリント映画では複数の当事者が関わるストーリーで、視点をある一つに限定することは珍しくないので、特にこのことを重大な欠点とするつもりはない。
ただし、私が『運び屋』を軽口のハウスワイン風と評したのは組織のその後を描かないからでなく、10年前のクリント映画なら描いたであろう「代償」や「業」が無いからだ。
クリント・イーストウッドの映画はいつも私正義を描いてきた。正義は国や社会が決めるのではなく、個人の判断だった。
しかし単に「俺が法だ」ドギューーン!って映画と違い、90年代以降は私正義の代償を描いていた。
『グラン・トリノ』の主人公の中盤の行動は感情的には理解できるが、彼はそのために大好きな女の子がレイプされる事態に直面する。まさに私正義の代償だ。
『ミスティックリバー』や『ミリオンダラー・ベイビー』は業を背負う物語だった。間違いだと気付いてももはや否定できなかったり、正しいと信じていてもそれを背負うのは辛かったり、そんな業があった。
しかし「運び屋」のクリントは、「家族が一番大事」というわりと陳腐な気づきに対して物語の中で代償を負わないし、業を背負い込むでも無い。
むしろストーリー序盤で提示された代償や業から解放されることになる。
(ここまで書いて思ったが『ブラッドワーク』も軽口映画と言ったがあれだってクリントは自身の心臓というあまりに重い業を抱えていくことになる物語でなにかダーティーハリー外伝っぽい刑事と異常者のサスペンスで見た当初は大喜びしたけど、00年代クリント作品的重さも内包した中々深い映画だったんだなーと)
でも何にせよ、いつ遺作になってもいいように真剣に…の割にユーモラスで神々しい映画を撮っていたゼロ年代クリントと比べると、逆に達観したような、もう語りたい事なんか大してないよ、人間って面白いなーと、ものすごいリラックス感があり、これはこれでクリントの境地では無いかとすら思える。
アメリカの映画批評サイトRotten Tomatoesでの支持率は60パーセントくらいとの事で、アメリカではあまり評価はされてないようだ。おそらく上記に書いたような軽さが原因だろう。
こないだ観た『ギルティ 』なんかは支持率100パーセントとかなんとか。
アメリカでクリントは過小評価されがちな傾向があると思うけど。
なに言ってんの?日本が過大評価してんだろ、特にキネ旬が、とアメリカ人に言い返されそうだが、まあでも「いいもんはいい」それだけだ。
アメリカ人がJ Jエイブラムズとかアレキサンダーペインとかデビッドラッセルとか持ち上げすぎな事の方がよっぽどわからん。
----
家族が大切とか言うクリントご本人は結婚、離婚を繰り返し、あまり家族想いでもない気もするが、だからこの映画のキャラは自分自身の投影なんだろう。
ゴシップニュースによると、クリントは最近20代の新恋人が出来たらしく、『運び屋』中盤の3pシーンとかも自身の投影という事で良いのかもしれない。
作劇においては前半の悪事に染まっていく過程はとても面白い。なぜそうなったのか?を90年代ゼロ年代はあまり語らなかったクリントだが10年代はそこまでの過程にも重きを置いているように思えて興味深い。
そしてクリントは作品で、字面だけ追えばポリコレ的にギリギリアウトな発言を繰り返す。でも彼と出会う人はなぜか彼を憎めない。文章ではうまく表現できない人間的魅力がある。映画内でクリントがインターネットをバカにする箇所がいくつかあるが、みなグーグルやツイッターで情報を簡単に仕入れ、文字や写真だけで判断する傾向にあるが、クリントが言いたいことは人間なんて合って喋ってみないとわからん、まず人と向き合え、と言うことだ。その点ではケン・ローチ『私は、ダニエル・ブレイク』にも通じるテーマだ。爺さんたちはみんなそんなことを思うのか。
----
キャスト陣雑感
ブラッドリー・クーパーの夢の企画「アメリカンスナイパー」を監督する交換条件で、今度俺が撮りたい映画に出ろよ、という約束でもしたのだろうか。
2人の会話シーンはとりたててすごい台詞でも映像でもないのに、何だかすごく印象深い。
モーフィアスアじゃなくてローレンス・フィッシュバーンも常連のような安定感あるが、考えてみるとミスティックリバー以来か
お恥ずかしいことにアンディ・ガルシアだってことにエンドロールまで気づきませんで
ダイアン・ウィーストは貫禄ですね
クリントのパートナーの女性が映画に登場するのって、スペースカウボーイ以来か
----
音楽について
今回クリント映画の音楽を、クリント本人か、クリントの息子か、あるいはレニー・ニーハウス以外の人物が手がけるという珍しいケース…と思ったけど『ハドソン川の奇跡』もそうだったし最近はあまり珍しくもないのか。
ともかく、今回の音楽はアルトゥロ・サンドバルという方で、どっかで聞いた名前だなと思ってて、映画終わってエンドロールでその名を見た時に突然思い出した。
デイブ・グルーシンのアルバムによく参加していたトランペット奏者だ。『ハバナ』サントラはのトランペットは特に素晴らしかった。
ただし映画音楽の作曲家としては、やや過剰というかドラマチックにしようとしすぎているように感じた。クリント・イーストウッド作曲のシンプルすぎて泣ける曲には到底かなわない。それでもエンドクレジットのトランペット主体のジャジーな曲はなんとなくイーストウッド好みの落ち着いた感じ。刑務所で悠々自適?に花を育てているクリントの顔が思い浮かぶようないい曲だった。
----
『運び屋』
監督 クリント・イーストウッド
脚本 ニック・シェンク
撮影 イブ・ベランジェ
音楽 アルトゥロ・サンドバル
出演 クリント・イーストウッド、ブラッドリー・クーパー、ローレンス・フィッシュバーン、ダイアン・ウィースト、アンディ・ガルシア
2019年3月 TOHOシネマズ六本木にて鑑賞

















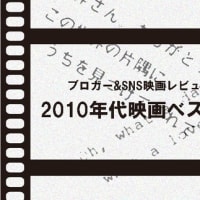








音楽つくるのもトシだしめんどくせーよっていう感じなのかもしれないですね
サンドバルさんも調べると69歳と結構なお年で、クリントからみたらキッドかもしれないですけど、年配者同士でどっかのジャズバーで意気投合したのかもしれませんね